蓮実重彦の『夏目漱石論』を紹介しましたので,同じ題名を有するものとして,権藤三鉉の『夏目漱石論』も取り上げます。

同じ題名のものとしてこれを選んだのには理由があります。蓮実重彦のものはかなりヘビーな夏目漱石の小説のファン向けであるのに対し,こちらはライトなファンに向けたものという一面があります。つまり対極にある同名の書物ということで,これを選びました。
ハードカバーですがそれほど厚さはなく,文字も大きめになっています。わりと簡単に,短時間で読むことが可能です。内容としても,初心者というか入門書的な性格ですので,それほど難しいことが書かれているわけでもありません。蓮実のものは漱石の小説を手繰らなければならないシーンが何度も僕にはありましたが,権藤のものにはその必要がありませんでした。逆にいったらコアな漱石ファンにとっては,やや退屈に感じてしまうおそれがあるかもしれません。
作家論と作品論とで分類すると,作家論としての傾きがやや強いかもしれません。ただ,『漱石の世界』ほどはっきりとした傾向があるわけではないです。
全5章から成っていて,章ごとの連結というのはあまり深く感じられません。各々の章はそれ自体で独立しているといった方がよいでしょう。おそらく最も筆者の力が入っているのは第2章の作品論ではないかと思います。『それから』,『彼岸過迄』,『行人』,『こころ』,『明暗』の五作品が取り上げられています。この部分はさすがに未読では厳しいのではないかと思いますが,1度でも読んだことがあるなら,理解するのにそれほど難しいところはない筈です。
あまり大きな期待を寄せてはいけないという気はしますが,手ごろに読めるのですから,読んでマイナスになるということは絶対にないだろうと思います。
ゲルーの主眼点は,もうひとつ,『エチカ』の別の個所によって補強されています。第一部定理二八備考の最後の部分でスピノザが主張していることです。
「神を個物の遠隔原因と名づけるのは,神が直接的に産出したもの・あるいはむしろ神の絶対的本性から生起するものと普通の個物とを区別するためになら別だが,本来的意味においては適当でないということになる」。
同じ第一部定理二八備考の直前の部分において,スピノザは神は物の絶対的な最近原因である,とくに自己の類における最近原因であるというわけではなく,絶対的な最近原因であるという考え方を表明しています。スコラ哲学においてその最近原因の対義語に該当するのが遠隔原因です。スピノザはこの部分ではスコラ哲学に準じて用語を使っています。ですから神が最近原因,とりわけ絶対的な最近原因であるということを主張したならば,それは遠隔原因ではないということを主張するのも当然であるといえます。
さらにこの部分の直後に,スピノザは遠隔原因に関してさらなる説明をしています。それによれば,遠隔原因とは,結果とは一切の関連性を有しないような原因と理解されなければなりません。ところが第一部定理一五にあるように,一切の事物は神のうちに存在しますし,神がなければ存在することができないのはもちろん,概念conceptusすることさえできないものなのです。いい換えれば一切の事物はそのように神に依存しています。よって神は結果である一切の事物と何らの関連性ももたないような原因ではありません。だから神が遠隔原因であるという主張は誤りであるということになります。
僕の考えを先に述べれば,スピノザがここでいいたかったことはこれがすべてです。しかし,ゲルーはこのことのうちに,もう少し別の意味を見出すのです。少なくともそこに一理あるということは,僕も認めざるを得ません。神を遠隔原因と名付けることが本来的な意味,すなわちスコラ哲学的な意味においては不適当であるというなら,本来的ではない意味においては,適当であると理解可能な場合があるというように受け取ることは可能だからです。

同じ題名のものとしてこれを選んだのには理由があります。蓮実重彦のものはかなりヘビーな夏目漱石の小説のファン向けであるのに対し,こちらはライトなファンに向けたものという一面があります。つまり対極にある同名の書物ということで,これを選びました。
ハードカバーですがそれほど厚さはなく,文字も大きめになっています。わりと簡単に,短時間で読むことが可能です。内容としても,初心者というか入門書的な性格ですので,それほど難しいことが書かれているわけでもありません。蓮実のものは漱石の小説を手繰らなければならないシーンが何度も僕にはありましたが,権藤のものにはその必要がありませんでした。逆にいったらコアな漱石ファンにとっては,やや退屈に感じてしまうおそれがあるかもしれません。
作家論と作品論とで分類すると,作家論としての傾きがやや強いかもしれません。ただ,『漱石の世界』ほどはっきりとした傾向があるわけではないです。
全5章から成っていて,章ごとの連結というのはあまり深く感じられません。各々の章はそれ自体で独立しているといった方がよいでしょう。おそらく最も筆者の力が入っているのは第2章の作品論ではないかと思います。『それから』,『彼岸過迄』,『行人』,『こころ』,『明暗』の五作品が取り上げられています。この部分はさすがに未読では厳しいのではないかと思いますが,1度でも読んだことがあるなら,理解するのにそれほど難しいところはない筈です。
あまり大きな期待を寄せてはいけないという気はしますが,手ごろに読めるのですから,読んでマイナスになるということは絶対にないだろうと思います。
ゲルーの主眼点は,もうひとつ,『エチカ』の別の個所によって補強されています。第一部定理二八備考の最後の部分でスピノザが主張していることです。
「神を個物の遠隔原因と名づけるのは,神が直接的に産出したもの・あるいはむしろ神の絶対的本性から生起するものと普通の個物とを区別するためになら別だが,本来的意味においては適当でないということになる」。
同じ第一部定理二八備考の直前の部分において,スピノザは神は物の絶対的な最近原因である,とくに自己の類における最近原因であるというわけではなく,絶対的な最近原因であるという考え方を表明しています。スコラ哲学においてその最近原因の対義語に該当するのが遠隔原因です。スピノザはこの部分ではスコラ哲学に準じて用語を使っています。ですから神が最近原因,とりわけ絶対的な最近原因であるということを主張したならば,それは遠隔原因ではないということを主張するのも当然であるといえます。
さらにこの部分の直後に,スピノザは遠隔原因に関してさらなる説明をしています。それによれば,遠隔原因とは,結果とは一切の関連性を有しないような原因と理解されなければなりません。ところが第一部定理一五にあるように,一切の事物は神のうちに存在しますし,神がなければ存在することができないのはもちろん,概念conceptusすることさえできないものなのです。いい換えれば一切の事物はそのように神に依存しています。よって神は結果である一切の事物と何らの関連性ももたないような原因ではありません。だから神が遠隔原因であるという主張は誤りであるということになります。
僕の考えを先に述べれば,スピノザがここでいいたかったことはこれがすべてです。しかし,ゲルーはこのことのうちに,もう少し別の意味を見出すのです。少なくともそこに一理あるということは,僕も認めざるを得ません。神を遠隔原因と名付けることが本来的な意味,すなわちスコラ哲学的な意味においては不適当であるというなら,本来的ではない意味においては,適当であると理解可能な場合があるというように受け取ることは可能だからです。











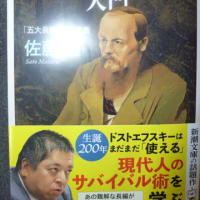
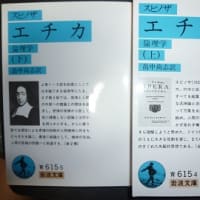

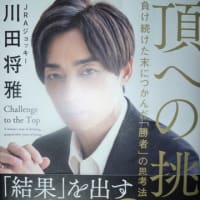





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます