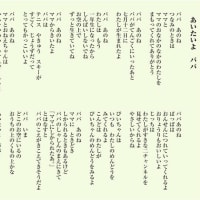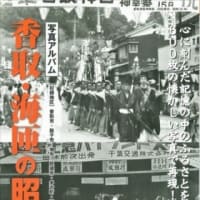仮面の下にあるものは

能や、民俗芸能の本を読んでいた。黒仮面のフォークロアという本の一部分コピーを昨日はやっていた。中に、狩りをおこなった集落で、イノシシの頭部を切り取り、神社に奉納するしきたりを持っているところがあることを知った。狩りを行うというところがキーワードである。写真付きであった。なんとも不気味であった。しかし、なぜそのイノシシの死んだ顔が、仮面の本に出ているのかと思った。はっとなった。仮面というものは、そういうものだったのだと思った。
つまり精霊の、あるいは怨霊の祟りを鎮めるものであるのかも知れないと思い至ったからである。
だとしたら、芸能で仮面をかぶるというのは、そういう面もあるのかもしれないと考え始めたからである。つまり、それほど覆い尽くさなければならないほど、現実はシビアーだからだ。そう思った。現実は確かに生きるのに難い。困難が多い。だからこそ、それにフタをしたくなってしまう。嫌な奴は、釜の中に閉じ込めて、フタをしたくなる。出てこないでほしいというわけだ。祟りもそうだ。出てこないでほしいというわけだ。
感情が表に出ている仮面というのは、わかりやすい。怒りの表情をしているもの、笑い顔のもの、哀しみを現しているもの等々たくさんある。
しかしながら、だからと云ってそれをそのまま受け取るのも問題がある。
例えば、八重山のミロク神。笑い顔の素敵な実にいい顔をなされている。見ているこっちまで、仕合わせになるような仮面である。しかし、鵜呑みにしてはならない。どこまでホントに笑っておられるのか、わかったもんじゃない。仮面の下には、おおいなる悲劇があるのかもしれない。あるいは、怒りがあるのかもしれない。またまた、諧謔があるのかもしれない。表ヅラは笑顔でも、まったく違った面があるのかもしれない。
だから我々は(オレだけかもしれないが)、表情だけで人を判断してはいかんのである。オレのような男の顔を見て、この人は不幸の始まりを演技してるなんて云っちゃいけねぇのだよん。
(^0^)
オレだって、仮面をかぶっているのである。聞きたくないことは、聞きたくない。聞こえないふりをすることも当然あるのだ。ミミが悪くなったことにすることもたくさんあったのだ。それでいいのだ。それで。
でないと耐えられないではないかと思うときもあったからである。
世間なんてそんなもんだ。人には厳しく、自分に甘く。冷たいもんだと思っていたほうが、裏切られたときのショックが軽く済む。
だからオレは、男性も女性も美男美女であるかどうかなんてくだらないことを判断の基準にはしない。美男美女というのも仮面の一つであるとしか思っていないからである。誰だって、「魔」というものが、顔という仮面の下にはあるからである。魔女の「魔」である。恨みとか、呪いとか、怒りとか、嫉妬とか、人間には触れられたくないものがあるからである。化粧だって、それらを隠すためにあるとオレは思っているくらいである。
むしろ、自分の持っている「魔」が、強大であればあるほど、我々は(やっぱりこれもオレだけかな?)それを隠す必要があると思うのである。
それをある種のゼッタイ者に預けてしまうという手もあるが。宗教のように。唯一神を奉ずる宗教のように。オレは、意外だろうが、特定の信教がない。信じられないのだ。信じたくてもダメなのだ。なぜか。知的理解でしか接しようとしないからである。これは信者としてはいけない傾向である。ある種のはまる体験を志向しなくてはならないのだろうが、オレにはできない。だから、熱狂的な信仰者からは叱られてしまうのだ。信心が足りないということになってしまうのだ。
音響的効果と云う観点から、コスモロジーという事を最近のオレはよく書く。この間も音のコスモロジーという観点から鬼来迎について書いて郷土史の研究誌に出してみた。そういう観点からしか、オレは宗教に接近できないのだ。オレのような中途半端な人間にはだから救いは無いのである。
それも仮面なのかもしれないのだがねぇ。
ま、ミロク神様のように毎日、あはははは、おほほほと笑って過ごしたいもんでっせ。マジに。
(^_-)-☆