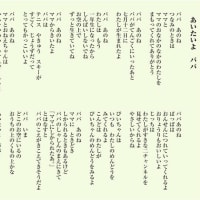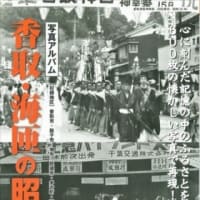1 日本人の特性を現す概念として「集団主義」が標榜されるようになったが、ほんとうにそうであろうかと疑問に思うことがある。このようなことがマスコミを中心としていろいろと書かれるが、マスコミだからと言って全部鵜呑みにしないで、果たしてそれが真実であろうかという疑問を持つこともまた重要であると考えている。また、コミュニケーションにおいてとられる空間行動の文化的違いについても以下に述べてみたい。
2 従来の日本人論について
(1)従来の日本人論というのは、「日本人、あるいは日本文化はどのような特質を持っているか」という議論である。
それは文化的要因を明らかにするという点で、日本文化論と呼ばれることも多い。日本人との比較の対象は、欧米人とりわけアメリカ人である。
日本人は集団主義であるという説がある。
基本的に、日本人は集団主義的だとするものである。集団主義とは、個人より集団を優先する傾向があるとする見方であって、日本人に対する強固なイメージとしてある。集団主義とまったく逆なのが個人主義であるが、集団主義的である日本人は、個人というものが確立していない、和を尊び、常に集団として行動するというものである。
日本人=集団主義説というのは、欧米人の間ではポピュラーになっている日本人観であって、新婚旅行にも団体で出かけると揶揄されているくらいである。
ハリウッド映画にも、集団主義的日本人はよく登場する。『ガンホー』というアメリカの映画には、日産自動車がモデルとなっているのだが、日産の管理職とアメリカの従業員が朝の体操を行おうとすると、アメリカ人従業員は笑ってしまってやろうとはしない。完全に文化的に違っているのである。全てがである。
『菊と刀』で著名なアメリカの人類学者ルース・ベネディクトは、日本人のこうした傾向を恥の文化と名付けた。個我が確立していない日本人は、他人から恥をかかされるのを怖れ、恥が行動の基準となるというのである。(1)
具体的な言説の例としては、英国日産の取締役ピーター・ウィケンズの「日本人はみんな同じような姿かたちで個性がない」、元アメリカ駐日大使のアマコストの「日本の『官界』には敢然として『個』を確立し自己の信念に基づいて哲学や理念を主張する『人間』がいない」等々の言説がある。
(2)日本人論批判
その他多くの日本人論があるが、1960年から1970年にかけてがその最盛期であった。一方、その日本人論を批判する書物も出版されるようになった。その中で、杉本良夫とロス・マオアは二つの点で、日本人論批判を試みている。(2)
一つは、「現実と一致していない」という指摘である。これは、日本人論が和の社会論に集中していて、日本に内部対立が決して無いわけではないという批判である。また、日本の方が労働争議が多いこと、革命の国フランスよりも暴力的なデモが多いこと、農民一揆は江戸時代が終わる頃まで、1600件であったこと、小作争議については第二次世界大戦前の20年間で3200件以上であることなどを指摘している。
二つ目は、「方法が間違っている」という指摘である。それは
①比較がなされていない
②比較がなされている場合でも適切でない
③研究データによる裏付けが乏しい
という批判である。
日本人論批判の結果は、批判自体が正しかったとしても、批判が功を奏しないという意味で、現在もあまり変わっていない。
理由は、
①実証的な証拠が不十分であった
②なぜこれまでの日本人論の通説が圧倒的な支持を誇っているかについて説明が不足している
③異質なものは封じ込めようする議論の力学が作用していた
④欧米人は個人主義で、それ以外は集団主義という世界の常識が裏にあった
⑤通説の根強さがあった
というようなことがあげられよう。
3 コミュニケーションにおける空間的行動の文化的違い
(1)空間とは
「空間行動」とは、「人間が一定の物理的空間内で示す空間利用にかかわる行動の総称」である。
「あてられた空間を効率よく使うことでコミュニケーションを円滑にすることができる」ということが前提となっている。
主な概念は、
①なわばり
②パーソナルスペース
③身体緩衝帯
④対人距離
⑤座席行動
⑥クラウディング
である。
今日の空間行動研究に大きな影響を与えたのは、文化人類学者のホールと、心理学者のソマーである。
ホールの対人距離研究は、相互作用場面においてとられる対人距離研究を以下の4つに分類した。
①親密距離
②個体距離
③社会距離
④公共距離
ホールは、ここで得られた距離帯がすべての例に当てはまるものではないとして普遍的であることは拒否をしているが、対人距離のような空間が、コミュニケーションの手段として機能していることを述べている。また、それは文化によっても規定されているとも考えた。
また、ソマーは、座席行動研究を行って、一定の空間配置をもった座席の選択利用行動を研究した。生態学的なアプローチで、コミュニケーションがどのようにとられるを考究した。
人のなわばり行動については、なわばりを「個人や集団が独占的に所有し、自由にできる地理的空間」とし、なわばり行動を「個人と他者の境界を調整し、その中での主体性を保ち、生理的欲求や社会的欲求を満足させようとする行動」と規定している。
動物のなわばり行動は、出費(コスト)より利益(ベネフィット)であるとし、「コスト・ベネフィット説」と呼ばれる。動物の場合、先住効果というものがあり、時間的に早いか遅いかで、心理的状態や反応が違ってくる。
対して、人のなわばり行動は、動物との違いをあげると以下のとおりである。
①なわばりと攻撃行動の結びつきがはっきりしていない
②生物学的欲求のためだけでなく、二次的目的のために使用される
③状況に応じて複数となる
④共有することもある
⑤自分のなわばりの中で他者をもてなす
人間のなわばり行動に関する研究では、病院に長く入院している患者ほど空間を自由に使用していることを見いだしたエッシャーらの研究がある。
他にパーソナル・スペース(個人空間と訳されることが多い)は、人間の空間行動を説明されたもので、ソマーらの研究で取り上げられた。なわばりと違って、地理的照合点を持たず、個人と共に移動するということが特徴である。
クラウディング(密集状態、過密感)ということも、人間の心理状態に及ぼす影響は大きい。これもまたコミュニケーションにおける空間行動を左右する要素である。
4 最後に
空間行動研究の課題について、パーソナル・スペースに関する研究は1970年代から80年代までは研究されたが、90年代以降は減少した。また、インターネットによるバーチャルな空間概念ができて従来と違った傾向を示すようになった。このことがこれからの課題である
参考文献
(1)ルースベネディクト著 角田安正訳 『菊と刀』 2008 光文社 pp.450-460
(2)杉本良夫/ロス・マオア編著 『日本人論に関する12章』 2000 ちくま学芸文庫 pp.14-37