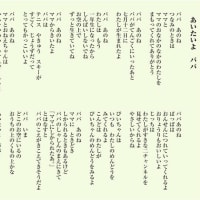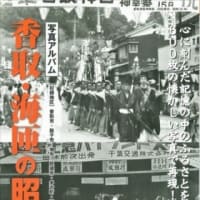またまた長いので、時間のある方のみご覧ください。3500字も書いてありますから。こんなに長く書くと、アクセス数が激減しますが、ま、気にしない、気にしない。(^0^)
地方の疲弊のことを考えることがある。それは、教育問題と密接に結びついていると思う。地方にある大学も、このことの考察なしには存在自体も危ういと思わざるを得ないからである。ましてや、地元地域の賛同なくしては、存亡の危機もありうると思っているからである。大学も高校もである。しかしながら、教育は廃れない。これこそが、わが日本国の大いなる特徴であろう。教育こそが生命線である。廃れさせてはいかんのである。
教育のルーツを考えることがある。現代教育はまだまだ明治維新からのささやかな歴史しかない。それ以前の藩校や寺子屋の教育にはかなり興味関心があるけれども。それでも、わが日本国民は教育に熱心である。教育には無限の投資をしているような気がしないでもない。
過大な教育投資はいつから始まったのか
明治維新からであるのかも知れないというのが、愚生なりの仮説である。
いろいろと調べると、全国の城下町というところで、祭礼というものが少ないことがよくわかる。多くは、士族階級以外の庶民がもっぱら楽しむという形なら、祭礼はある。あるどころか、庶民はそれなりに楽しみ、興奮までしている。しかし、士族階級は違う。
千葉県内のまつりもすべて庶民の世界である。
これまでほとんど中断することなく、庶民は行ってきている。
ところが、士族階級においては、ほとんどそれらしき祭礼はない。仮にあったとしても、明治以降に盛んになったものである。士族階級は庶民を押さえつけることはしたが、庶民のエネルギーを爆発させることはしなかった。
士族は、むしろ、藩校に代表されるような独特の教育を盛んにしていたのである。全国至るところに、このような藩校教育があったからこそ、現代の日本の教育の隆盛があったと思うのである。ちなみに、士族は漢文の素養に長けている。愚生のような庶民は、ひらがな文化の影響を受けている。俳諧がそうである。庶民の文化である。結局、戦争ばかりしていた武家とは違っていたのだった、庶民は。
士族文化は残念ながら、明治以降の城下町の解体に貢献したのであって、決して地域交流に貢献したわけではないのである。
廃藩置県を境にして、城下町在住の士族たちは食禄を離れた。没落をしていった。帰農したり、商業に携わったものもいる。愚生は米沢の出身であるが、上杉の士族で、商業を行っていたものを少なからず知っている。しかも、そうした人は、***様と尊称つきであったのだ。まぎれもない事実である。
明治維新の大業にかかわった士族たちはどうしたのか?
ほとんどが東京に出たのである。軍人になり、巡査になり、下級官吏になり、教師になった。旧城下町に県庁が置かれ、県の役人になったものもあった。
士族階級は文字を理解した。これは維新の後の文字を必要とする新社会体制を構成するのに大いなる影響があったというべきであろう。
文字を解するが故に、士族たちは東京に出ようとしたのである。その子弟たちを東京に出そうとした。
つまり、士族は、それぞれの居住地からもっとも離れやすい性質を持っていたのである。これが問題なのである。
東京だけが学問の府となっていくのである。士族とまでいかなくても、郷士階級もまた東京の学校に憧憬することになる。なぜなら農民になることは許されなかったからである。
士族は全体として、それぞれの子弟を東京にやって、教育を受けさせることを願った。生活は苦しかったと思うが、送金だけはしていたのである。明治中期になると、財産のある商人、地主層たちまで東京に子弟を送ることになる。
ここに地方の経済的蓄積が東京に集中することになる。
東京勉学の問題は、明治三十年代には全国にみられるようになる。どれだけの金子が東京に集中することになるか。
ところが、これらの費用は、地方に還元されないのである。教育を経済で考えたくない愚生ではあるが、このことが地方を逼迫させたのではないかと思う。
ましてや、地方における進学高校というのは、そういう地方を逼迫させる運命にある。
大学だけではなく、地方の高校を出たものも郷里にとどまるものはいない。少ないというべきであろうか。
教育投資は、個人の家にとっては効果的であったといえようが、地方にとっては決して有利ではない。
そうしたことを作ったのは、士族である。よって、それこそが、農村の疲弊を作ってしまったのである。
明治以降においては、軍人になったものはほとんどが士族階級であった。その士族が農民を支配したという構造は、大正時代まで続いていった。
現在、地元の進学校を出て、東京の大学に行ってそれっきり故郷に帰らない若者が多い。むべなるかな。
すべてはシステムである。武家のシステムである。残念ながら。
すべての原因が維新にあるとは、言えない。
しかし、要素の一つではあるのかもしれない。
中央と地方というものは、維新以来そのような関係にあるということを皆知っていたのである。だから東京にすべてが集中していったのである。
このことは、改善されていない。
じわじわと地方は疲弊していったのである。庶民こそがそれを意識すべきであると愚生は思うのだが。