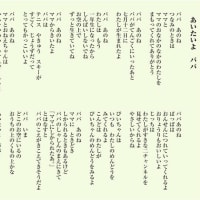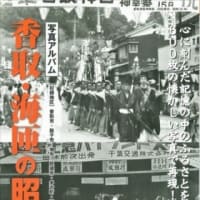嫌ならやめればいいのに、やめられない。タノシミであるから。ブログも自分宛に書いているから、これもまたやめられない。ただし、あまりアクセス数が増える... blog.goo.ne.jp/tym943/e/60854…
学生時代、「オレ朝弱いから9時半からね」と9時からの講義を30分短縮したまま1年間通した教員がいた。当時はラッキーと喜んでいたが今なら問題だよな。ちなみに専任教員。教授。
靖国問題は日本の発信力が問われる。…米国務省副報道官代理は、閣僚の靖国神社参拝を受け、韓国外相の訪日の取りやめに関し「日韓両国が対話を通じ、友好的な方法で立場の違いを乗超えるよう期待している」<時事:日韓は冷静対応を=靖国問題で米国務省jiji.com/jc/zc?k=201304…
私が「神武天皇」に始まる大和朝廷そして「日本書紀」に付いて言及するツイートが多いのは、縄文以来受け継がれて来た神道に繋がる信仰の概念には王朝簒奪し、その氏神の神道祭祀を奪うと言った物が無い事。それ故に神武天皇より今上陛下まで125代の皇統が紡がれて来た事を知って欲しいからです。
私は現在の日本を取り巻く政経事情や支那、南北半島等に付いての保守言論よりも、縄文弥生日本建国に始まる古代史レベルでの自虐的歴史解釈の打破と古代半島国家との日本優勢な日本人のアイデンティティーを説き明かす方が向いている様に思う。
奈良国立博物館「當麻寺」展の図録売場に、田中貴子さんの『日本〈聖女〉論序説』(講談社、2010年) bookclub.kodansha.co.jp/bc2_bc/search_… が置いてありました。今回は買いませんでしたが、表紙が梅若万三郎師の能《三輪》のお写真で、思わず反応…! @takakotanaka
當麻曼荼羅ももちろん素敵でしたが、「當麻寺縁起」絵巻の詞書が、後奈良天皇や三条西実隆の筆によるのを見て、当時の公家たちが当麻寺に寄せた思いなどを感じました。近衛政家の日記『後法興院記』の曼荼羅拝見の記事や、後奈良天皇や後土御門天皇が當麻寺へ下した綸旨も展示されていました。
すべては、祈りから始まります。愛する心を神にお願いすることなしには、私たちは愛する心をもつことはできないし、人を愛することができるとしても、人に与えることのできる愛は、ほんのちょっぴりでしかないでしょう。
【歴史の交差点】明治大特任教授・山内昌之 平成のお雇い外国人教師を - MSN産経ニュース sankei.jp.msn.com/life/news/1304…明治初期の帝大では,教師の大半は外国人であり,授業を受けるのに必要な語学力は旧制高校で訓練していた。
当時大学で古代史を専攻していた身としては、その中将姫伝説の「史実から乖離した感じ」がどうも好きではなかったのです。中世を通した変容が受け入れられなかった。今は「中世特有の捉え方」に興味があるので却って面白く感じるぐらいですが、そこまで至っていなかった。
中将姫関連の能に《雲雀山》《当麻》があります。私は《雲雀山》の演能を拝見する直前に少し調べて、中将姫なる人物が存在することを初めて知ったのですが、一種の継子いじめの話で、あまり好きにはなれなかったんですね。奈良時代の右大臣・藤原豊成の娘とのことですが、いかにも中世っぽい話。
先日、奈良へ行ったついでに奈良国立博物館「當麻寺―極楽浄土へのあこがれ―」展を拝見してきました。 narahaku.go.jp/exhibition/201… 中将姫が作ったという當麻曼荼羅を中心とした展示。當麻寺の草創から、曼荼羅の受容史を見ていると、私ですら何か圧倒されるものが感じました。
マタギの歴史掘り起こす 「白神学」第3巻 : 新おとな総研 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) yomiuri.co.jp/otona/news/201…
ひとりの女性が子どもを抱いてやって来て、こう言いました。「マザー、私は食べ物をもらいにあちこち訪ねました。私たちはこの丸三日間何も食べていないのです。けれど人々は、あなたは若いんだから、自分で働いて、お金を稼ぎなさい、と言って、だれひとりとして何もくれようとしなかったのです」
【東寺と教王護国寺】東寺および教王護国寺という2つの名称があり、百科事典でも東寺を見出し語とするものと教王護国寺を見出し語とするものがある。さらに正式名として金光明四天王教王護国寺秘密伝法院と弥勒八幡山総持普賢院の2つの名称があるが、宗教法人としての登録名は教王護国寺である。
詐欺による少年の年齢別検挙人員数。2000年と2011年の比較。どの年齢でも増加している。振り込め詐欺の「出し子」「受け子」に使われているのだろう。 pic.twitter.com/HQJgeloZiI
東寺帝釈天:力の神・帝釈天は、阿修羅に勝利し仏門に帰依させた英雄とされている。平安時代に完成したが、頭部はすべて後補のため、他の平安期像と比較すると、顔は穏やかで美しいと評されることが多い。twitpic.com/9cgyum










 と~ま君 @tym943
と~ま君 @tym943 これでも大学職員 @koredemo
これでも大学職員 @koredemo 天之釈 @12hirottoN
天之釈 @12hirottoN 仏陀 ブッダ ことば 仏教 @Buddha_Words
仏陀 ブッダ ことば 仏教 @Buddha_Words 猫津彦 長岡休齋 @minamoto33
猫津彦 長岡休齋 @minamoto33 柏木ゆげひ @kashiwagiyugehi
柏木ゆげひ @kashiwagiyugehi 観世流能楽師 宮内美樹 @Miki_MIYAUCHI
観世流能楽師 宮内美樹 @Miki_MIYAUCHI マザー・テレサ @MotherTeresabot
マザー・テレサ @MotherTeresabot 舞田敏彦 @tmaita77
舞田敏彦 @tmaita77 世界遺産BOT @isan_bot
世界遺産BOT @isan_bot
 masa @sarasuzuna
masa @sarasuzuna


 仏像紹介BOT @butsuzobot
仏像紹介BOT @butsuzobot