いつも勝手なことばかり書いていて、少しは申し訳ないとは思っているのだけれども書かないと忘れてしまうからブログに書かせていただいている。そういう側面を愚生はけっこう重視していて、ここからへたくそな論文めいたものにいくつか発展していったから、けっして愚生には疎かにできないのである。
だから許されよ。
日常的なことは、Twitter一本に絞ってしまったから、Twitterでつぶやいたことは、ダイレクトにブログに反映されるように仕組んである。最近は、このTwitterで意見を交換させていただく方も増えて、なかなか楽しい。それぞれのツールに役割分担を願っているから、こちらはこちらでいいものである。
それで、けふは、「地域学」ってなことである。「地方史」というと、なんとなく中央と対峙している地方という感じがして、愚生はあまりおもしろくない。その中央だって、京都を中心とした関西勢力と、江戸の勢力と対峙している。江戸から後はどっちが中央なんだかわからんくらいに変遷してきている。地方の対象が変わってきている、と屁のつっぱりみたいに考えているからである。
だから、「地域学」とでもしたほうがよろしいのではないかと思うのである。愚生が今住んでいるのは、関東である。だから「関東学」とでもいったほうが感覚的にはすっとくる。まさにすっとくるのであって、そこには根拠もなにもないのであるが。
特に、中世のことを調べていると、錯覚に陥りやすい。厳に戒めているのだが、どうしても中世文化は西国中心というか、京都・奈良以外は視野に入ってこないということになりやすい。これはとても危険なことである。中世のときも、関東は存在していたのであり、文化のレベルも高かった。安房地区からも、竹に書かれた文字が、京都まで運ばれていったし、考えもつかないような交流が、関西文化圏と関東にはあったのである。
八丈島も、時代劇などを見ると島流しのイメージが強く、流された以上、もう帰ってこられない島が八丈島というのが我々には染み着いている。しかし、ここには装飾品をまとった縄文時代人の墳墓が発見されている。死んだ後に、自分で墳墓を作る死人はいないから、常態的に生活していた縄文人がいたということになる。そのことがなにを意味するのか。縄文時代の人々は、今よりも考えられないような海上の道を持っていたのである。
現在の我々は、臆病である。だから、太平洋を小さな舟で行き来することなんてできないと断定してしまうのである。我々のご先祖様たちは、今よりも勇敢であったと考えるべきであろう。
グローバルなんとかという言葉がはやっているけれども、我がご先祖様たちは、東洋の世界だけではあったけれども、なかなかしたたかに生きていたのだ。
そこには、日本古来の民族が持っている大いなる大地信仰というものがあって、アニミズムとドッキングしたところの土着信仰と、神道が合体している。後から仏教が入ってきて、それこそ神仏習合的な形態になっていったのだけれども、まだまだその影響は現代の日本人にも影響している。無宗教であることを誇りに思うような、世界の中では特異な民族になってしまったけれども、まだまだいろいろな意味で習俗を気にしたりする人は多い。仏滅とか、大安とか、大吉とか、大凶とか。さらには、日本国民ほとんど全員がキリストの誕生日を祝っているという実におもしろい国でもある。つまり、古代からふわ~っとした信仰みたいなものを持っていたんだろうと愚生は思うことにしている。大地や海、大自然への限りない畏れと信頼が同居していたのであると思っている。それが如実に信仰に現れていると。ま、今はそのことには触れない。これからの愚生の追求課題であるから。
大地への、海への畏れと信頼があるから、逆にどこへでも出かけていたのだ。天竺というのは大げさとしても、中国南方とか、インドシナ半島あたりまで。しかし、今日は北方にもいろいろと出かけていたらしいということを、知った。さすがである。つまり津軽海峡をどうどうと小舟で行き来していたらしいのだ。確かに、去年大間の港から見えた函館は、渡るのに不可能な距離ではないようにも思えた。
コンパスの針をどこに置くかである。関西に置けば、関東は遠くの地。関東に置けば、その逆である。八丈島に置けば、関東も近在地になる。八重山諸島にコンパスの針を置けば、また違って見えるのが本州であろう。
地域学というのは、このコンパスの針の置き方である。どこに置くかはその人の自由である。視点といってもいいけれども。それによって、人生が変わってしまう人もいるかもしれない。
愚生のように。
ハハハ。
最新の画像[もっと見る]
-
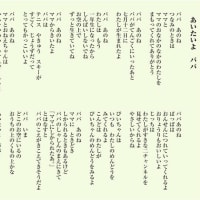 東日本大震災の時・・・・・こんな詩が新聞にでていたっけ
12ヶ月前
東日本大震災の時・・・・・こんな詩が新聞にでていたっけ
12ヶ月前
-
 秋保温泉で 二泊三日 温泉入り放題だった( ̄∇ ̄)
2年前
秋保温泉で 二泊三日 温泉入り放題だった( ̄∇ ̄)
2年前
-
 秋保温泉で 二泊三日 温泉入り放題だった( ̄∇ ̄)
2年前
秋保温泉で 二泊三日 温泉入り放題だった( ̄∇ ̄)
2年前
-
 秋保温泉で 二泊三日 温泉入り放題だった( ̄∇ ̄)
2年前
秋保温泉で 二泊三日 温泉入り放題だった( ̄∇ ̄)
2年前
-
 ありがたい 実にありがたい
2年前
ありがたい 実にありがたい
2年前
-
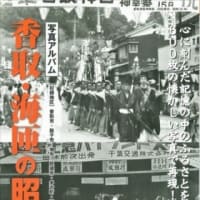 校正が大変だった。でもタノシミにしているけど。出るのが、来月になる。
4年前
校正が大変だった。でもタノシミにしているけど。出るのが、来月になる。
4年前
-
 昨日いただいたすき家の牛丼 うまかったな たっちゃんねるで知ったのだけど
5年前
昨日いただいたすき家の牛丼 うまかったな たっちゃんねるで知ったのだけど
5年前
-
 死んだらどうする? こんなにガラクタ集めて けふは書庫の大掃除でした(笑)
5年前
死んだらどうする? こんなにガラクタ集めて けふは書庫の大掃除でした(笑)
5年前
-
 孫と一緒に中根東里センセに会いに行っていた そしたら孫が地元テレビのインタビューを受けてしまった(笑)
5年前
孫と一緒に中根東里センセに会いに行っていた そしたら孫が地元テレビのインタビューを受けてしまった(笑)
5年前
-
 生涯学習ごっこというのは、残糞感みたいなもんである。まだ、うんこがケツの中に残っているという感覚。これがあるから、やる気になっちまうのですなぁ(^_^)
5年前
生涯学習ごっこというのは、残糞感みたいなもんである。まだ、うんこがケツの中に残っているという感覚。これがあるから、やる気になっちまうのですなぁ(^_^)
5年前
















