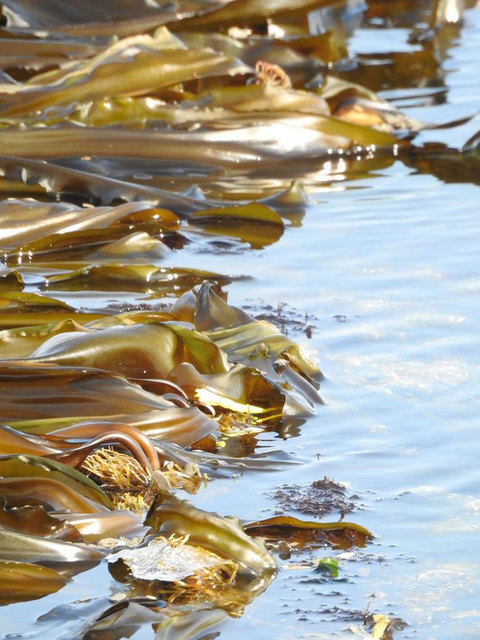ただ、初詣にも作法があってそれを守ればご利益も大きくなるそうです。
例えば、お正月にできたら伊勢神宮に行く。
1月、5月、9月のこの3か月がお勧めの月です。
普段は、住んでいる神社や大きな神社でも良いのですが、
年の初めで大きな願い事をする場合は総本山の伊勢神宮に行った方が良いんですね。
伊勢神宮参拝の方法もあります。
基本的に、下宮~内宮と両方とも参拝するのが基本です。
通常、「お伊勢詣り」というと、この内宮と外宮の二つを回ることとされています。
内宮のご祭神は天照大御神(あまてらすおおみかみ)。日本人の総氏神といわれる存在です。
外宮のご祭神は豊受大御神(とようけのおおみかみ)。
天照大御神の食事をつかさどり、産業や食事に関する神様です。
この内宮・外宮を中心に、それぞれの別宮、摂社、末社、所管社と呼ばれる宮社があり、
すべて合わせて125社の総称が、伊勢神宮と呼ばれています。
内宮・外宮に属する宮社のなかでも、「別宮」はそれぞれの分家のようなもので、
内宮・外宮のご正宮に次いで、格が高い存在。
参拝の順序は、外宮から内宮へ回るのが、古来からの習わしとされています。
参拝だけではなく、伊勢神宮で行われるさまざまな行事に関しても、「外宮先祭」と言われ、
外宮→内宮の順序で行われています。
外宮か内宮、片方だけをお詣りするのは、「片まいり」と呼ばれ、避けるべきことと言われています。
それぞれの場所に着いたら、まずはご祭神の祀られているご正宮にお詣りするのが手順。
その後、別宮を回るのが正式な順序です
具体的な参拝方法。
入口に着いたら、外宮の場合は火除橋、内宮の場合は宇治橋を渡って、神域に入っていきます。
外宮と内宮、参拝方法は基本的に同じですが、少し異なるのが、外宮の参道は左側通行、
内宮の参道は右側通行であること。
これは、橋を渡った先の手水舎の位置に合わせて決められています。
それぞれの橋には表示がありますので、それにしたがって歩けばOKです。
参道では、基本的に中央を歩くのはタブー。中央は神様の通る道とされているからです。
鳥居をひとつ越えるごとに、神様の領域に近づいていきます。
鳥居の前では立ち止まり、軽く一礼してから進みましょう。
正宮にお詣りする前に、手水舎で手と口を清めます。
この手水舎の作法は下記の通りです。
・右手でひしゃくを持って水をすくう
・左手を清める
・左手にひしゃくを持ちかえ、右手を清める
・右手にひしゃくを持ちかえ、左手に水をすくって口をすすぐ
・左手を清める
・ひしゃくを垂直に持ち、余った水をひしゃくの柄に伝わせ、清める
水は最初に一度すくうのみで、その水を少しずつ使います。
手水は、お詣りの前の「禊」を簡略化したものだといわれています。
さて、内宮の正宮前の階段を上がったところにご正宮があります。
ご正宮に祀られているのは、内宮のご祭神である天照大御神の和魂(にぎみたま)、
つまり、神様の穏やかな面の魂です。
外宮の場合は同様に、豊受大御神の和魂が祀られています。
拝礼は、「二拝二拍手一拝」にて行います。
内宮でも外宮でも、ご正宮は日頃のご加護に対する感謝を神様に伝える場所と言われています。
個人的なお願いごとをする場所は、外宮・内宮とも、それぞれの「第一の別宮」と言われています。
内宮の第一の別宮は「荒祭宮」、外宮の第一の別宮は「多賀宮」。
どちらも、第一の別宮には、ご祭神の荒魂(あらみたま)、
つまり、神様の荒々しい活動的な面の魂が祀られています。内宮の場合は天照大御神の荒魂、
外宮は豊受大御神の荒魂ということですね。
参拝の方法を知ってお参りすれば1年のご利益も大きいかもしれません。
まさに、1年の計は元旦にありです。
「空海」の言葉
あなたの心が暗闇であれば 出会うものは
ことごとく 「禍い 」になる
あなたの眼明るければ 出会うものは すべて宝となります。
なんて素晴らしいんでしょう。
更に比叡山延暦寺には 発祥があちらこちらに。
根本中堂に1200年もの間、一度も消えたことがない「不滅の法灯」と言うお灯明。
毎朝夕に燃料の菜種油を絶やさないように僧侶が注ぎ足し続けているそうですが、気を抜くと燃料が断たれて火が消えてしまう。
世界平和を願って、京都の鬼門に造られた延暦寺。その灯には 願いと共にこんなことも。
「油を断やさないように」それが
「油断大敵」の言葉の由来 だそう です。
油を注ぐのは単純で簡単なことだが、それを1200年もの間ずっと欠かさずに継続することは、とても大変なこと。気の緩みがあってはとても続くものではないですね。
人間関係の一番の敵は、「無理する」ことだと思います。
無理して他人に合わせると絶対に良くないと思います。
他人なんて他人だし、あなたのことをそんなに真剣に考えてないですから。
宮藤官九郎