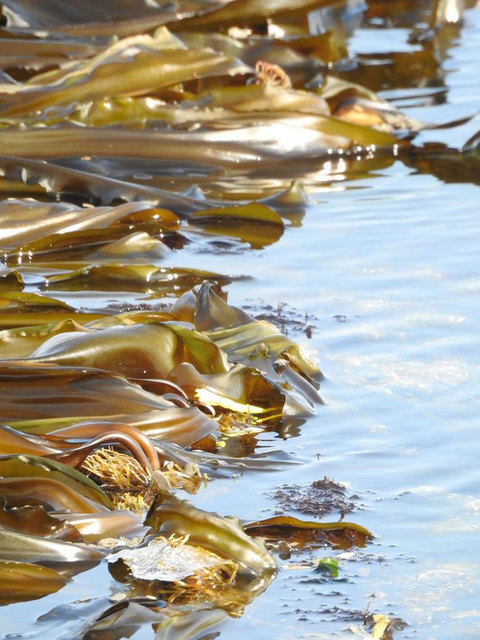4月1日、東池袋大勝軒の創業者であり、つけ麺の創始者である山岸一雄さんが80歳で亡くなった。今回は、山岸さんを偲んで過去に書いた文章を引用しながら想い出を語らせていただく。(長文ご容赦。写真は旧店舗閉店日のものと東京ラーメンショーのステージでハーモニカを吹いていただいたときのもの。2ショットは恐縮過ぎて残念ながら撮ってない。)
山岸さんは1934年4月に長野県で生まれた。16歳で上京し、17歳からラーメン職人としての人生を歩み始める。親戚の「兄貴」と慕う人の手伝いである。中野にある「大勝軒」(今も中野にあるが当時は違う場所だった)を任されていたときに賄いで食べていた「もりそば」(つけ麺のことを大勝軒ではこう呼ぶ)をお客さんにも出すようになった。これがつけ麺誕生の瞬間であり、1955年のことである。その後、1961年にようやく自分の店を持つことになった。それが東池袋の「大勝軒」だ。まだサンシャイン60も無く、寂しい場所だったがすぐに行列ができる繁盛店になった。
しかし、順風満帆に半世紀が過ぎてきたわけではない。実は大勝軒には2度の閉店危機があった。最初は1974年、山岸さんの足の手術により、3ヶ月間の休業。この時は奥さんの献身的なサポートで店を続けることができた。2度目は1986年、奥さんが52歳の若さでこの世を去ったのだ。幼なじみだった奥さんの死は、山岸さんの生きる気力すら失わせた。もちろん店はずっと休業。そんな山岸さんにやる気を起こさせたのは、大勝軒を愛するお客さんであった。「しばらく休業します」という貼り紙にびっしりと書かれたたくさんのお客さんからのメッセージ。それを見て山岸さんはもう一度やってみようと思ったのだ。
これまで「大勝軒」では店員を雇わずにやってきたが、奥さんを亡くしてしまったのでそうもいかない。この時から弟子を取るようになったのである。山岸さんには子供がいない。だから味の継承ができない。そこで、弟子を取り、自分の味を教えて受け継いで欲しかったという。最低3ヶ月で暖簾分けを認めたこともすごい。しかも、暖簾代やロイヤリティは一切要らないというのだ。そんなこともあってか、今では100人以上のお弟子さんが全国各地で活躍している。山岸さんは、そのお弟子さん達を自分の子供のように可愛がっていた。山岸さんの味は、まったく同じとは言えないまでも間違いなく受け継がれているのである。
私が初めて大勝軒で食べたのは30年以上前。都内の会社に就職し、営業の仕事でサンシャイン60に来たときだ。当時、もりそばの知識はなかったので、注文したものは中華そば。会津に生まれた私はいわゆる喜多方ラーメンで育っている。なので、「違ったタイプのうまいラーメンもあるんだなぁ?」と感動したことを覚えている。そして2回目に行ったときにはおいしかった中華そばを大盛りで頼んだ。すると山岸さんは「おにいちゃん、うちのは多いけど大丈夫かい?」と聞いてきた。人より大食いの自信があった私は「大食いなので大丈夫です」と言って大盛りにしてもらった。しかし、自称大食いの私でも食べられなかったのである。それほど大盛りのボリュームは凄かった。こんなにおいしいのを残すなんて、お店の人に大変申し訳ない。でも、食べきれなかった。私は何度も頭を下げて、お店を後にした。しばらく恥ずかしさでお店には行けなかったのだが、おいしさの魅力に負けてまた通うようになっていた。通うと言っても年に数回程度である。もちろんその後、つけ麺の魅力にはまって、3回に2回はつけ麺を食べたものである。
大勝軒の土日は、朝7時くらいから人が集まりだす。大勝軒好きの常連さん達がやってきて酒盛りが始まるのだ。開店までの3-4時間をこうして過ごす。常連さんが朝早くから来るのにはもう一つ理由があった。山岸さんの体力的な問題で仕込みはお弟子さんに任せるようになった。しかし、最初に着席できる16人分(店内は16席)の麺は山岸さんが打つ、という話があった。そうしたことも目的の一つであったのだろう。最初の16人に入るとメニューにはない餃子がスープの中に入っていることもあった。あるいは、チャーシューが一枚多かったりしたことも。「長い間待っていてくれてありがとう」という山岸さんの気持ちなんだと思う。
ある日、私もその16番以内を目指して早めに並び、常連さん達と一緒に酒盛りをしていたときに、こんなことを言われたことがある。「大崎君ねぇ、あなたも大勝軒が好きなんだろうけど、我々は年に50回とか100回食べに来てるのよ。調子の良いときもあれば、いつもと違うときもある。それら、全部を含めて「大勝軒の味」なんだよね。年に数回じゃ大勝軒の本当の味はわからないよ。」確かにその通りだと思った。私の「好き」は、この常連さん達の「好き」には到底及ばないと思った。しかし、それでも言いたい。私も大勝軒がそして山岸さんが好きなんだと。
山岸さんの功績はつけ麺を考案したことだけではない。動物系と魚介系を濃厚に合わせる大勝軒の手法は今でも東京の多くの店が参考にしている。それと自家製麺だ。今でこそ、つけ麺ブームで自家製麺が増えたが50年以上も前から自分で麺を作っていたのだからすごい。そして山岸さんは「ラーメンの神様」などと呼ばれることがある。それはつけ麺の考案者であることやラーメン一筋50年以上の人生に対して言ってる場合が多い。しかし、実は物の考え方が非常に達観的であり、悟りの境地に至ってる話がいくつもある。そういう意味でも「神様」なのだと思う。その事例をいくつか紹介したい。
まず有名な話として、お弟子さんにはすべて包み隠さず何もかも教えるということ。店の宝である「味」と「ノウハウ」をすべて伝授してしまうのだ。しかも暖簾代やロイヤリティも一切取らないのだから驚く。ある時、店の売り上げが合わなかったことがあった。普通なら店員を疑い問い詰めるであろう。しかし、そんなことをしないだけでなく、そんな環境を作ってしまった自分を責めたという。そんな時に周りが券売機の設置を提案したら「それではお客さんや店員を信用してないことになるから要らない」と断ったという。
こんなに長い間、行列を作る人気店になっているのに山岸さんはいつも「感謝の気持ち」を口にしている。食べに行って「ごちそうさまでした」と言うと「いつもありがとうね。遠くからどうもね?」と返してくれる。「おいしかったです」と言うとにっこり笑ってくれる。その笑顔を見たいがために通った、と言っても過言ではない。そして新店舗になって山岸さんは厨房に立てなくなった。それでも可能な限り店には出た。冬でも店内ではなく、店頭の椅子に座ってお客さんを歓迎した。行くといつも握手をしてくれた。ゴツゴツした大きな手だが、まさにゴッドハンドである。それでいつも元気と勇気を貰った。
ラーメンは味だけではない。豚ガラ、鶏ガラで作られるラーメンには「人柄」も重要なファクターなのである。そして、山岸さんの人柄こそが半世紀の行列を作り出したのだと思う。
どうして大勝軒はこんなにも愛されたのか?片思いでは、半世紀もの行列が続かない。山岸さんとお客さんは両思い、つまり相思相愛だったのだと思う。山岸さんを愛し、大勝軒を愛するお客さん。そして自分の店に足を運んでくれるお客さんへの愛情とお客さんに出すラーメンへの愛情。一方通行ではなく、双方向だったのだと思う。だからこそ半世紀もの長い間に渡って行列ができたのだろう。
長い間、本当にお疲れ様でした。そしておいしいラーメンをありがとうございました。私は味やノウハウを受け継げないが山岸さんが抱いていた「ラーメン愛」はしっかりと受け継ぎたいと思う。