1958年10月。
中学生になって半年、学校には一日も休まずに行っていたがあんまりおもしろくない。勉強にもそれほど興味もなく、だからといってスポーツなどのクラブ活動をやろうとも思わなかった。
稲刈りが始まった。これからは学校から帰ったら田んぼ、日曜日も田んぼの毎日が一月半くらいつづく。
「今年は上出来や!」と稲穂を持ったおっ母ァはうれしそうだ。刈り取った稲は束ねて稲木に架けて2~3週間ほど天干しにする。よく乾かしてから脱穀し、籾を家に持ち帰るのだ。
籾は毎朝陽が昇るころにムシロに広げて3時ころに終うという乾燥を1週間ほど繰り返す。これでやっと籾摺りができる状態になるのだ。籾摺り機は村の共同使用だったので、一軒づつ順番が決まっている。籾摺りには一家総出だった。
籾摺りでのオレの仕事は、もっぱら出てきた玄米を一斗升でこぼさんように運んで俵に入れることだ。1斗(15㎏)を持った時のずっしりした重み、4斗入った俵の中に手をつっこんだ時の感触はなんともいえない。親父も俵の中のコメを掌に広げて見ては、「今年は艶があってよう肥えとる。これやったら1等や」といっている。
摺りたてのコメは温いのでその日は俵の口は広げておく。次の日、兄貴はその俵に蓋をかぶせて縄で編んでいくのだ。この仕事はオレにはまだまだ無理。
兄貴が見ているオレに、「いっぺん担いでみるか。担げたら一人前や」といった。1俵(60㎏)を下から両手で持上げ肩に担いで歩けたら男として一人前だというのだ。
兄貴が一度やって見せてくれた。「腰を入れて、体全体を使って、力まかせはアカン」と。やってみたがなかなか上がらない。「腰を使こうて、一気に!」と兄貴。空気を吸ってほっぺを膨らませて、腰を落としてウッと唸った。上がった。重たい、腰がふらつき地面にめり込むようだ。「ヨシッ」の兄貴の声でなんとか下した。
晩飯の時に兄貴が、「タカシも1俵担げるようになったで」とみんなの前でいった。親父はニヤニヤしていた。
オレも一人前の男になれたのだ。
昼の仕事で疲れているはずなのに、その夜は少し興奮していたのか布団に入ってもなかなか寝つけなかった。
中学生になって半年、学校には一日も休まずに行っていたがあんまりおもしろくない。勉強にもそれほど興味もなく、だからといってスポーツなどのクラブ活動をやろうとも思わなかった。
稲刈りが始まった。これからは学校から帰ったら田んぼ、日曜日も田んぼの毎日が一月半くらいつづく。
「今年は上出来や!」と稲穂を持ったおっ母ァはうれしそうだ。刈り取った稲は束ねて稲木に架けて2~3週間ほど天干しにする。よく乾かしてから脱穀し、籾を家に持ち帰るのだ。
籾は毎朝陽が昇るころにムシロに広げて3時ころに終うという乾燥を1週間ほど繰り返す。これでやっと籾摺りができる状態になるのだ。籾摺り機は村の共同使用だったので、一軒づつ順番が決まっている。籾摺りには一家総出だった。
籾摺りでのオレの仕事は、もっぱら出てきた玄米を一斗升でこぼさんように運んで俵に入れることだ。1斗(15㎏)を持った時のずっしりした重み、4斗入った俵の中に手をつっこんだ時の感触はなんともいえない。親父も俵の中のコメを掌に広げて見ては、「今年は艶があってよう肥えとる。これやったら1等や」といっている。
摺りたてのコメは温いのでその日は俵の口は広げておく。次の日、兄貴はその俵に蓋をかぶせて縄で編んでいくのだ。この仕事はオレにはまだまだ無理。
兄貴が見ているオレに、「いっぺん担いでみるか。担げたら一人前や」といった。1俵(60㎏)を下から両手で持上げ肩に担いで歩けたら男として一人前だというのだ。
兄貴が一度やって見せてくれた。「腰を入れて、体全体を使って、力まかせはアカン」と。やってみたがなかなか上がらない。「腰を使こうて、一気に!」と兄貴。空気を吸ってほっぺを膨らませて、腰を落としてウッと唸った。上がった。重たい、腰がふらつき地面にめり込むようだ。「ヨシッ」の兄貴の声でなんとか下した。
晩飯の時に兄貴が、「タカシも1俵担げるようになったで」とみんなの前でいった。親父はニヤニヤしていた。
オレも一人前の男になれたのだ。
昼の仕事で疲れているはずなのに、その夜は少し興奮していたのか布団に入ってもなかなか寝つけなかった。


















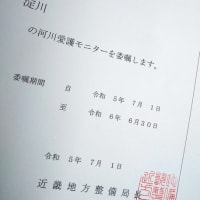

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます