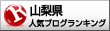ガソリンや灯油、カップラーメンやトイレットペーパー(ロールペーパー)など。
我々の住むところで生活必需品の買占めが横行(といっていいのか)しており、そのせいで被災地に物資が送られない、という報道を目にします。
被災地の人たちのために買占めはやめよう、とテレビで呼びかける声も聞きます。
少し違ううんじゃないかなと思います。
我々は生産している工場から無理やり持ってきているわけではないのです。
東北地方向けになっている物資を横取りしたわけでもありません。
普通の流通ルートに乗って店頭に並んでいるものを購入しているだけなのです。
物資の送り先について、政府としての命令や指導はまだないと思いますが、流通業者や小売業者のそれぞれの判断があって、被災した地域に優先して生活必需品が送られていることは確かだと思います。
自由経済でいうところの「需要のあるところに供給される」わけです。
したがって我々のところに回ってくるのはその“残り物”になります。
“残り物”の量が我々の需要を満たさないので、モノ不足になり、争って買い占めようとすることになります。
買占めをされて困るのは、我々の地域の「買えなかった人たち」です。
我々は、貴重な“残り物”をみんなで分け合うために、不要な買占めをやめなければなりません。
そうして分け合ったもので我慢して生活をしましょう。
飽食の時代といわれて、大量消費が当たり前のこれまでの生活を見直すのには確かに良い機会になりました。
我々の住むところで生活必需品の買占めが横行(といっていいのか)しており、そのせいで被災地に物資が送られない、という報道を目にします。
被災地の人たちのために買占めはやめよう、とテレビで呼びかける声も聞きます。
少し違ううんじゃないかなと思います。
我々は生産している工場から無理やり持ってきているわけではないのです。
東北地方向けになっている物資を横取りしたわけでもありません。
普通の流通ルートに乗って店頭に並んでいるものを購入しているだけなのです。
物資の送り先について、政府としての命令や指導はまだないと思いますが、流通業者や小売業者のそれぞれの判断があって、被災した地域に優先して生活必需品が送られていることは確かだと思います。
自由経済でいうところの「需要のあるところに供給される」わけです。
したがって我々のところに回ってくるのはその“残り物”になります。
“残り物”の量が我々の需要を満たさないので、モノ不足になり、争って買い占めようとすることになります。
買占めをされて困るのは、我々の地域の「買えなかった人たち」です。
我々は、貴重な“残り物”をみんなで分け合うために、不要な買占めをやめなければなりません。
そうして分け合ったもので我慢して生活をしましょう。
飽食の時代といわれて、大量消費が当たり前のこれまでの生活を見直すのには確かに良い機会になりました。