『COVID-19との長期戦に備えて 1(参考にすべき国々と比較 37)』
―PCR検査で陽性者の把握と、『率先自主隔離とお願い隔離』の継続徹底を―
今、一番重要なことは、最近数カ月の日本の数値、PPM値(100万人あたり)で、『感染者数推移』、『死者数推移』、『PCR検査数推移』、『ワクチン接種人数推移』を、西欧と東アジアの主要国との比較を、公開して、国民の皆様に、日本の現状を理解いただき、対策徹底をしてもらうことです。 特に、今後の『ワクチン接種人数推移』と『感染者数推移』の推移が心配です。
COVID-19のSARS-Cov-2変異株の影響が、出始めました。 データ不足ですが、ドイツ、インド、韓国、日本が 心配です。 SARS・MERSの経験がある東アジアの台湾・韓国と比較してみると日本の実態は、かなり厳しい状態にあると思います。
|
COVID-19をSARS・MERSに比較
|
|
|
|
|
SARS
|
MERS
|
COVID-19
|
|
感染者数/死者数
|
8,096 / 774
|
2,494 / 858
|
13.586.9万人/
293.5万人
(20210411現在)
|
|
潜伏期間
|
2-10日(平均5日)
|
2-15日
|
1-14日
(20210116現在)
|
|
感染経路
|
飛沫感染
接触感染
(糞口感染)
(空気感染)
|
不明
(現在調査中)
|
飛沫感染
接触感染
|
|
致死率(全体)
|
約9.6%
(20030930現在)
|
症例致死率
34.4%
(20191130現在)
|
約2.16%(微減)
(20210411現在)
|
|
致死率(年齢別)
|
34歳未満: 1%
25-44歳: 6%
45-64歳: 15%
65歳以上:50%以上
|
不明
|
不明
|
|
終息時期
|
最初の患者から
8カ月後
|
現在も終息に
至っていない
|
不明
|
- 人口100万人あたりのCOVID-19の感染者数推移(東アジアの4カ国)
『人口100万人あたり感染者数、いわゆるPPMベースで韓国の2.16倍(前月2.14倍から微増)、台湾の145.3倍(172.3倍から減少)』
- 人口100万人あたりのCOVID-19の死者数推移(東アジアの4カ国)
第四波に備えて、『PCR検査で陽性者の把握と、「率先自主隔離とお願い隔離」の継続徹底を』、
人口100万人あたりのCOVID-19の感染者増加率・死者数推移(11ヶ国と世界)『頭打ち直前です。』 ここで定量的把握を強化して、日本もアジアで抑え込んだ国になって貰いたいです!
4月11日のデータで更新しました。
人口100万人あたりのCOVID-19の感染者増加率(11ヶ国と世界)
| |
中国 |
台湾 |
日本 |
韓国 |
インド |
スウェーデン |
ドイツ |
英国 |
米国 |
ブラジル |
南ア |
世界 |
| 2002 |
55 |
1 |
2 |
57 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
11 |
| 2003 |
57 |
13 |
15 |
191 |
0 |
399 |
739 |
571 |
497 |
22 |
23 |
104 |
| 2004 |
58 |
18 |
111 |
210 |
24 |
2,010 |
1,899 |
2,633 |
3,142 |
368 |
95 |
403 |
| 2005 |
58 |
19 |
133 |
224 |
132 |
3,675 |
2,166 |
3,794 |
5,349 |
2,188 |
551 |
771 |
| 2006 |
59 |
19 |
147 |
250 |
411 |
6,700 |
2,319 |
4,201 |
7,826 |
6,437 |
2,550 |
1,314 |
| 2007 |
61 |
20 |
267 |
279 |
1,188 |
8,931 |
2,491 |
4,490 |
13,579 |
12,279 |
8,316 |
2,219 |
| 2008 |
62 |
20 |
537 |
389 |
2,624 |
8,341 |
3,184 |
4,980 |
18,171 |
18,171 |
10,573 |
3,243 |
| 2009 |
62.91 |
21.58 |
656 |
464 |
4,511 |
9,223 |
3,452 |
6,715 |
21,725 |
22,476 |
11,370 |
4,333 |
| 2010 |
63.48 |
23.26 |
794 |
517 |
5,896 |
12,779 |
6,192 |
14,948 |
27,333 |
25,953 |
12,232 |
5,866 |
| 2011 |
64.55 |
28.34 |
1,178 |
676 |
6,857 |
24,074 |
12,770 |
24,066 |
40,910 |
29,808 |
13,320 |
8,118 |
| 2012 |
66.67 |
33.55 |
1,864 |
1,205 |
7,440 |
43,308 |
21,013 |
36,771 |
60,326 |
36,112 |
17,825 |
10,703 |
| 2101 |
69.52 |
38.25 |
3,085 |
1,531 |
7,795 |
56,138 |
26,564 |
56,391 |
79,109 |
43,304 |
24,512 |
13,137 |
| 2102 |
70.15 |
40.10 |
3,416 |
1,756 |
8,052 |
65,085 |
29,245 |
61,704 |
86,339 |
49,639 |
25,517 |
14,639 |
| 2103 |
70.68 |
43.25 |
3,753 |
2,021 |
8,856 |
79,697 |
33,940 |
64,225 |
92,026 |
59,977 |
26,103 |
16,536 |
| 2104 |
71.31 |
46.33 |
4435 |
2367 |
11103 |
93879 |
39425 |
65144 |
98097 |
69386 |
26578 |
18980 |
10月度 11月度 12月度 1月度 2月度 3月度 4月末予想
前月末比 前月末比 前月末比 前月末比 前月末比 前月末比 前月末比
ドイツ 179% 206% 165% 126% 110% 116% 116%
スウェーデン 139% 188% 180% 130% 116% 123% 118%
英国 223% 161% 153% 153% 109% 104% 101%
米国 126% 150% 147% 131% 109% 107% 107%
ブラジル 115% 115% 121% 120% 115% 121% 116%
台湾 105% 122% 121% 114% 105% 108% 107%
中国 100% 103% 103% 104% 101% 101% 101%
韓国 111% 131% 178% 127% 115% 115% 117%
日本 121% 148% 158% 166% 111% 110% 118%
インド 131% 116% 109% 105% 103% 110% 125%
南ア 108% 109% 134% 138% 104% 102% 102%
世界 135% 138% 132% 123% 111% 113% 115%
人口100万人あたりのCOVID-19の感染者数推移(東アジアの4カ国)
| |
中国 |
台湾 |
日本 |
韓国 |
| 2002 |
55 |
1 |
2 |
57 |
| 2003 |
57 |
13 |
15 |
191 |
| 2004 |
58 |
18 |
111 |
210 |
| 2005 |
58 |
19 |
133 |
224 |
| 2006 |
59 |
19 |
147 |
250 |
| 2007 |
61 |
20 |
267 |
279 |
| 2008 |
62 |
20 |
537 |
389 |
| 2009 |
62.91 |
21.58 |
656 |
464 |
| 2010 |
63.48 |
23.26 |
794 |
517 |
| 2011 |
64.55 |
28.34 |
1,178 |
676 |
| 2012 |
66.67 |
33.55 |
1,864 |
1,205 |
| 2101 |
69.52 |
38.25 |
3,085 |
1,531 |
| 2102 |
70.15 |
40.10 |
3,416 |
1,756 |
| 2103 |
70.68 |
43.25 |
3,753 |
2,021 |
| 2104 |
71.31 |
46.33 |
4435 |
2367 |
人口100万人あたりのCOVID-19の死者数推移(11ヶ国と世界)
| |
中国 |
台湾 |
日本 |
韓国 |
インド |
スウェーデン |
ドイツ |
英国 |
米国 |
ブラジル |
南ア |
世界 |
| 2002 |
1.97 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.37 |
| 2003 |
2.31 |
0.04 |
0.44 |
3.18 |
|
14.46 |
|
36.19 |
9.58 |
0.75 |
|
4.96 |
| 2004 |
3.22 |
0.25 |
3.28 |
4.84 |
0.78 |
243.78 |
75.05 |
394.1 |
184.19 |
25.72 |
1.74 |
29.23 |
| 2005 |
3.22 |
0.29 |
7.04 |
5.29 |
3.74 |
435.18 |
101.45 |
552.79 |
313.54 |
135.65 |
11.52 |
47.41 |
| 2006 |
3.22 |
0.29 |
7.69 |
5.51 |
12.61 |
525.78 |
107.11 |
596.28 |
381.08 |
274.34 |
44.81 |
64.42 |
| 2007 |
3.24 |
0.29 |
7.93 |
5.87 |
25.91 |
568.26 |
109.11 |
607.99 |
459.42 |
429.35 |
134.97 |
85.74 |
| 2008 |
3.28 |
0.29 |
10.11 |
6.32 |
46.72 |
577.86 |
110.98 |
612.63 |
553.07 |
568.44 |
238.57 |
108.66 |
| 2009 |
3.29 |
0.29 |
12.37 |
8.06 |
70.65 |
580.14 |
113.24 |
622.12 |
580.14 |
672.38 |
282.15 |
129.46 |
| 2010 |
3.29 |
0.29 |
13.88 |
9.05 |
88.15 |
590.34 |
127.45 |
687.11 |
693.98 |
750.27 |
325.01 |
151.74 |
| 2011 |
3.30 |
0.29 |
16.41 |
10.26 |
99.72 |
661.53 |
199.25 |
862.40 |
809.80 |
814.45 |
363.11 |
188.39 |
| 2012 |
3.32 |
0.29 |
26.03 |
17.89 |
107.78 |
864.12 |
403.31 |
1,084.49 |
1,044.51 |
917.15 |
480.01 |
233.25 |
| 2101 |
3.35 |
0.34 |
45.49 |
27.79 |
111.88 |
1,147.71 |
682.27 |
1,566.85 |
1,333.28 |
1,056.19 |
744.65 |
284.33 |
| 2102 |
3.36 |
0.38 |
62.38 |
31.31 |
113.88 |
1,269.99 |
837.30 |
1,813.08 |
1,550.72 |
1,199.39 |
842.93 |
324.80 |
| 2103 |
3.36 |
0.42 |
72.39 |
33.84 |
118.06 |
1,333.26 |
914.13 |
1,870.12 |
1,667.88 |
1,512.59 |
891.03 |
361.22 |
| 2104 |
3.36 |
0.53 |
77.00 |
35.69 |
130.61 |
1,375.40 |
976.31 |
1,884.93 |
1,750.22 |
1,918.33 |
912.93 |
403.14 |
ブラジルとインドの増加が心配です。
10月度 11月度 12月度 1月度 2月度 3月度 4月末予想
前月末比 前月末比 前月末比 前月末比 前月末比 前月末比 前月末比
ドイツ 110% 156% 202% 169% 123% 109% 107%
スウェーデン 102% 112% 131% 132% 111% 105% 103%
英国 110% 126% 126% 144% 116% 103% 101%
米国 112% 117% 129% 128% 116% 108% 105%
ブラジル 112% 109% 113% 115% 114% 126% 127%
台湾 100% 100% 100% 117% 112% 111% 126%
中国 100% 100% 101% 101% 100% 100% 100%
韓国 112% 113% 174% 155% 113% 108% 105%
日本 112% 118% 159% 175% 137% 116% 105&
インド 125% 113% 108% 104% 102% 104% 111%
南ア 115% 112% 132% 155% 113% 106% 102%
世界 118% 124% 124% 122% 114% 111% 111%
人口100万人あたりのCOVID-19の死者数推移(東アジアの4カ国)
| |
中国 |
台湾 |
日本 |
韓国 |
| 2002 |
1.97 |
0.04 |
|
|
| 2003 |
2.31 |
0.04 |
0.44 |
3.18 |
| 2004 |
3.22 |
0.25 |
3.28 |
4.84 |
| 2005 |
3.22 |
0.29 |
7.04 |
5.29 |
| 2006 |
3.22 |
0.29 |
7.69 |
5.51 |
| 2007 |
3.24 |
0.29 |
7.93 |
5.87 |
| 2008 |
3.28 |
0.29 |
10.11 |
6.32 |
| 2009 |
3.29 |
0.29 |
12.37 |
8.06 |
| 2010 |
3.29 |
0.29 |
13.88 |
9.05 |
| 2011 |
3.30 |
0.29 |
16.41 |
10.26 |
| 2012 |
3.32 |
0.29 |
26.03 |
17.89 |
| 2101 |
3.35 |
0.34 |
45.49 |
27.79 |
| 2102 |
3.36 |
0.38 |
62.38 |
31.31 |
| 2103 |
3.36 |
0.42 |
72.39 |
33.84 |
| 2104 |
3.36 |
0.53 |
77.00 |
35.69 |
第四波と、将来の感染症に備えて、この度の『後手に回った新型コロナ感染症対策』の経済へのマイナス影響の分析を、スパコン『富嶽』で、是非やってほしいと思っています。
今までは、各方面・分野で『喉元過ぎれば…』で世界中に後れをとっている事例が日本では、多々ありますので。 台湾までとは言いませんが韓国並みに『人口100万人あたりの感染者数』を抑え込んでいたら、と思います
(20210412纏め #313)
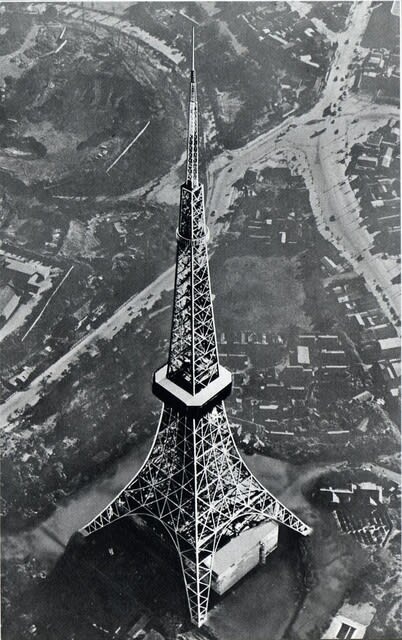





















 ウエブ情報から引用
ウエブ情報から引用
 ウエブ情報から引用
ウエブ情報から引用 ウエブ情報から引用
ウエブ情報から引用





