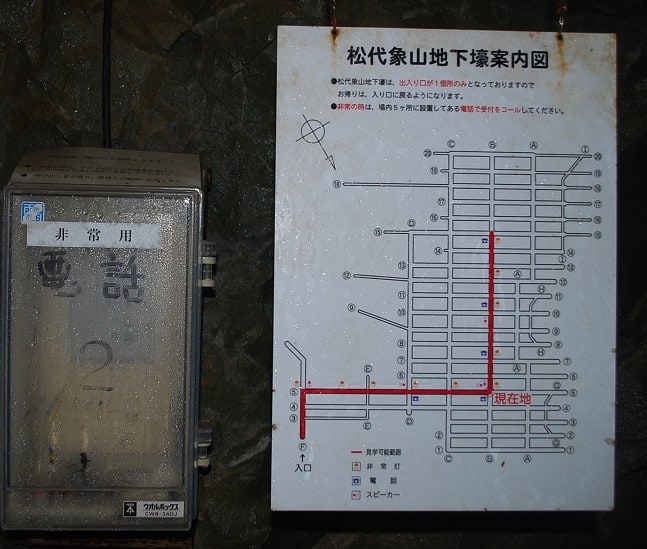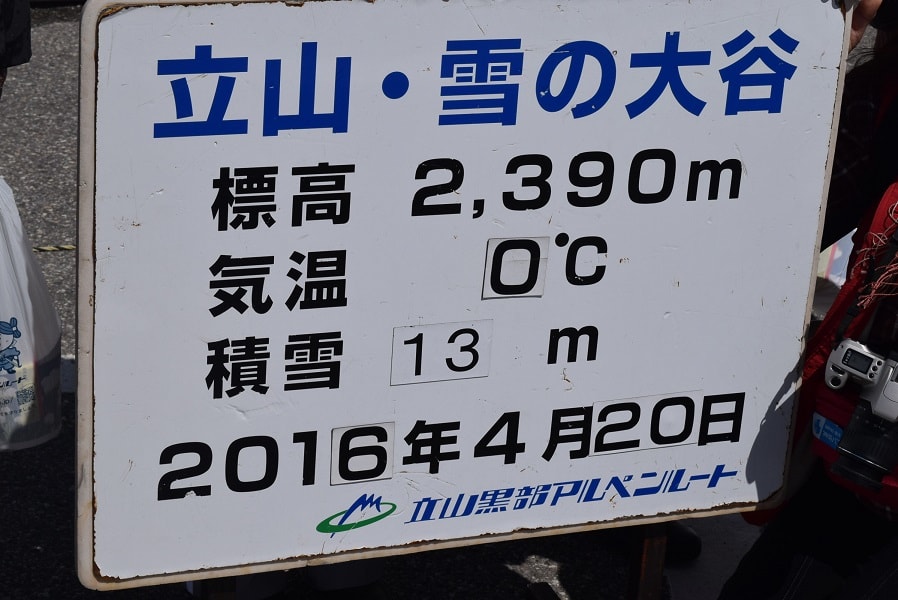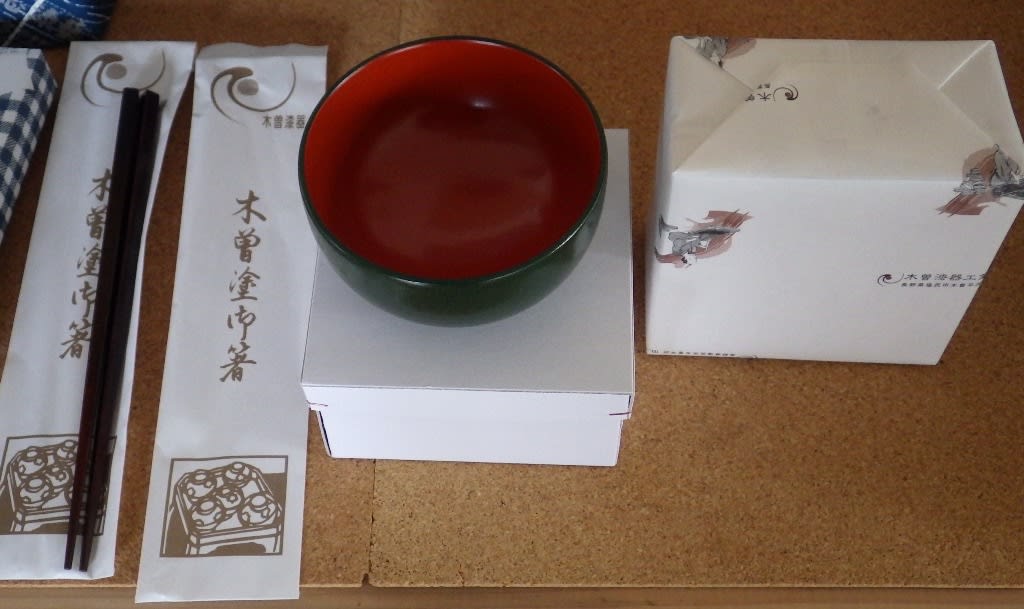峠の我が家に到着した日に何度も地元のTVで放送されていた。
カゴメの工場がある事は知っていたがお邪魔した事はなかった。
今回もお邪魔したのは工場見学ではなく、カゴメ野菜生活ファームです。
事前の予約は一切していませんが、何か目新しい物が在ればとお邪魔しました。
カゴメリリースニュースから引用させて頂きます。
カゴメ株式会社( 本社:愛知県 本社:愛知県 名古屋市 代表取締役社長:寺田直行)は、「カゴメ野菜生活ファーム富士見」(長野県諏訪郡富士見町)の営業を4月26日より開始いたします 。「カゴメ野菜生活ファーム富士見」では、八ヶ岳の雄大な自然の中で野菜の収穫や調理を体験でき、レストランでは旬の食材を使った料理が楽しめます。また隣接する当社富士見工場では野菜ジュースの製造工程が見学できできる、まさに“野菜のテーマパーク”です。3月 6日(水)から「カゴメ野菜生活ファーム」の ホームペーム(*1 )において、工場見学ならびに 体験教室の予約受付を開始いたします。
国道20号から左折してカゴメ富士見工場を右に見て通り越して800メートル程先に進むと駐車場やカゴメ野菜生活ファームの建物をが見えます。
至れり尽くせりの案内の方が誘導してくれました。
迷うことなく到着しました。
この看板が目印です。

こちらは手前にある工場です。
要予約ですが、工場見学できます。













カゴメの工場がある事は知っていたがお邪魔した事はなかった。
今回もお邪魔したのは工場見学ではなく、カゴメ野菜生活ファームです。
事前の予約は一切していませんが、何か目新しい物が在ればとお邪魔しました。
カゴメリリースニュースから引用させて頂きます。
カゴメ株式会社( 本社:愛知県 本社:愛知県 名古屋市 代表取締役社長:寺田直行)は、「カゴメ野菜生活ファーム富士見」(長野県諏訪郡富士見町)の営業を4月26日より開始いたします 。「カゴメ野菜生活ファーム富士見」では、八ヶ岳の雄大な自然の中で野菜の収穫や調理を体験でき、レストランでは旬の食材を使った料理が楽しめます。また隣接する当社富士見工場では野菜ジュースの製造工程が見学できできる、まさに“野菜のテーマパーク”です。3月 6日(水)から「カゴメ野菜生活ファーム」の ホームペーム(*1 )において、工場見学ならびに 体験教室の予約受付を開始いたします。
国道20号から左折してカゴメ富士見工場を右に見て通り越して800メートル程先に進むと駐車場やカゴメ野菜生活ファームの建物をが見えます。
至れり尽くせりの案内の方が誘導してくれました。
迷うことなく到着しました。
この看板が目印です。

こちらは手前にある工場です。
要予約ですが、工場見学できます。