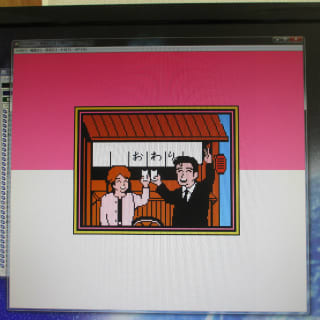大会3日目、外で夕食を食べた鬼ヅモ会員一同は、その帰りにセブンイレブンに寄りました。
この日は中華料理を食べたので、冷たい、さっぱりしたものを口に入れたい気分でした。
「セブンイレブンの良心」と称賛されるアイスコーヒーのカップを手に取ると、近くにあるものを見つけました。
白熊です。
そして白熊といえば・・・
「やあやあ、○○○○!!」 (←○○○○には副会長たか氏の本名が入ります)
ここに鬼ヅモ同好会白熊対決が勃発します。

白熊はおそらくセブン&アイのPBと思われる260ccのものです。
鬼ヅモ会員の中では私とたか氏、そしてよね氏が藩士でありますので、3人で白熊を購入します。
セブンの店員の不手際で、よね氏の白熊だけスプーンがプリン用のものになってしまいました。
そして・・・鹿児島県の西郷公園で西郷どんに見守られながら対決・・・ではなく、
神奈川県のよね氏邸で、藩士ではない会長ともと氏から「なにやってるんだ、こいつら・・・」という表情で見られながら対決です。
そう氏の「Ready Go!!」の掛け声とともに、3人は一斉に白熊をかき込みます。
最初のアイス部分。これが意外にネバネバで食べづらく、そして冷たい。
口の中がキンキンに冷えてしまって、簡単に飲み込むことができません。
一気に飲み込んで頭がキンキンのアイスクリーム頭痛に襲われる、それ以前にやられてしまいます。
ミスター鈴井貴之氏と藤村Dはあんな冷たいものをよくもガッツリ食えるなあ、と心から感心してしまいます。いやホントにすごいです。
さて戦況は・・・私とたか氏が同じくらいで、よね氏が少し遅れているか。
よね氏はミスターの「手のひらでカップをおおう」作戦をとっているようです。
私も途中で思い出してやってみるのですが、これまたカップがむちゃくちゃ冷たい!!
あんな冷たいものを長時間じっと持てるよね氏とミスターに、またしても感心します。
想像以上に冷え冷えの白熊にすっかりやられ、三者三様の嗚咽、悲鳴、唸り声をあげていました。
対決が始まって5分以上経過し、ついにたか氏が勝利のテレマーク!!
それに遅れること20秒、私が完食・・・(T_T)
よね氏はセブン店員の失策に足を取られたためか、4分の1ほど残していました。
優勝したたか氏には、「魔神」の称号が贈られました。
敗北した私は、「挑戦者」に降格です・・・。