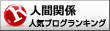礼拝宣教 創世記21章9-21節 平和
今月8月は平和月間としておぼえて、祈り、あゆんでいく月です。6日広島、9日長崎への原子爆弾投下、15日敗戦記念日から73年目を迎えます。核兵器全廃へ国連が舵を切った中、唯一の被爆国の私たちの日本政府はそれを否決し、大変残念な思いを多くの人たちが致しました。原子爆弾によって苦しんでいる被爆者の方々の思いは今も踏みにじられています。9日長崎の平和式典に国連事務総長が初めて参加されるようですが。祈りつつ見守りたいと思います。
私たちの国が戦争への道を二度とたどることのないように、今後の動きに注視しながら、祈りにおぼえていきたいと願うものです。
先日7月24日、連盟の問題特別委員会のフィールドワークが奈良県の水平社博物館で行われ、参加しました。
「人の世に熱あれ、人間に光あれ」で知られる宣言は日本で最初の人権宣言、又被差別マイノリティーが発信した世界で初めての人権宣言とされています。
その記念碑には真っ黒な背景に真っ赤な荊冠:いばらのかんむりが刻まれていました。黒はこの世の闇であり、そこにキリストが十字架に磔にされた折に頭に被された荊の冠を描くことで、「殉教者」の覚悟をもって解放を求め差別と闘う決意を表わしたそうです。実はこれを考案された方は仏教関係者だそうですが、宗教の枠を超えたメッセージをキリストのお姿に見出されたのでしょうか。
もう一つ興味深かったのは、被差別マイノリティーの平等や解放を訴えてきた運動の16回大会において、戦時下に入り初めて日の丸が講壇の中央に掲げられ、「挙国一致」(天皇制)を合い言葉とする戦争協力を全面に打ち出したということです。あえてそうしたのは、一丸となって国に協力することを通して差別がなくなる社会になると考えたからです。けれど結果的に戦争は多くの犠牲者を作り、人を殺し他国を侵略する分断と差別を生み出す結果にしかならなかった。差別されていたものが一致団結のもとで差別する側になっていったということであります。このことは心に深く残りました。
さて、今日は先週読みました創世記21章のイサクの誕生に続く記事であります。
神の賜物として与えられた約束の子イサクが乳離れをして間もなく。サラはエジプトの女ハガルがアブラハムとの間に産んだ子が、イサクをからかっているのを目にします。サラはアブラハムに、「あの女とあの子を追い出してください。あの女の息子は、わたしの子イサクと同じ跡継ぎとなるべきではありません」と訴えます。
そもそも事の始まりは、子供がいないサラが自分のエジプト人の女奴隷ハガルをアブラハムのもとに連れて来て、「側女としてほしい。わたしは彼女によって子供が与えられるかも知れないから」と頼み、アブラハムはそれを受け入れてハガルはみごもるのです。
ところがそうなりますと、ハガルは女主人のサラを軽んじるようになります。その心におごりたかぶりが表われたのです。
サラはこのハガルの態度に怒り猛然とアブラハムに抗議し訴えます。それに対してアブラハムから、「女奴隷はあなたのものだ、好きなようにするがいい」と言われたサラは、ハガルにつらく当たったので、身重のハガルは荒れ野に逃げます。
まあ人間くさいというか、それぞれの思いや感情、その言動がここには赤裸々に記されていますが。そういった人間の側の思惑を超えたかたちで、そこに神さまが介入して来られるのです。
逃げたハガルが荒れ野の泉のほとりまで来ると、主の使いが彼女と出会い「どこへ行くのか」とお尋ねになります。
ハガルが事情を話しますと、御使いは彼女に「女主人のもとに帰って従順に仕えなさい」とさとした上で、「あなたの子孫を数えきれないほど多く増やす」と約束し、「その子をイシュマエル(神は聞かれる)と名付けなさい。主があなたの悩みをお聞きになられたから」と伝えます。
それを聞いたハガルは「あなたこそエル・ロイ(わたしを顧みられる神)」と言って、主の言葉に従い、帰って行きます。
ハガルは女主人サラのもとに戻ることに対して、人間的には抵抗感や反発心を抱くような感情もあったかもしれません。けれど主のおっしゃるまま帰って行くのです。
ここで肝心なのは、彼女が人間的な思いはいろいろあったと想像できますが、主に信頼し、主のお言葉通りに自分を従わせた、ということですね。
そのことによって主のご計画は実現し、アブラハムが86歳の時にその子が生まれ、ハガルはその子にイシュマエルと名付けるのであります。
さて、そうした事の後にサラはイサクを産み、その子が乳離れした頃。
今日の箇所では、ハガルの子イシュマエルがサラの子イサクをからかっているのをサラが見て、「あの女とあの子を追い出してください」とアブラハムにまた訴えたというのです。
先の箇所ではハガルが荒れ野に逃亡せざるを得なくなったのにはハガルにも非があったわけですが。今日の箇所はある意味不可抗力といいますか、ハガルには何ら非がないといえます。まあ子供の間に生じたことによって、ハガルとその子イシュマエルは荒れ野に追いやられてしまうのですね。
ちなみに、イシュマエルとイサクの誕生時のアブラハムの年齢から換算しますと、イシュマエルとイサクの年齢差は14歳開いていたと考えられますが。「イシュマエルがイサクをからかっていた」というのがどういう状況であったのかはわかりませんけれど、サラにとってはそれがたまらなく悔しく許せないことだったのでしょうか。
このサラの訴えは「アブラハムを非常に苦しめた。その子も自分の子であったからである」と記されています。
非常に苦しめたという原意・もとの意味は「アブラハムの目に非常に悪だった」ということになるそうです。まあ、サラの「あの女とあの子を追い出してください」との言動がアブラハムの目に非常に悪だと見えて彼を悩み苦しめたということですね。
すると神はアブラハムに「あの子供とあの女のことで苦しまなくてもよい。すべてサラが言うことに聞き従いなさいとおっしゃいます。
この、「すべてサラがいうことに聞き従いなさい」と神さまがおっしゃるというのは意外な気がします。神はどうして、このわがままともいえるサラの肩をもたれるのか、そう思われる方もおられるのではないでしょうか。
けれど、実はここでアブラハムは試みられているのですね。
アブラハムにとってイシュマエルはイサク同様我が子に違いありません。ハガルに対する思いもあったでしょう。彼らをサラの言うとおり荒れ野に追い出すなんて、アブラハムはどんなに忍びなかったでしょう。又、自分の目に悪と映ったことには激しい葛藤がったかも知れません。けれどアブラハムは神のお言葉に自分を従わせました。
先のハガルが荒れ野において女主人のもとに帰りなさい、とのお言葉に自分を従わせたように、アブラハムは神に従ったのです。
神は続けてアブラハムに、「あなたの子孫はイサクによって伝えられる。しかし、あの女の息子も一つの国民の父とする。彼もあなたの子であるからだ」と、約束なさいます。
アブラハムが自分の考えや思い煩いを神にゆだね御言葉に従った時、「苦しまなくてもよい」との、その神さまの約束とそのご計画が実現していくのですね。
アブラハムは、せめて陽が暑くならないうちにと考えたのでしょうか。朝早くに荒れ野の険しい道に備えてパンと水の入った革袋をハガルに与え、背中に負わせて、イシュマエルとともに送り出します。
こうしてハガルは子供と一緒に立ち去り、ベエル・シェバの灼熱の荒れ野をさまようことになるのです。
人っ子一人いない灼熱の荒れ野において遂にアブラハムが用意してくれた革袋の水は無くなります。ハガルは一本の灌木の下に子供を寝かせ、「子供が死ぬのを見るのが忍びない」と言って、矢の届くほど離れ、子供の方を向いて座り自ら声をあげて泣きます。遠くから見える子供も泣いていたのでしょう。
するとハガルに神の使いのお言葉が臨みます。
「恐れることはない。神はあそこにいる子供の泣き声を聞かれた。立って行って、あの子を抱き上げ、お前の腕でしっかり抱き締めてやりなさい。わたしは、必ずあの子を大きな国民とする」。
ここは旧約聖書の中でも本当に神の慈しみをおぼえる箇所ですね。
人間の社会やその関係には時に差別や排除が生じます。それは逃れ難い人間の性質から起ってくるのでありますが。しかし神はその世の中から出されて泣くほかないような人の泣く声、神に訴えるほかない人の叫びを、聞いておられるのですね。
イシュマエルという名は「神は聞かれる」という意味をもっています。神は、まさにその名のとおり世から見捨てられたようなイシュマエルの声を聞かれるお方なのであります。
さて、神がハガルの目を開かれたので、彼女は水のある井戸を見つけ、その井戸の水を革袋に満たし子供に飲ませることができました。死を待つほかなかったイシュマエルの命を救い出されたのです。
又、そればかりか「神がその子イシュマエルと共におられたので、その子は成長した」とあります。神はどこまでもこのイシュマエルに慈しみを示されるのですね。
実はそこには理由があります。
それは「彼もイサクと同様アブラハムの子であり、アブラハムにあってイサクと兄弟だから」です。
イサクはアブラハムの子、いわゆる約束の子として選ばれたシオンの民の基となっていきます。そして神はイシュマエルにも、その約束どおり大いなる国民の父とされ、その死後イサクと共に父アブラハムの墓に納められたと25章に記されています。
イサクとイシュマエルは全く別の人生を歩みましたが。最後は父と兄弟同じ墓に納められました。そこに神さまの偉大な愛とそのご計画の深さを見せられる思いがいたします。
「神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである」とのヨハネ3章16節は聖書の命の言葉を凝縮した一番濃い内容だとされます。
ひとりとして、神の愛されていない者などいない。神は御子イエスさまを十字架に引き渡してまでも私たち一人の命が尊く、滅びてはならない存在として見捨てられることなく、愛を注ぎ続けて下さっているお方です。その証明が主イエスの十字架です。
最後に、今日のこの個所から思いますのは、私たちは目に見えるところによって良し悪しの判断をしてしまいがちですが。神さまはいつも主に聞き従う者に最善の道をご計画してくださっている、ということです。
ハガル、そしてアブラハム。彼らはある意味、自分を悩ます苦境に立つ中で、主のお言葉に信頼し聞いて行うことをまさに実践しました。そのことを通して、主が導かれる最善に与るのです。
御言葉は聞くことで終わるのではなく、それを聞いて行っていくときにその効果は発揮され、神の備えたもう最善が起こされていく、ということを今日の聖書の御言葉から私たちも受け取ってまいりましょう。
8月の平和月間の一日一日、キリストにある平和を心から祈り求めて歩む私たちでありたいと願います。
今日もここからそれぞれの場へと遣わされてまいりましょう。祈ります。