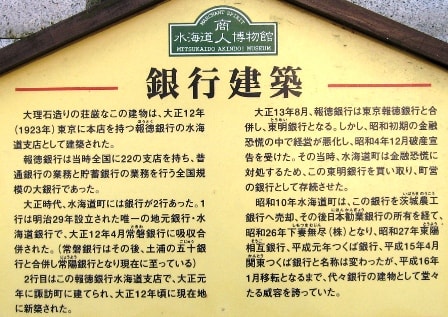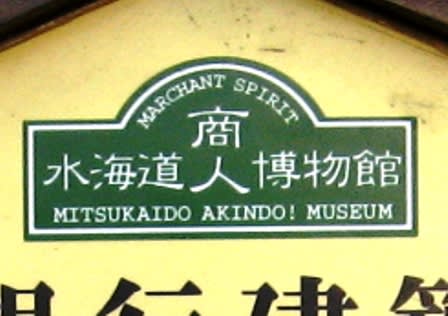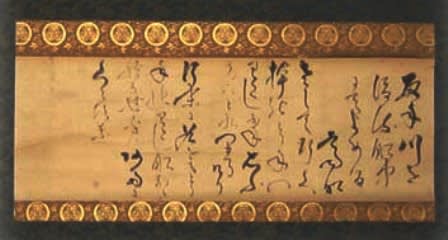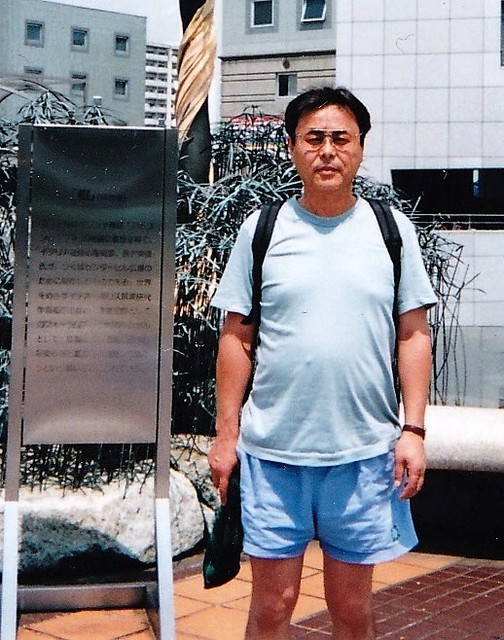昨日の続きです。
外に出ました、改めてこれが新館の建物です。三部屋あり、それにトイレで、各部屋の広さは10畳ほどだったと思います。
ホントにお寺か神社の佇まい。朝鮮半島に調査に行った際、あちらの建物の様式が気に入り、取り入れたそうです。そう云われて見ると、そんな雰囲気があります。

この写真は、我孫子見学の終盤に撮ったものです。画面中央の林の中に建っています。大通りとの間は未だ空き地になっています。

この空き地にもそのうち建物が建ってしまうことでしょう。手賀沼の湖畔に建っていた別荘は、町中の裏通りの別荘になってしまいます。
知らない人が通りがかりにこの建物を見れば、間違いなくお寺か神社と思う筈。

昭和2~3年にかけて(正確な記録がない?)建てられたようで、大正12年の関東大震災の経験から、建物の基礎部分は鉄筋コンクリートにしたそうです。
堅固さんは、震災で恐ろしい惨状を目の当たりにしたか、自らもかなりの恐怖を体験をしたのかも知れません。
寝室を母屋ではなく、強固な基礎の上に立てられた新館にしたのも、恐怖の記憶に依るものかも知れません。

基礎部分は床下倉庫になっています。
“展望室”のガラス窓は出窓になっていたのです。腰掛けの下は何も無いのです。強度的にはかなり弱いです。

鋳造品の金具で補強して有りますが不安な構造です。展望室の出窓構造は基礎が出来上がってからの設計変更でしょうか。

出窓部分もしっかりとしたコンクリートの基礎の上に造ってほしかったです。

これを見てからですと、出窓に巡らす腰掛けに安心して座り、のんびり酒も呑めなくなります。

これで、新館部分が終わったのですが、未だ母屋があるのです。ガイドの方の親切丁寧な説明を受け、村川さんの別荘見学はまだ続きます。
それでは、また明日。
外に出ました、改めてこれが新館の建物です。三部屋あり、それにトイレで、各部屋の広さは10畳ほどだったと思います。
ホントにお寺か神社の佇まい。朝鮮半島に調査に行った際、あちらの建物の様式が気に入り、取り入れたそうです。そう云われて見ると、そんな雰囲気があります。

この写真は、我孫子見学の終盤に撮ったものです。画面中央の林の中に建っています。大通りとの間は未だ空き地になっています。

この空き地にもそのうち建物が建ってしまうことでしょう。手賀沼の湖畔に建っていた別荘は、町中の裏通りの別荘になってしまいます。
知らない人が通りがかりにこの建物を見れば、間違いなくお寺か神社と思う筈。

昭和2~3年にかけて(正確な記録がない?)建てられたようで、大正12年の関東大震災の経験から、建物の基礎部分は鉄筋コンクリートにしたそうです。
堅固さんは、震災で恐ろしい惨状を目の当たりにしたか、自らもかなりの恐怖を体験をしたのかも知れません。
寝室を母屋ではなく、強固な基礎の上に立てられた新館にしたのも、恐怖の記憶に依るものかも知れません。

基礎部分は床下倉庫になっています。
“展望室”のガラス窓は出窓になっていたのです。腰掛けの下は何も無いのです。強度的にはかなり弱いです。

鋳造品の金具で補強して有りますが不安な構造です。展望室の出窓構造は基礎が出来上がってからの設計変更でしょうか。

出窓部分もしっかりとしたコンクリートの基礎の上に造ってほしかったです。

これを見てからですと、出窓に巡らす腰掛けに安心して座り、のんびり酒も呑めなくなります。

これで、新館部分が終わったのですが、未だ母屋があるのです。ガイドの方の親切丁寧な説明を受け、村川さんの別荘見学はまだ続きます。
それでは、また明日。