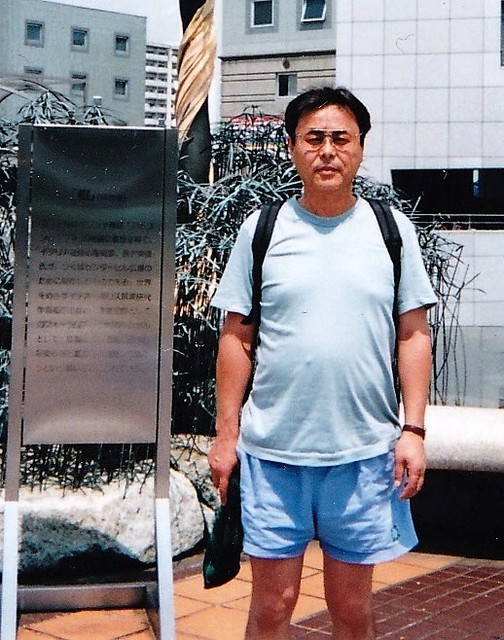いろいろ歩き回っているのですが、見学者は他に誰も居ません。それに、職員らしき人の気配も有りません。昼の休憩時間なのかも知れません。
誰も居ない、広い屋敷を先ほどより一人でウロウロ、キョロキョロしています。多分、問題はないと思うのですが、誰も居ないと少し心配になります。
兎に角、勝手に歩き回り、見て回り、触れて回り、撮り捲ります。
この電話室、昔の「お金持ちのお屋敷」には必ずあったのです。テレビや映画では見たことがありましたが、実物を見るのは始めてです。

正面玄関の裏手、脇玄関を入った処に、電話室がありました。電話を掛ける為に、わざわざ専用部屋を造る、今から思うと不思議です。
公共の建物とか町中でしたら、他人の耳が気になるので実用上必要でしょう。
個人の家の中に造るのは、実用性と云うよりも、資産家の「ステータスシンボル」として、当時、流行ったのでしょう。
電話室の壁にあった貼り紙です。

警察が2番で、野田の390番はどこなの? 非常用の番号ですから、それなりの処なのでしょう。しかし、警察があって消防がないのも不思議です。
390番は、警察より下、消防よりも上、一体どこなんだ!そこは? 警察が2番とすると、普通に考えると、消防は1番か3番になる筈ずです。謎の390番です。
電話室から奥に進み、台所に来ました。
マホービンに、湯飲み茶碗に、薬缶が沢山並んでいます。この台所も現役です。

飾り気がなく、しっかりと造られた重量感のある食器棚です。この辺りはお金を掛けず、実用性が最優先で造られています。サスガに経営者です。

ガスコンロの台は、焚き口が二つ有り、薪を焚いた竈と思われます。しかし、焚き口の中には何故か?「ゴミ」が詰まっていました。
ここまでは、管理が行き届いていると思っていたのですが、見てはいけないものをを見てしまったようで、残念でした。

台所の先は風呂場になっていました。白いタイルに、紅色のベンガラ入り漆喰壁、「艶めかしさ」を感じます。それにしても「白と紅」の配色は鮮やかです。
壁に取り付けられた、シャワーヘッドがイイです。

洗い場は8畳ほどの広さで、ゆったりとしているのですが、湯船がとても狭いのです。二人で入る・・・・・・別に、二人で一緒でなくてもいいのですが・・・・・・のはとても無理です。
一人はシャワー、一人は湯船に浸かる・・・・・・・そう考えても洗い場は無駄に広すぎます。冬場など、浴室内は暖房でもしない限り、寒くて居られない気がします。

浴室の天井は手の込んだ板張りになっています。

洗面所も広く、洗面台が二つ並んでいます。この造り、懐かしいです。温泉地の古い旅館を思い出します。

床は寄せ木細工の板張りになっています。

台所、風呂場、と書いてきて、水回り3点セットの「トイレ」を見て来るの忘れた事に気づきました。
いつもの「トイレチェック」を忘れたのは残念です。風呂場、洗面所の凝り方から推測して、それなりのトイレの筈です。
あの広さですから2~3ヶ所はある筈です。しかし、気が付かなかったのも不思議です。厠として別棟だった?
茂木邸は見るところが多くあり、楽しませてもらいました。
さぁーてと、次は「郷土博物館」です。
それでは、また明日。