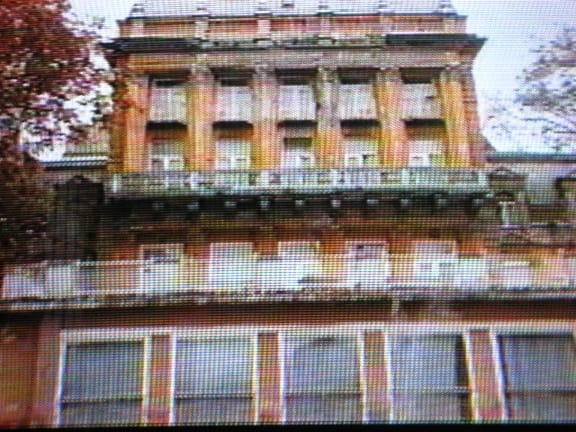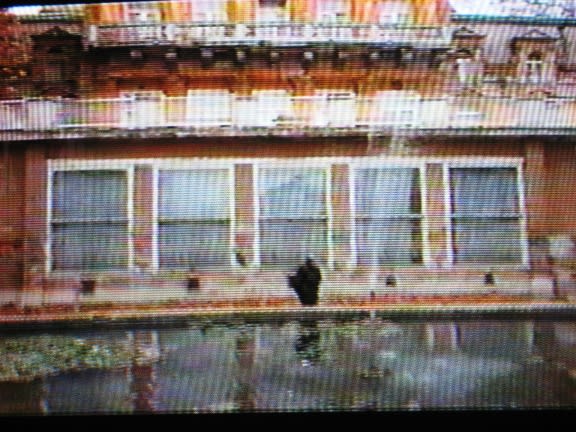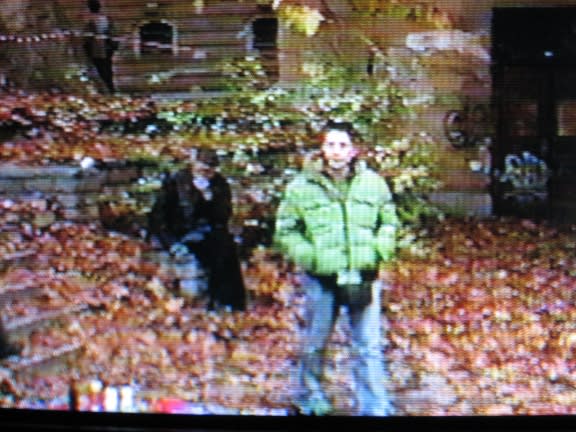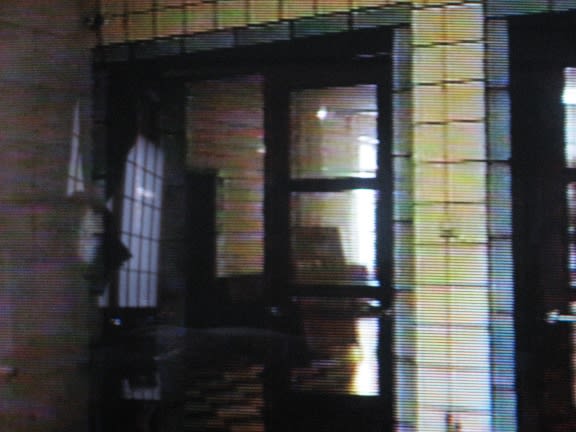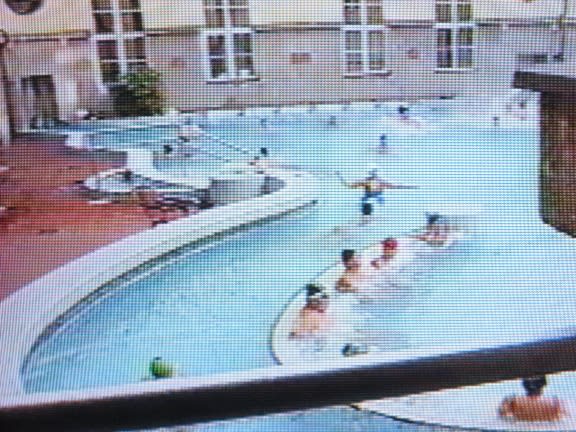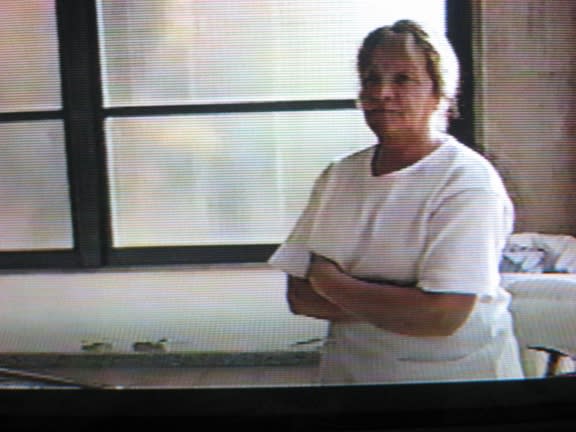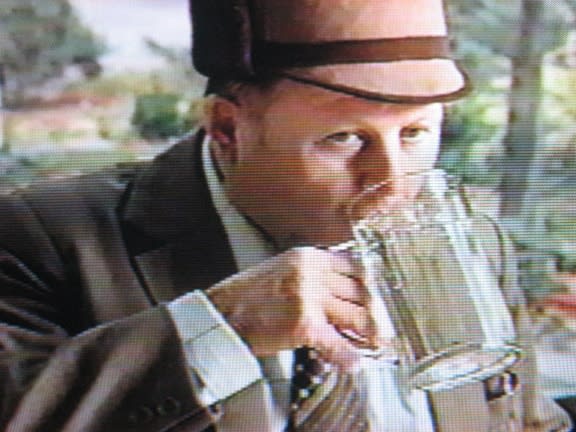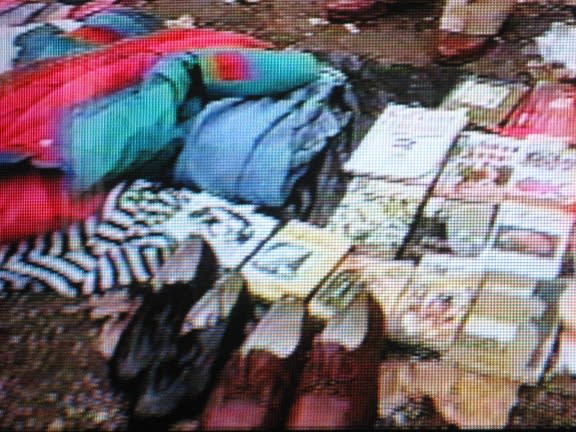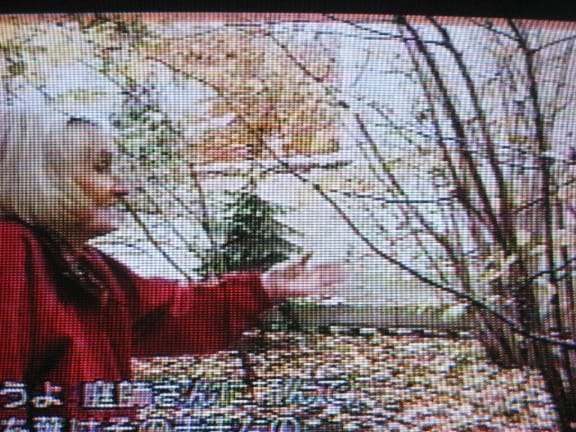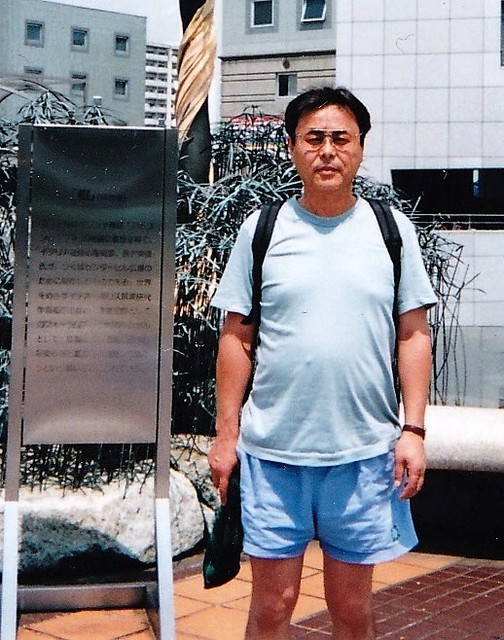先週の続きです。
ハンガリーの首都ブタペストの“ブタ”側を歩いています。
ここは“銅像公園”、たくさん、たくさん、銅像があります。これは、第二次世界大戦で、ナチスドイツに占領されたハンガリーを、“解放”した“ソビエト軍兵士の像”です。

こちらは“解放”してくれたソビエト連邦の指導者スターリンの銅像です。靴しかありません。それにしても“デカイ”です。右下の人と比較すると靴だけで3メートルはありそうです。

ハンガリー国民を解放してくれたソビエト連邦、そして、解放者は“支配者”となったのです。小さな国は大変なのです。
そのソ連支配からの“独立”を闘い、そして敗れた1956年の“ハンガリー動乱”、スターリン像は引き倒され靴だけが残ったのです。
この銅像公園には、ソ連支配時代に各地に造られた、42体の銅像が1989年の民主化後、ハンガリー国内からここに集められ、観光名所になっているそうです。
つい最近迄、全国にこんなモノが立ってたのですから、ハンガリー国民は、今更、のこのこ出掛けて来て、こんなモノをとても見上げる気には・・・・・・、きっと観光と云っても海外からの観光客が主なのでしょう。
この“靴だけ像”は、何処かで見覚えがあります。あのイラクの“サッダーム・フセイン大統領像”引き倒し“事件”です。
まぁ、このとき“参加”したのは“一部の国民”だったらしいのですが、こちら“スターリン像引き倒し”は、多数の国民によって行われたそうです。
“サッダーム・フセイン体制”と“スターリン体制”には、似通った特徴があると、専門家の間では云われているそうです。確かに、二つの“靴だけ像”からも、そのことは云えそうです。
このような事は、歴史上でも、2度あることは、3度ありそうです。3度目の靴だけ像は、我が国に近い、あの半島の、あの独裁者の一族が、国民多数の手により・・・・・・、アッ! これ以上、触れては、内政干渉に、そうです、その国の国民の決めることでした。
独裁者、独裁国家は、大きな銅像とか、大きな建造物を好むようです。

大きなモノは、見上げているうちに、大きいだけで、それなりに、偉いとか、尊敬とか、かしずきたい、ひざまずきたい、逆らえない、逆らってはいけない、支配されたい、支配されて当然だァ、となり。

そして、いつしか、思考停止状態になり、支配して下さい!、万歳!、万歳!、万歳!、と、涙を流し叫んでしまう。そんな効果を期待するのでしょうか。
我が国には、為政者の手による“為政者の大きな銅像”は、今のところはありません。見上げるような、銅像が造られた、その時では、もう・・・・・・手遅れなのです。
日本では、今のところ、見上げるような大きな銅像と云えば、

大仏か、観音様です。これは、見上げても、頭を下げても、手を合わせても、涙ぐんでも、叫んでも?、大丈夫です。
今日は、ブタペストの“銅像公園”ウロキョロしました。
“他人のふんどしシリーズ”は、明日が最終回の予定です。
それでは、また明日。
ハンガリーの首都ブタペストの“ブタ”側を歩いています。
ここは“銅像公園”、たくさん、たくさん、銅像があります。これは、第二次世界大戦で、ナチスドイツに占領されたハンガリーを、“解放”した“ソビエト軍兵士の像”です。

こちらは“解放”してくれたソビエト連邦の指導者スターリンの銅像です。靴しかありません。それにしても“デカイ”です。右下の人と比較すると靴だけで3メートルはありそうです。

ハンガリー国民を解放してくれたソビエト連邦、そして、解放者は“支配者”となったのです。小さな国は大変なのです。
そのソ連支配からの“独立”を闘い、そして敗れた1956年の“ハンガリー動乱”、スターリン像は引き倒され靴だけが残ったのです。
この銅像公園には、ソ連支配時代に各地に造られた、42体の銅像が1989年の民主化後、ハンガリー国内からここに集められ、観光名所になっているそうです。
つい最近迄、全国にこんなモノが立ってたのですから、ハンガリー国民は、今更、のこのこ出掛けて来て、こんなモノをとても見上げる気には・・・・・・、きっと観光と云っても海外からの観光客が主なのでしょう。
この“靴だけ像”は、何処かで見覚えがあります。あのイラクの“サッダーム・フセイン大統領像”引き倒し“事件”です。
まぁ、このとき“参加”したのは“一部の国民”だったらしいのですが、こちら“スターリン像引き倒し”は、多数の国民によって行われたそうです。
“サッダーム・フセイン体制”と“スターリン体制”には、似通った特徴があると、専門家の間では云われているそうです。確かに、二つの“靴だけ像”からも、そのことは云えそうです。
このような事は、歴史上でも、2度あることは、3度ありそうです。3度目の靴だけ像は、我が国に近い、あの半島の、あの独裁者の一族が、国民多数の手により・・・・・・、アッ! これ以上、触れては、内政干渉に、そうです、その国の国民の決めることでした。
独裁者、独裁国家は、大きな銅像とか、大きな建造物を好むようです。

大きなモノは、見上げているうちに、大きいだけで、それなりに、偉いとか、尊敬とか、かしずきたい、ひざまずきたい、逆らえない、逆らってはいけない、支配されたい、支配されて当然だァ、となり。

そして、いつしか、思考停止状態になり、支配して下さい!、万歳!、万歳!、万歳!、と、涙を流し叫んでしまう。そんな効果を期待するのでしょうか。
我が国には、為政者の手による“為政者の大きな銅像”は、今のところはありません。見上げるような、銅像が造られた、その時では、もう・・・・・・手遅れなのです。
日本では、今のところ、見上げるような大きな銅像と云えば、

大仏か、観音様です。これは、見上げても、頭を下げても、手を合わせても、涙ぐんでも、叫んでも?、大丈夫です。
今日は、ブタペストの“銅像公園”ウロキョロしました。
“他人のふんどしシリーズ”は、明日が最終回の予定です。
それでは、また明日。