添い寝夫婦は一端さ。
租は1段につき稲2束2把で、収穫量の3%であった。
〈2018早大・教育(文科系)
問7.下線部d徴税に関連して、律令国家の税制について述べた文として、正しいものはどれか。一つ選べ。
ア.調は地方の財源となった。
イ.雑徭は中央において使役される労役であった。
ウ.租は主に郡家の正倉に貯蔵された。
エ.計帳は6年に1度、作成された。
オ.税負担において男女の区別は、ほとんどなかった。」
(答:問7ウ〇 ※ア×中央の財源、イ×地方財源、エ×毎年作る、オ×女は男の3分の2)
〈2017慶大・商
〔三〕律令制のもとでは、全国は畿内および[ 2 ]つの道に分けられた。公民は戸籍・計帳に登録され区分田が支給され、収穫の約[ 3 ]%にあたる租税や兵役などさまざまな負担が課せられた。」
(答:2→7、3→3)
七道
「僕とさ」とかな催淫よ。
北陸道 東山道 東海道 南海道 西海道 山陰道 山陽道
〈2017関西学院大・文2/3
問1 下線部a律令に定められた多様な種類の税に関して、七道の諸国の状況として誤っているものを下記より選びなさい。
ア.租(田租)は口分田などに課せられ、年齢・性別を問わず1段あたり稲2束2把を納めた。
イ.調は正丁・次丁・中男に課せられ、絹や布、郷土の産物を納めた。
ウ.庸は正丁・次丁に課せられ、歳役にかえて布を納めた。
エ.雑徭は正丁・次丁・中男に課せられ、都で10日間の労役を行なった。
(答:エ×)
〈2016関西学院大学・全学部2/1
問5.下線部5統一的税制に関して、正しい文を下記より選びなさい。すべて誤っている場合は、「エ」をマークしなさい。
ア.旧来の税制も廃されることはなく、並行して用いられた。
イ.田地に賦課する租と、各戸に課される庸・調の併用で、いわゆる人頭税はなかった。
ウ.後の大宝令では、田に対して収穫の約15%の税が課せられた。
(答:問5エ※ア×旧来の税制は廃止、イ×庸調は人頭税、ウ×約15%→約3%)
〈2014早大・文化構想
3 下線c律令制下の農村に関する文章として正しいものはどれか。1つ選べ。
ア 人々は口分田1段につき、2束3把の稲で納める租を負担させられた。
イ 朝廷は6年ごとに戸籍をつくり満6歳以上の男子のみに口分田を与えた。
ウ 人々は姓を持つ部民と姓を持たないに区分されていた。
エ 凶作に備えて粟などを徴収して貯蓄しておく義倉の制度が行われた。
オ 主に金銭を民間で貨し出す私出挙や、国衙などが貸し出す公出挙が行われた。
(答:エ〇 ※ア×2束2把、イ×男女に、ウ×姓はない、オ×貸し出すのは稲)〉
〈2012学習院大・法
問2 下線部租を納める義務を負ったに関して、租は、律令の規定では口分田1段あたり何束何把と定められていたか、答えなさい。」
(答:2束2把)
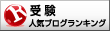
受験 ブログランキングへ
















