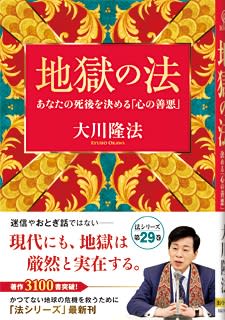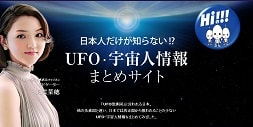『民主菅政権で日教組が力を増す─脱原発論者の中核はこういう人たち』
http://blog.goo.ne.jp/georgiarule/e/7b65d9a9c1a62a1f8875fd91b2ee2c66
「女性のための『日教組』入門・前編」 の続きです
対談 「女性のための『日教組』入門・後編」より
教育評論家 森口朗×ジャーナリスト 田中順子
全国一斉の学力テストはなぜ必要か
田中順子氏(以下、田中) 2009年に民主党が政権をとって以降、その支持団体である日教組の主義主張が日本の教育方針になっています。
森口朗氏(以下、森口) その通りです。世論がよほど反対しない限り、民主党政権は日教組の主義主張を政策に反映すると見て、まず間違いないでしょう。
田中 象徴的なのは、民主党が政権を取ったとたんに、全国一斉に行われていた学力テストが抽出性になってしまいました(※1)。これは日教組がずっと要求していた事ですね。
森口 民主党は、「学校独自の教育方法を尊重する事が大事であり、全国一律を押し付けるのはよくない」「地方分権を進めるべき」と言う論法で来ました。確かに、全国平均を見るだけならば、3割も抽出すれば充分でしょう。しかし、「この学校はどうか」「この市町村はどうか」という個々の学力をフェアに比べる土壌がなければ、そもそも学校独自のやり方など認められないはずです。
田中 全国一斉に行われる学力テストは、全ての子供達が、必要な学力を身につけているか、学校はきちんと指導を行っているかを計るためのものです。また、継続的に測定する事で、問題点が明確になり、改革をした場合の効果も検証する事が出来ます。「学校独自の教育方法によってどのような結果が出ているのか、それは正しいのか」を判断するためにも、全国一斉でなければなりません。抽出性では問題点や責任の所在が曖昧になり、頑張っている学校もそうでない学校も表に出ないので、指導のしようも改善のしようもありません。
かわいそうなのは、適切な学力をつけることが出来ない学校で学ぶ子供達です。
森口 そうなのです。ですから、地方分権を尊重するというならば、逆に全国一斉の統一テストだけは、しっかりと実施しなければいけないと思います。
(※1)学力低下の批判を受け、2007年に小学校6年生と中学3年生全員を対象とする調査が再開されたが、2010年、民主党政権下で、約3割の抽出方式に変更された。ただし抽出されなかった学校でも希望があれば参加が可能で、2010年は約7割の学校が参加した。
1960年代に学力テストが中止された経緯
森口 1960年代にも、日教組と、日教組に同調した一部のマスコミの圧力によって全国一斉の学力調査が中止された事がありました。産業の国外流出が起きる以前の、首都圏から地方に工場が移転していた時代のことです。そのとき、「教育水準が高い県の方が工場の誘致に有利である」と言う噂が流れたんですね。各県は学力を競い合うようになり、その結果、教育現場で何が起こったか。学力の低い子供を学力テストの日に休ませる、カンニングを黙認する、といった弊害が一部の地域で起き始めたのです。
それを毎日新聞が連載記事にして書き立てたために、日本中が大騒ぎになりました。そして、「全国一斉のテストがあるから、こんなことになるのだ」という、一斉テストに反対する日教組の主張どおりの世論ができ上がってしまったんですね。
田中 問題のすり替えですね。それは不正を正せばいいのであって、テストそのものの問題ではありません。
森口 その通りです。「カンニングが起きたから、今後、京都大学では入試を実施しない」などといったら笑いものですが、彼らの主張はそういうことです。
学力テストの結果を公表すべき
田中 そもそも全国一斉テストの目指すものは、「全ての子供に一定の学力を身に着けさせる」ということのはずです。ですから、全国が合格ラインに到達するよう努力するということは可能です。そして優秀な学校のやり方を学び、さらに子どもたちの学力を上げていくよう努力することが、日本全体の学力向上につながります。
日本の子供の学力低下が指摘されている今、結果平等や、結果から目をそらすようではいけませんね。
サッチャー首相時代のイギリスの教育改革でも、国が教育内容を定め、全国を公表して、親が学校を選べる仕組みをとり得れました。弊害も指摘されていますが、切磋琢磨によってイギリスの教育は復活しました。
森口 やはり、日本でも一斉テストを行い、その結果について情報公開すべきです。もし県単位、市町村単位で情報をオープンにすることになれば、必ず、「わが県は学力日本一を目指します」と言う首長が出てくるでしょう。学校単位までオープンになれば、「わが校を市下一番、県下一番の学力にします」という校長が出てくるはずです。そうした首長や校長がマスコミなどに取り上げられ、結果を検証され、地域住民から支持されるようになれば、日本全体に「学力向上を目指そう」という空気が生まれます。日本人は空気に支配されて動きますから、そうした空気をつくることが大事なんですね。
結果を公表したら、その先は、自治体や各学校に任せればいいと思います。
田中 今は学校だけでなく塾に行かないと受験に対応できません。ダブル・スクールでくたびれきっている子供達を見るにつけ、学校の役割はなんなのかと疑問に思ってしまいます。また、公立学校の予算は私たちの税金でまかなわれています。税金のほかに塾費を払うのは、家計にとっても大きな負担です。
学校で何を学び、どのような学力がついているのか、情報を開示するのは学校の責任であり、また学校運営に関心を持って発言し、参加するのは親の義務ではないかと思います。
マカレンコの集団主義教育
田中 現代日本の教育が抱える問題は3つあります。一つは前回お話いただいた自虐史観教育、ふたつ目は学力低下、そして3つ目がいじめ問題です。はじめのふたつには日教組が関わっています。いじめ問題に関しても、「子供達の問題よりも政治活動に熱心であるために、学級崩壊が起こり、いじめが止められない」と言われていますが、いかがでしょうか。
森口 いじめの責任が日教組にあるというのは、一部、言いがかりの部分もあるとは思います。ただ、問題の核をついているともいえるかもしれません。戦前のソ連(現・ロシア)に、アントン・マカレンコ(※2)という教育学者がいました。労働者の団結によって「集団主義教育」という教育手法を提唱した学者です。日本でも、班活動やクラス対抗の活動があり、私も基本的には、子供達を集団で競わせることはいいことだと思います。しかし、マカレンコ的な発想をする共産主義者は、競う事よりも集団そのもの、集団の団結そのものに価値を置くんですね。
そのマカレンコに影響を受けた日教組の先生方が、『仲間外し実践』というものを推奨した事があります。集団のルールに従わない子、集団の空気になじまない子を仲間外しすることによって、集団に帰属する事がいかに大切であるかを教える、という教育です。
田中 先生がいじめを主導する事が学校で行われていたのですか。
森口 50年以上経った今でも、そうした教育手法を行っていた。“空気”は、まだ何となく残っています。ですから、日教組がいじめ問題を悪化させた、という部分がないわけではない。
もちろん、今現在、マカレンコの集団主義教育を本気で正しいと思っている日教組職員は、おそらく1%もいないと思いますが。
田中 先生が仲間はずれを認めていると、子供達は敏感にそれを感じ、自分達が悪い事をしているという意識を失います。学校が正義を示さないと、「いじめは悪である」ということさえわからなくなってしまいます。
(※2)アントン・マカレンコ・・・・1888~1939年。帝政ロシアからソビエト社会主義連邦共和国に移り変わっていく時代の教育学者。子供の個性や自発性よりも、集団への服従や協同に重きを置く「集団主義教育」を唱えた。
いじめを隠ぺいする役人体質
田中 いじめがあっても隠そうとする、学校の隠ぺい体質も指摘されていますが。
森口 それは共産主義というより、「責任を逃れたい」という役人体質、公務員体質の部分でしょう。
例えば、横領のような不正は、自分が主体的に「行う」不正です。しかし、いじめの隠ぺいというのは、何も「行わない」といことですから、サボタージュ(怠慢)なんです。いじめの種を自らまく教師も一握りはいますが、多くの場合はサボタージュです。
やはり集団があれば、いじめのような事が起きることは避けられません。ただ、それが起きた時に、自ら乗り出す勇気のない教師が多いわけです。あえて乗り出さなくても、3月31日がくればクラス替えなり、卒業なりで、時が解決してくれるわけですから。
田中 その間いじめられ続ける子供の気持ちを考えたら、問題の先延ばしなど許されません。
森口 そうです。ただ、いずれにしても、これは教師個人の資質による部分が大きいと思います。いじめを全て日教組のせいにするのは、ちょっと酷かなという気もします。
今、親としてできること
田中 これまで2回にわたってお話を伺ってまいりました。教育は国の要ですから、よりよい教育を実施したいと思いますが、日教組と一体化した民主政権が続く限り、早急な教育改革も期待できません。その中で、私たち子をもつ親ができることとしては、どのようなことがあるでしょうか。
森口 学校で自虐史観のような偏った教育をされる前に、家庭で“ワクチン”を打っておくことです。「先生はこういうことを言うかもしれないけれど、それは一方的な意見であって、世の中にはこういう見方だってあるんだよ」と、先回りして教えておく。
特に、子供の愛国心を育むには、家庭の中で、常々、「日本って凄いね」いう話をする事です。例えば、今、節電で自動販売機を批判する人もいますが、街中に自動販売機が並んでいる国は日本くらいです。なぜ、他の国にはないか。それは、壊されてお金を盗まれるからです。自販機があるのは、日本人の素晴らしさの象徴なんですよ。
田中 日本の偉人の話し、日本の素晴らしい点を耳にしていると、愛国心も自然に芽生えてきますね。
森口 「日本を愛しましょう」と抽象的に言っても、子供は理解できません。身近で具体的な話をする事です。私は子供に対して最大の影響力を持っているのは、教師ではなく、やはり親であると思っています。もちろん、学校が健全な方がよりよく育つわけですから、学校を改善することも大事です。しかし、学校がどんな状況でも、自分の子供をしっかり育てることは不可能ではないと思います。
田中 学校や社会で理不尽なものを見ても、家庭でしっかり教育されていれば、正しい基準で判断する事ができます。家庭での教育が人格形成の要ですね。2回に渡り、貴重なお話をありがとうございました。(了)























 THE FACT
THE FACT
 及川幸久ニコ生
及川幸久ニコ生
 U2
U2
 及川幸久 X
及川幸久 X