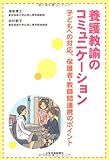「子供をわかるーー「養護教諭とコミュニケーション」より
● 子供は小さな大人ではない
新生児から高齢者までの心の変化を研究する領域を発達心理学という。発達心理学の最大の貢献は、1950年代を境に子供観をがらっと変えたことであろう。
それまでは、「子供は小さな大人」。したがって、大人の心性から子供のそれを見れば、子供は理解できると考えられていた。つまり、子供は未熟な大人として考えられていた。
しかし、偉大な発達心理学者・ピアジェは、乳幼児に固有のさまざまな心性を、巧みな研究手法と壮大な理論に基づいて次々と明らかにしてみせた。これよって、子供には子供なりの世界があること、さらに、子供、とりわけ乳幼児は大人が思っている以上に「賢い」ことが認識されるようになってきた。
● 子供をわかる
「子供は小さな大人でない」とすると、大人である自分のメンタリティを子供に投射して子供を理解することはあまり好ましくないことになる。
たとえば、青年期の子供の理解。大人は薄々でも自分の青年期を思い出すことができる。それがかえって、目の前の青年の心を理解する妨げになってしまうことがある。青年の心や行動は時代を映す鏡、というくらいに、時代とともに変わる。20年前の自分からは想像できない世界があると考えたほうが良い。
図には、他者理解の2つの典型的な型を示した。一つは、今述べた投影的理解、つまり、自分がそうだから相手もそうだろう、という理解である。子供を理解するときには、厳しい限界がある。
もうひとつは、共感的理解、つまり、自分(I)を相手のIに移して、相手のIがmeを理解するように理解する。これができないと、とりわけ子供の心の世界の理解は難しい。このモデルを提案している丹野義彦氏は、共感的理解を「相手の内側から内側をみる」と述べている。至言である。
では、子供を共感的に理解するには、具体的にはどうしたら良いのであろうか。
●子供の心の世界についての知識を豊富にする
発達心理学は、半世紀以上にわたり、子供の心の世界についての膨大な知見を蓄積してきている。
たとえば、以下のような知見を知っている人と知らない人とでは、子供の共感的理解の質が違うはずである。
一つは、子供はいつ頃から心があることを知るかという問題である。これが意外と早く、3歳後半から4歳頃にかけてらしい。
さらに、中学生頃の思春期心性。自己への関心が強くなり自分が何者なのかを知りたくなる。しかし、それがわからないための心理的混乱が激しくなる時期である。
ちなみに、いずれも、発達途上でみられる反抗期に対応しているのがおもしろい。
もちろん、子供の共感的理解には知識だけでは充分ではないが、理解のベースとしては不可欠である。こうした知識があった上で、さらに、次の2つ。カウンセリングの心がまえと技法とを心得ておくことが共感的理解をより良質にする。
●受容する
「相手を知りたければ、知りたいことを尋ねればよい。それだけのこと、何も難しいことはない」。こんな考えの人々は意外と多い。
表面的な他者理解なら、確かにこれで事たれりであるが、相手の心の世界を深く知りたければ、こんな考えではどうにもならない。
共感的な理解には、まずは、相手をその自然なままに受け入れる姿勢が必要である。泣いているのを黙らせるのではなく、まずは、ともに泣くくらいの気持ちになれることである。
かといって、実際に泣いてしまっては共感的理解はおぼつかない。頭のどこかで自分、相手、そして状況全体を俯瞰しているもう一人の自分(ホムンクルス;第4回で取り上げる)がしっかりと見張っている感覚がなければならない。
具体的には、受容とは、次のような言動がとれることである。
・ 泣いていたら、泣いていることを受け入れる
・ 「どうしたの」といったような説明を性急に求めない
・ 相手が話し出すまで待つ
・ 時間にとらわれないゆったり感を出す
● 傾聴する
そして、話ができるようになったら、カウンセリング技法のひとつである傾聴を心がける。
傾聴は、英語では、皮肉なことに、「active 」listeningになる。日本語のイメージとは違って、
積極的に聴くのである。
質問したり、説明したり、批判したり、忠告は厳禁。あくまで、相手の言い分を存分に引き出すことがねらいである。
・相手が話すまで待つこと
・相手の言い分を確認、反復すること
傾聴することによって、相手は自分が受け入れられているという気持ちになれるので、それだけでストレスや悩みの解消の効果があるし、相手の本音を知ることもできる。保健室の現場での共感的理解を深めるためのコミュニケーションの要素技術としても活かせる