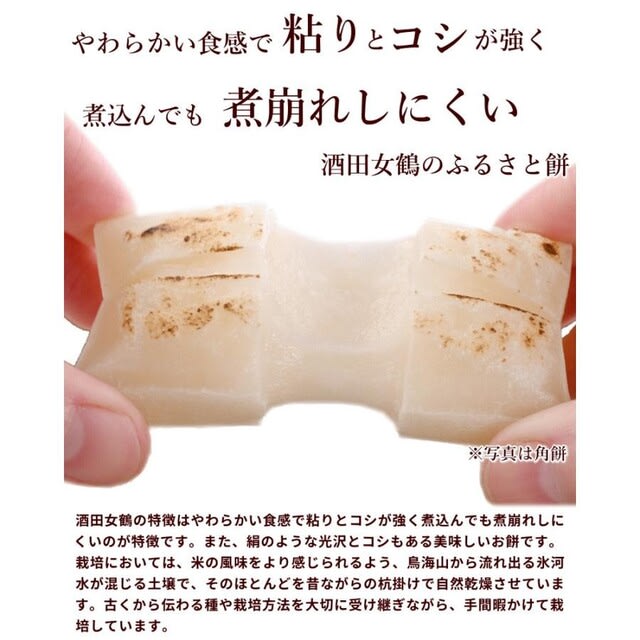第34回「目覚め」はこちら。
この三連休も、寺や畑の草刈り。朦朧となる。少しずつ、涼しくはなっているのだけれど、よくぞこんなに汗がかけるものだと我ながらあきれる。
そして部屋にもどってエアコンをガンガンに効かせ、それでも足りずに扇風機も「強」にして身体に当てる。ほんとに不健康で不経済な生活。
さて大河。今回はついに一条天皇(塩野瑛久)と彰子(見上愛)が結ばれる展開。
まさにこの回に向けたように、脚本の大石静さんが文春オンラインにおける有働由美子アナとの対談でかましまくっている。
「欲しい男は必ず押し倒していました。好きな人には『好きです』と打って出る。男の人って気が弱いから、必ず『そんなに僕を好きなら付き合って見ましょうか』ってなりました、昔は」
おおおすごいな。亡くなった旦那さんとはお互いに嫉妬しない関係で、どちらもよろしくやっていたとか。平安時代の男女関係もびっくり。まるで宍戸錠が奥さんと「嫉妬するのも嫌だろうし、お前も他の男とやっていいから」と協定を結んだのに似ているかも。違うかも。
だから彰子が涙ながらに「お上、お慕いしております」というどストレートな告白をし、一条天皇がついに陥落するあたりの展開に似ているかも。やっぱり違うかも。
そして大石脚本のおみごとなところは、紫式部(吉高由里子)が道長(柄本佑)に向かって源氏物語について
「わが身に起きたことにございます。わが身に起きたことは全て物語の種にございますれば」
「物語になってしまえば、わが身に起きたことなど霧のかなた」
は紫式部に仮託した脚本家としての強烈なマニフェストかな。名セリフですよね。