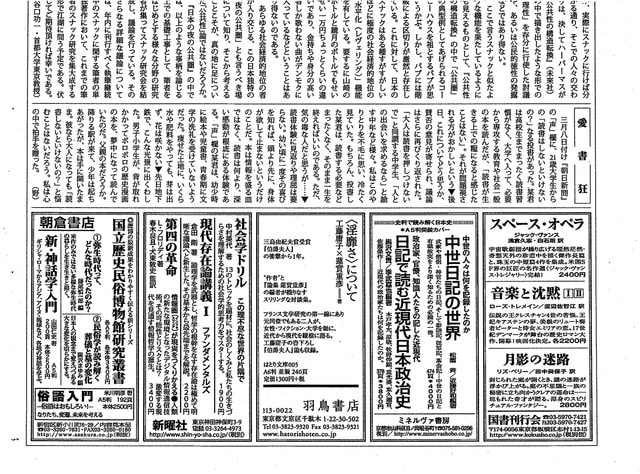2017年9月13日(水)
いえ、朝からお酒が飲みたいという意味ではなくて。
***
歸去來辭 陶潜
歸去來兮
田園將蕪胡不歸
既自以心爲形役
奚惆悵而獨悲
悟已往之不諫
知來者之可追
實迷途其未遠
覺今是而昨非
舟遙遙以輕颺
風飄飄而吹衣
問征夫以前路
恨晨光之熹微
乃瞻衡宇
載欣載奔
僮僕歡迎
稚子候門
三逕就荒
松菊猶存
攜幼入室
有酒盈樽
引壺觴以自酌
眄庭柯以怡顏
倚南窗以寄傲
審容膝之易安
園日渉以成趣
門雖設而常關
策扶老以流憩
時矯首而游觀
雲無心以出岫
鳥倦飛而知還
景翳翳以將入
撫孤松而盤桓
*****
さあ帰ろう、田園が荒れようとしている、いままで生活のために心を犠牲にしてきたが、もうくよくよと悲しんでいる場合ではない、今までは間違っていたのだ、これからは自分のために未来を生きよう、道に迷ってもそう遠くは離れていない、
船はゆらゆらとして軽く、風はひょうひょうと衣を吹く、船頭にこれからの行き先を問い、朝の光のおぼろげなのを恨む
やっと我が家が見えたので、小走りに向かっていくと、召使いたちが出迎え、幼い子が門で待っている、三本の小道は荒れてしまったが、松菊はまだ元気だ、
***
幼子を抱きかかえて部屋に入れば、酒の用意ができている、壺觴を引き寄せて手酌し、庭を眺めては顔をほころばす、南の窓に寄りかかって楽しい気分を満喫し、狭いながらも居心地の良さを感じる
庭は日ごとに趣を増し、門は常に閉ざしたままだ、杖をついて散歩し、時に首をもたげてあたりを眺める、雲は無心に山裾からわき上がり、鳥はねぐらに帰ろうとする、日は次第に暗くなってきたが、一本松をなでつつ去りがたい気持ちになる
***
さあ帰ろう、世間との交際をやめよう、自分と世間とは相容れない、なんで再び官吏の生活に戻ることを考えようか。
親戚のうわさ話を喜んで聞き、琴書を楽しんで屈託がない、農夫が春の来たことを告げ、西の畑で農作業を始めた、車に乗ったり、船を操ったりして、深々とした谷を訪ねたり、険しい丘に登ったりする、木々は生い茂り。泉はほとばしる、万物が時を得て栄える中、私は自分の人生が終わりに近づいていくのを感ずるのだ。
***
致し方のないことだ、人間はいつまでも生きていられるわけではない、どうして心を成り行きに任せないのだ、また何故あたふたとして、どこへ行こうというのだ、
富貴は自分の望むところではない、かといって仙人になれるわけでもない、よい日を選んで散歩し、杖をたてて草刈りをしたり、土を盛ったりする、
また東の丘に登っては静かにうそぶき、清流に臨んでは詩を賦す、願わくはこのまま自然の変化に乗じて死んでいきたい、天命を甘受して楽しむのであれば、何のためらいがあろうものか
(http://tao.hix05.com/102kaerinan.html より拝借)
Ω










 Umberto Eco, 1932-2016
Umberto Eco, 1932-2016