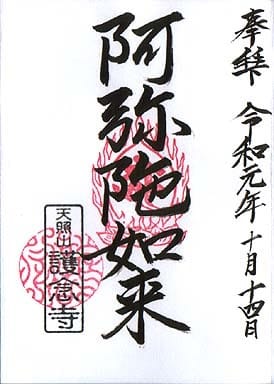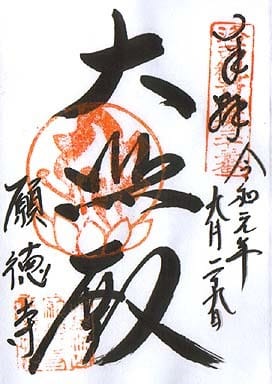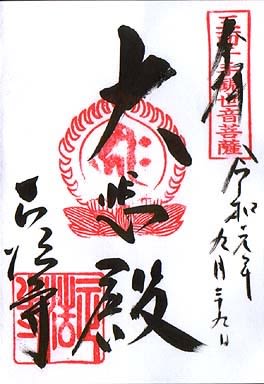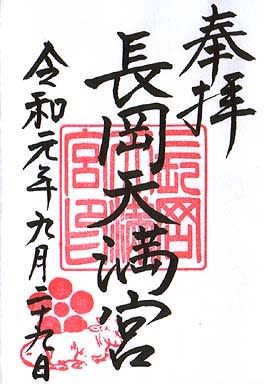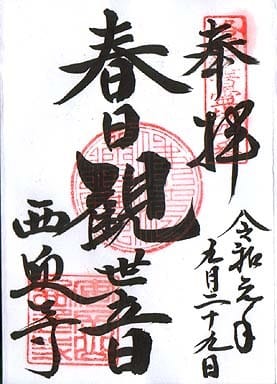本年も沖縄に移動運用に行ってきますのでご案内させて頂きます。
この日程は現時点での予告であり変更される場合があります。出発前に改めて最終のご案内をさせていただきます。
(1)宮古島市[池間島]移動(JCC:4714 JIA:47-104)
日時:11/8(金)15:00~17:45頃
場所:池間島からQRVの予定です。
バンド:7/18/21MHz帯(SSB)
(2)宮古島市[伊良部島]移動(JCC:4714 JIA:47-135)
日時:11/9(土)09:30~11:30頃
場所:伊良部島からQRVの予定です。
バンド:7/18/21MHz帯(SSB)
(3)島尻郡座間味村[座間味島]移動(JCG:47002 JIA:47-124)
日時:11/10(日)10:30~15:30頃
場所:座間味島からQRVの予定です。
バンド:7/18/21MHz帯(SSB)
(4)うるま市[浜比嘉島]移動(JCC:4713 JIA:47-115)
日時:11/11(月)10:00~12:00頃
場所:浜比嘉島からQRVの予定です。
バンド:7/18/21MHz帯(SSB)
(5)豊見城市[瀬長島]移動(JCC:4712 JIA:47-119)
日時:11/12(火)09:00~11:00頃
場所:瀬長島からQRVの予定です。
バンド:18/21MHz帯(SSB)
[※お願い事項]
・移動運用の詳細についてはこちら、QSLについてはこちらをご覧下さい。
荷物の関係でCWの運用はありません。
・船や飛行機の欠航等により渡島できない場合や荒天の場合は中止もしくは
スケジュールを変更することがあります。あらかじめご了承下さい。
逆に時間ができた場合にはスケジュール外でQRVすることもあります。
・現地からのご連絡はTwitterで行います。Twitterは[@JF4CAD4]です。
2016年12月よりIDを変更しておりますのでご注意ください。
・もしご連絡/ご要望等ございましたらこの記事の「コメント」でお願いします。
↓にある「コメント」をクリックして頂きますと書き込めるようになります。
この日程は現時点での予告であり変更される場合があります。出発前に改めて最終のご案内をさせていただきます。
(1)宮古島市[池間島]移動(JCC:4714 JIA:47-104)
日時:11/8(金)15:00~17:45頃
場所:池間島からQRVの予定です。
バンド:7/18/21MHz帯(SSB)
(2)宮古島市[伊良部島]移動(JCC:4714 JIA:47-135)
日時:11/9(土)09:30~11:30頃
場所:伊良部島からQRVの予定です。
バンド:7/18/21MHz帯(SSB)
(3)島尻郡座間味村[座間味島]移動(JCG:47002 JIA:47-124)
日時:11/10(日)10:30~15:30頃
場所:座間味島からQRVの予定です。
バンド:7/18/21MHz帯(SSB)
(4)うるま市[浜比嘉島]移動(JCC:4713 JIA:47-115)
日時:11/11(月)10:00~12:00頃
場所:浜比嘉島からQRVの予定です。
バンド:7/18/21MHz帯(SSB)
(5)豊見城市[瀬長島]移動(JCC:4712 JIA:47-119)
日時:11/12(火)09:00~11:00頃
場所:瀬長島からQRVの予定です。
バンド:18/21MHz帯(SSB)
[※お願い事項]
・移動運用の詳細についてはこちら、QSLについてはこちらをご覧下さい。
荷物の関係でCWの運用はありません。
・船や飛行機の欠航等により渡島できない場合や荒天の場合は中止もしくは
スケジュールを変更することがあります。あらかじめご了承下さい。
逆に時間ができた場合にはスケジュール外でQRVすることもあります。
・現地からのご連絡はTwitterで行います。Twitterは[@JF4CAD4]です。
2016年12月よりIDを変更しておりますのでご注意ください。
・もしご連絡/ご要望等ございましたらこの記事の「コメント」でお願いします。
↓にある「コメント」をクリックして頂きますと書き込めるようになります。