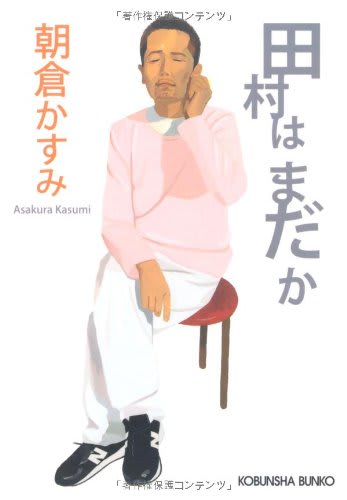
本のサイト「シミルボン」に、以下のコラムを寄稿しました。
https://shimirubon.jp/columns/1677278
“朝倉かすみワールド”へ、ようこそ!
「朝倉かすみ」という作家の名前を知ったのは、2003年のことだ。もう14年も前になる。
その前年に、北海道にある大学に単身赴任していた。住民票も移して、ちゃんと県民ならぬ北海道民となった。クルマも冬対策で4WDにしたし、新聞も多くの北海道民と同じく、宅配で「道新(北海道新聞)」を取るようになった。
そして2003年、道新で「朝倉かすみ」の名を目にする。小説「コマドリさんのこと」で、第37回「北海道新聞文学賞」を受賞したというのだ。小樽市の女性らしかった。
その「コマドリさんのこと」をちゃんと読めたのは、2005年11月。第72回「小説現代新人賞」を受賞した表題作を含む初作品集『肝、焼ける』(講談社)だ。
表題作の主人公「わたし」は、年下の男と遠距離恋愛中の独身女性31歳。相手の自分への気持ちがつかめない。そんな「肝、焼ける(じれったい)」状態から脱したくなって、男が住む北の町へとやってきた。
会うまでの微妙な時間を過ごす銭湯や寿司屋。これまでの仕事や恋愛の回想が、ほろ苦くも愛しい。そして、ついに男と向き合う瞬間が近づいてくる。
朝倉さんの文体の特長は、短いセンテンスの連打にある。観察と表現に齟齬と遅延がなく、リズムが心地よい。また、ヒロインの眼から見た若い男女、中高年の男女がリアルでユーモラスだ。そして、全作品に共通するのは、30代女性の日常と本音をすくい上げる力の確かさである。新人とはいえ、すでに自分の「ポジション」を持っているのだ。
他には、小さな田舎町の小さな事務所で働く独身女性の心の軌跡を優しく描いた「コマドリさんのこと」(北海道新聞文学賞受賞作)。同僚である40代独身女性たちの恋や不倫を眺めながら、自身も揺れている若い女性がヒロインとなる「一番下の妹」など、いずれも30代女性の“普通の生活”が非凡に描かれている。
「コマドリさんのこと」もよかったが、「肝、焼ける」は、さらに上手い!と思った。新人とは思えないほど、独自の小説世界を巧みに構築していた。こういう嬉しい”出会い”があるから、「本読み屋」はやめられないのだ。
次々と出てくる新刊を読んでいると、ついこの間読んだ本のことさえ忘れてしまいそうになる。『田村はまだか』(光文社)は、2008年の2月に出た本。ちょうど、6年におよんだ北海道の大学への単身赴任が終りを迎え、東京の大学に移る直前だった。ずいぶん懐かしい。
でも、この小説のことは、よく覚えている。とてもよかったからだ。読了後、家族にも薦めたので全員が回し読みしている。実は、朝倉さんの小説の中で、今でも一番好きなのは、この『田村はまだか』である。
深夜、路地の奥にある小さなスナックに5人の男女が集まっている。小学校の同級生で、皆40歳。クラス会の3次会だった。そして彼らは田村を待っている。店に向かっているはずだが、現れない。ふと誰かが口にする。「田村はまだか」・・・。
田村は小学校時代から不思議な男だった。父親はいない。男出入りの激しい母親との二人暮らし。年中ジャージを着て、頭は虎刈り。だが、勉強はできたし走るのも速い。とはいえ、田村が皆から一目置かれていたのは、一人だけどこか大人の風格があったからだ。「孤高の小6」だった。
実に巧妙な小説である。そこにいない田村のことを各人が想い、同時に「忘れられない人」「自分に影響を与えた人」のことを振り返る。それは会社の先輩だったり、年下の“恋人”だったりする。共通するのは「その人がいなければ今の自分はない」と思えるような人物であることだ。深夜のスナック、昨日と今日の境目で、彼らの過去と現在とが交錯していく。それにしても、田村は一体どうしたのか・・・。
朝倉さんの作品の特徴である小気味いい短文の連なりと、深い情感をさりげない言葉に託す表現に、益々磨きがかかっている。
『田村はまだか』で吉川英治文学新人賞を受賞した後に出た、朝倉さんの長編小説が『感応連鎖』(講談社)だ。例によって、男からはうかがい知れない、女たちの内なる葛藤のドラマが描かれている。
登場するのは4人の女性だ。節子は子ども時代からの肥満体。顔も大きい。周囲に自分を「異形」と認識させることで、いじめから逃れてきた。絵理香は他人の気持ちを読み、操るのが得意。美少女の由季子は、その外見ゆえに自意識過剰気味だった。そして4人目が彼女たちの担任教師・秋澤の妻である。
ごく普通の男であるはずの秋澤を触媒に4人の女たちの心が化学反応を起こす。一人の行動が、玉突きのように他者へと影響を与えていくのだ。感応連鎖である。
自らの人生における主人公は自分だ。そんなヒロイン同士は、互いの眼にどう映っているのか。どう思われているのか。何気ない日常が女たちの戦場と化すのだ。
そして、なんとも不思議な味わいの長編小説が、『幸福な日々があります』(集英社)。ここにはヒロインである「わたし」が2人いる。結婚したばかりの幸福な時代の「わたし」と、夫と別れようとしている10年後の「わたし」が交互に登場するのだ。
森子は46歳の専業主婦。3つ年上の夫は大学教授だ。見た目も穏やかな性格も、森子を大事にする気持ちにも文句はないはずだった。しかし、森子は突然宣言してしまう。親友としてはすごく好きだが、「夫としてはたぶんもう好きじゃないんだよね」と。離婚に応じようとしない夫を家に残し、ひとり暮しを始める。
10年前に結婚した時も言いだしたのは森子のほうだ。どこか安心したかったからだが、望み通りの生活に入ってからも時々心が揺れた。たとえば夫は何でも習慣化する。森子は単純作業は好きだが習慣は苦手だ。「しなければならない」という雰囲気、ルールめいた感じが窮屈なのだ。他人には贅沢と思われそうだが、森子は誰にも言わなかった。
物語は10年を行ったり来たりしながら、ゆっくりと進んでいく。連載時のタイトルは「十年日記」であり、心の動きがまさしく詳細に書き込まれている。人はなぜ人を好きになり、なぜそうではなくなっていくのか。夫婦の深層にじわりと迫っていく。
最後に、『ぜんぜんたいへんじゃないです。』(朝日新聞出版)は、朝倉さんの初エッセイ集。当時50歳だった“新人”作家の日常は、恋愛や冒険や蘊蓄に溢れているわけではない。それなのに、独自の“おかしみ”につい引き込まれてしまう。中でも母親をめぐる「京子レジェンド」は必読です。















