昨日2月6日、自然博物園ねいの里で生き物セミナーがありました。
野生鳥獣による農林業への被害が県内でも問題となっており、特にサルやイノシシ等の獣類による被害が多い。そのため、それらの生態や体の構造について学び、どのように付き合っていけばよいか考えるものです。

ツキノワグマ

鳥獣保護のお仕事をされていらっしゃる間宮先生から、展示のクマ、イノシシ、シカなどのはく製を使って、体の仕組みや生態についてお話をお聞きました。

シカ 矢印の所が、「足のかかと」です。動物はつま先で歩いているのですね。

この後、生のシカとイノシシを解剖して、歯や骨、内臓、肉などから、体の仕組みを勉強しました。ねいの里では、ジュニアナチュラリストの養成を行っておられるので、ジュニアナチュラリストの学習目的も兼ねて行われました。農作物に害を及ぼすシカやイノシシは、今まで狩猟することで数が調整されていましたが、狩猟をする人は年々少なくなり、増加の傾向にあります。解剖はめったにない機会なので、怖いもの見たさで見せてもらいました。
矢印の所が、膝です。 外見では見えなかったけど、モモの下にちゃんと付いてたのですね。


内臓は、ちょっとリアルすぎてお見せ出来ませんが、シカの胃は、牛と同じで4個あります。一度食べたものを、口に戻してすり潰し、3番4番の胃へと送られて行くうちに、消化してして行くのがよく分かりました。

肉は、背中の部分の背ロースが柔らかくて美味しく、モモの辺りに多い肉は脂肪が少ないので固いそうです。この後、内臓は研究機関へ提供され、肉は食用に、他すべてが有効利用されるとのことです。
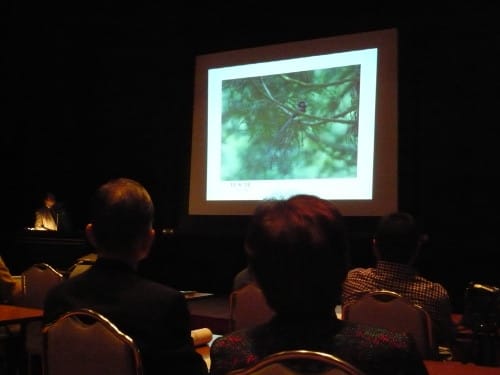
午後から高志会館で、日鳥連富山県支部の新年交歓会が行われました。前半の特別公演では県自然保護課中田氏より「この冬の鳥インフルエンザについて」、湯浅支部長の「サンコウチョウの繁殖生態」繁殖の素晴らしい写真、村本義雄氏の「思い出に残るトキの姿」と、興味深いお話をお聞きしました。その後、会員のショートレポート、ハクチョウやアサギマダラの調査報告などがあり、後半の交流懇親会では、ロシアの国際交流員の方や石川県支部の来賓の方との交流も始終和やかな雰囲気でした。
![]()
にほんブログ村
野鳥ランキング
















