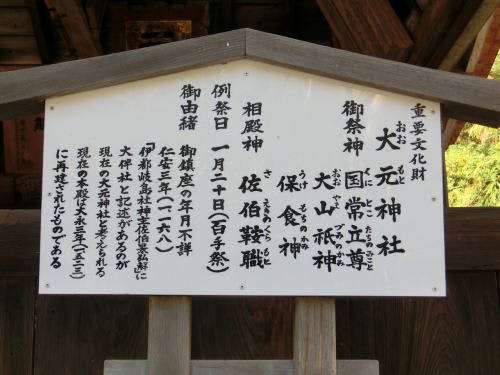西洋医学の父 「 伊東玄朴旧宅 」





佐賀県神崎市仁比山の九年庵に向って行くと右手前に伊東玄朴旧宅がある。
伊 東 玄 朴(執行勘造・しぎょう かんぞう)
寛政12年(1800)~明治4年(1871) 肥前国神崎郡仁比山村の農民、執行重助の子、
幼名勘造・諱淵・字伯寿,号沖斎・長翁など。
隣村の医者古川左庵から漢方医学を学び、父親の死後自宅で開業していたが、
蘭方医学を志し、文政5年(1822) 佐賀城下の蘭医島本龍嘯に学ぶ。
島本の紹介により長崎で通詞猪俣伝右衛門にオランダ語を学び、
シーボルトから医学を学んだ。
文久9年(1826)玄朴はオランダ商館長の一行に従って江戸へ出た。
一年後長崎に戻るとき、幕府天文台長兼図書館長の高橋作右衛門から
シーボルトへの贈り物の日本地図を、猪俣伝右衛門の子の源三郎から託される。
その後、シーボルトがオランダに向けて乗り込む船が台風で座礁し、
その船から幕府が国外へ持ち出しを禁じていた日本地図が出てきたために
関係者は捕らえられ、高橋作右衛門は牢獄で拷問死、猪俣源三郎は獄中で自害した。
伊東玄朴は偶然熊本に出かけていて捕らえられずにすんだ。
勘造の知識と能力を重視した佐賀藩の配慮により鍋島直正家臣伊東玄朴として自首し、
荷物を預かっただけで中身は知らないと主張して罪を免れた。
これ以後、勘造は伊東玄朴と名乗る。
天保4 年 (1833) 34歳のとき、下谷和泉橋通御徒町に転居して蘭学塾象先堂を開く。
天保14年(1843)、鍋島家の匙医となり牛痘の取り寄せを藩主に建言、
嘉永2年(1849)にバタビアから牛痘種がもたらされると種痘の普及に一役かった。
安政5年(1858)、神田お玉ケ池の種痘館設立を主導、
同年幕府奥医師となり蘭方医の勢力拡張に功があった。
門人は403人を数え全国に及んだ。