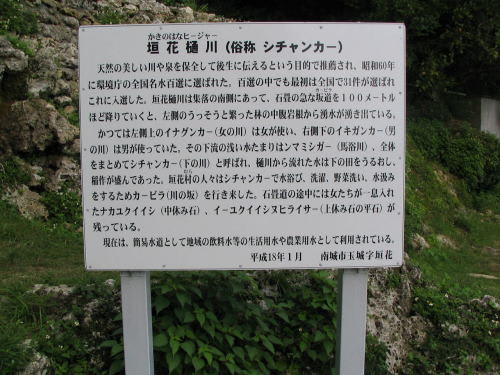国東の帰りにシャトレーゼに寄って、
堀倫さんのブログで見た 「 自慢のりんごパイ 」 を買おうと入って行ったが、
売っていなかったので 「 夢うさぎ 」 にそのまま直行した。
その 「 りんごパイ 」 の代役というか、
ここで主役をつとめたのが、
夢うさぎの 「 ロールケーキとシュークリーム 」 である。
今回は 「 花福 」 の前を通って行ったので分かりにくかったけど、
福沢通りに出ればこっちのものである。
いつもながらシュークリームも美味しかったけど、
ちょっぴり黒糖がきいたチョコロールも良かったな。