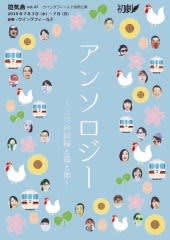
思いもしなかった(失礼!)面白さで、衝撃を受ける。久々に見た遊気舎の芝居、ということよりも、久保田浩という作家発見の興奮のほうが大きい。彼の力量に圧倒される。こんなすごい作家が関西にはいたのか、と改めて驚く。というか、役者としての彼ならずっと前から知っているし、古い話で恐縮だが、後藤ひろひとが遊気舎を抜けたとき、絶対に彼が作、演出を担うべきだと思った。だけど、なかなかそういうことにはならなかったし、そのうち、僕は遊気舎を見ることがなくなっていた。
そして、今回、たまたまウイングで上演されたから見たのだが、今日まで待ってよかったと思う。円熟した台本、演出はベテランだからこそ可能だった。気負いのなさ、と余裕。それがこの作品の魅力を担う。どこにも無理がない。短編3本からなる80分の作品である。別々の方向性を持つ独立した3作品は、同じテイストで貫かれている。静かに3本が流れるように綴られていく。舞台転換のロスタイムもなく暗転のみで次のエピソードにつながるスマートさもいい。
終わった後、ため息がでる。こんなにも見事にそれぞれの短編が完結しているにもかかわらず、1本の芝居としてきれいに収まる。よくわからないざわざわした感触を残す。それは最初のお通夜の話から最後まで、貫かれてある。ホラータッチの作品には隠し味として『キャリー』、ジェイソン(『13日の金曜日』ね)を経て、『シャイニング』の双子のような2人の女たちのお話へと、続く。特に3本目が怖い。たぶん昼間の朝霧から新長田までの電車の中での話なのに、これが一番短くて怖い。
最初のオープニングの気味の悪い手の動きから始まり、最後まで、理屈ではなく、ただわけのわからないざわざわしたものが心に残る。その気味の悪さは、なんなんだろうか。ホラータッチと書いたが、怖がらせる気はない。でもコミカルに見せるわけでは断じてない。ちょっとした不条理にすらならないギリギリのところで、とどまる。それを久保田さんは気負いなく自然体で見せる。こけおどしはない。むしろこれは淡々としたタッチだ。でも、意味の分からない恐怖がそこにはある。
2話目の中年に達した男女がセーラー服、学ランを着てキャンプをする話はふつうならコメディになる。ここには、深夜に怖い話をする、なんていう中学時代のキャンプを再現しながら、過ごす時間が描かれる。1話目の祖父の通夜の晩、久々に家族4人が揃う、というお話もそうだ。どこにでもありそうな設定で、日常のちょっとしたお話を切り取っただけ、のように見せかけて、そこに得体のしれないものを見せていく。どこにもない「何か」がここにはある。傑作である。

























