一昨日と昨日,立川市で指された第72期王将戦七番勝負第四局。
羽生善治九段の先手で角換わり相腰掛銀。玉の形に新しい工夫を凝らした先手から仕掛け,駒損の攻めを敢行しました。なので焦点は先手が攻め切るか,後手の藤井聡太王将が受け切るかという一点に。
大きな分岐となったのは封じ手で,ここは玉で取る手と銀で取る手のふたつがあり,実戦は玉で取ったことによりAIの評価値は大幅に下がりました。
この将棋を後手が勝つパターンは,受け切るかさもなければどこかでカウンターの反撃を決めるかです。このとき,Aという手は評価値は下がらないけれども先手の攻めは長く続き,Bという手は評価値は下がるのだけれどももしも先手が攻め続けるには怯むところがあってはならないとすれば,人間と人間が戦う場合にはBの方が後手が勝つ可能性が高いという場合があります。なので後手が玉で取る方の手を選んだことに理由がないわけではないように思います。
実戦は先手が怯まずに攻めを継続していったので,後手が銀をただで取らせるような受けをしなければならなくなり,先手は駒損を回復することができたので局面がはっきりしました。先手としても攻め続けるほかなかったので仕方がなかったという面もあるでしょうが,怯まずに攻め続けたことで先手が勝利を引き寄せた一局だったと思います。
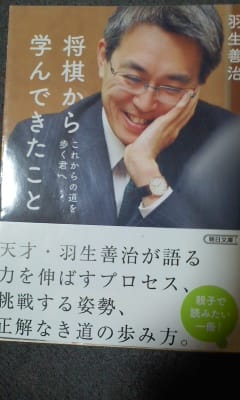
羽生九段が勝って2勝2敗。第五局は25日と26日に指される予定です。
人の噂も75日という諺があります。この諺なども,第五部定理四二備考でスピノザが無知者について語っている部分を利用して説明することができるでしょう。すなわち他人の噂をするような人間は無知者なのであって,75日も経てばその噂は消えてしまう,つまり噂をするような無知者は無知者として存在することをやめるようになるという観点です。そしてなぜ存在することをやめるようになるのかといえば,それは噂の対象となっている人の表象像imagoという点からみれば,第二部定理一七の様式で,その人の表象像から別の表象像へと移行するからです。またそうした噂をすることへの欲望cupiditasという点からすれば,第四部定理七の様式で,より強力な感情affectuによってその欲望が排除されるからです。備考Scholiumの中でいわれているように,無知者というのは外部の原因causaから様ざまな仕方で揺り動かされているのですから,そうした人の表象像も受動的な感情も,排除されやすいものだといえるでしょう。つまり,他人の噂をするような人間は,ある人の噂から別の人の噂へ,またさらに別の噂へと移ろいやすいものなのです。ですから人の噂も75日という諺は,スピノザの哲学から照らし合わせてみて,ある真実をいっているといってよいでしょう。
この諺がどういう経緯でいつごろから広く使われるようになったのかということは僕は分かりません。ただ,この諺が広まった時代と比べれば,現代は情報の量というものが格段に増えていることは間違いないと思います。情報の量が増えているというのは,他人の噂をするような無知者の精神mensを揺り動かすような外部の原因が大幅に増加しているという意味です。ですから現代では75日も継続するならそれはよほど強力な噂であるといえるかもしれません。むしろもっと短い周期で,無知者はあるある噂から次の噂へ,そしてまた別の噂へと移っていくものなのであって,それだけ頻繁に存在することをやめては別のところに存在するようになるということを繰り返していくことになるといえそうです。
これで『はじめてのスピノザ』の第一章の無知者に関連する考察は終了します。次に同じ章の中の,汎神論に関連する部分を考察します。
羽生善治九段の先手で角換わり相腰掛銀。玉の形に新しい工夫を凝らした先手から仕掛け,駒損の攻めを敢行しました。なので焦点は先手が攻め切るか,後手の藤井聡太王将が受け切るかという一点に。
大きな分岐となったのは封じ手で,ここは玉で取る手と銀で取る手のふたつがあり,実戦は玉で取ったことによりAIの評価値は大幅に下がりました。
この将棋を後手が勝つパターンは,受け切るかさもなければどこかでカウンターの反撃を決めるかです。このとき,Aという手は評価値は下がらないけれども先手の攻めは長く続き,Bという手は評価値は下がるのだけれどももしも先手が攻め続けるには怯むところがあってはならないとすれば,人間と人間が戦う場合にはBの方が後手が勝つ可能性が高いという場合があります。なので後手が玉で取る方の手を選んだことに理由がないわけではないように思います。
実戦は先手が怯まずに攻めを継続していったので,後手が銀をただで取らせるような受けをしなければならなくなり,先手は駒損を回復することができたので局面がはっきりしました。先手としても攻め続けるほかなかったので仕方がなかったという面もあるでしょうが,怯まずに攻め続けたことで先手が勝利を引き寄せた一局だったと思います。
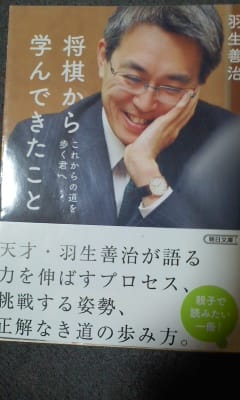
羽生九段が勝って2勝2敗。第五局は25日と26日に指される予定です。
人の噂も75日という諺があります。この諺なども,第五部定理四二備考でスピノザが無知者について語っている部分を利用して説明することができるでしょう。すなわち他人の噂をするような人間は無知者なのであって,75日も経てばその噂は消えてしまう,つまり噂をするような無知者は無知者として存在することをやめるようになるという観点です。そしてなぜ存在することをやめるようになるのかといえば,それは噂の対象となっている人の表象像imagoという点からみれば,第二部定理一七の様式で,その人の表象像から別の表象像へと移行するからです。またそうした噂をすることへの欲望cupiditasという点からすれば,第四部定理七の様式で,より強力な感情affectuによってその欲望が排除されるからです。備考Scholiumの中でいわれているように,無知者というのは外部の原因causaから様ざまな仕方で揺り動かされているのですから,そうした人の表象像も受動的な感情も,排除されやすいものだといえるでしょう。つまり,他人の噂をするような人間は,ある人の噂から別の人の噂へ,またさらに別の噂へと移ろいやすいものなのです。ですから人の噂も75日という諺は,スピノザの哲学から照らし合わせてみて,ある真実をいっているといってよいでしょう。
この諺がどういう経緯でいつごろから広く使われるようになったのかということは僕は分かりません。ただ,この諺が広まった時代と比べれば,現代は情報の量というものが格段に増えていることは間違いないと思います。情報の量が増えているというのは,他人の噂をするような無知者の精神mensを揺り動かすような外部の原因が大幅に増加しているという意味です。ですから現代では75日も継続するならそれはよほど強力な噂であるといえるかもしれません。むしろもっと短い周期で,無知者はあるある噂から次の噂へ,そしてまた別の噂へと移っていくものなのであって,それだけ頻繁に存在することをやめては別のところに存在するようになるということを繰り返していくことになるといえそうです。
これで『はじめてのスピノザ』の第一章の無知者に関連する考察は終了します。次に同じ章の中の,汎神論に関連する部分を考察します。















