「それ以上言わないで」はドラマの「親愛なる者へ」で用いられた部分からも分かるように,女が男から別れを告げられる場面が歌になったものです。ただ,歌の主題になっているのは男のセリフの部分なのではなくて,そう言われたときの女の心境です。この歌の魅力はその部分にあって,この女はとても客観的にこの別れを認識している部分もあれば,とても情念的に男に訴えたいという部分もあるのです。そのどちらもリアルであり,だからその対照的なふたつの部分が女のうちで両立しているということもリアルに感じられます。

憎み合っての別れじゃなかったと 明日みんなに言わなきゃね
昔貴方を愛した時も だれかこうして泣いたのかしら
男のセリフから想像できるように,確かにこのふたりは憎み合って別れることになったというのとは違うようです。ただ,女はそのように友人たちに言わなければならないと思い,さらにかつてこの男と付き合うようになったときには,今の自分のようにだれかが泣いたのかもしれない,つまり自分はだれかを泣かせたのかもしれないと想像しています。これは女がこの別れを客観視していることの象徴だといえるのではないでしょうか。
もしも私に勇気があれば ここで貴方を殺したかった
あの娘にあげる心はあげる せめて私に命をほしい
別れを客観視して,どこか心に余裕さえあることを感じさせる女が,同時にこのような怨念ともいうべき強い情念も持ち合わせているのです。そして確かにこのふたつは,女のうちで両立しているのでしょう。同時に,それが両立していたから,これは歌になり得たのだともいえます。どちらかだけだったなら,単なる吐露で,歌としては成立しなかったでしょう。
先生が静の涙を見て悲しみtristitiaを感じ,その後に悲しんでいる自分を表象して「一滴の潤い」すなわち喜びlaetitiaを感じたのは,静の涙を見たときに先生に生じた小なる完全性perfectioへの移行transitioより,悲しんでいる自分を表象したときのより大なり完全性への移行の方が大きかったからです。このゆえに先生の善悪としてみれば,この事態は全体的には善bonumであったのです。しかしもし悲しみによるより小なる完全性への移行の方が大きかったとしたら,先生がたとえ「一滴の潤い」を感じたとしても,全体的には善ではなくて悪malumであったでしょう。
しかし,この場合には全体的には善であったのですから,先生は静の涙を目にすることによって悲しみを感じたのだとしても,それによって泣いている静のことを否定したとはいい得ないことになります。まずこのことから,単にある人間を表象するimaginariことによって悲しみを感じたのだとしても,それだけでその人間を否定しているというわけではない,いい換えればその人間に対して排他的傾向を有しているいうわけではないということが,感情affectusのレベルだけでも理解できます。
ただ,排他的思想といわれるときの思想は意識のレベルのことであり,単純な感情のレベルとは異なっているとみることもできます。そこで今度は先生の意識のレベルも考察してみましょう。ただ,先生が静に対しては排他的感情すら有していないということは明らかで,意識というのは観念の観念idea ideaeですから,もしも無意識的な感情の段階で排他的感情をもっていないのであれば,排他的思想を有するということは不可能です。これはある人間の精神mens humanaのうちにXの観念が存在しないならば,その人間の精神のうちにはXの観念の観念も存在し得ないということから明らかです。第二部定理二一から明らかなように,観念とその観念の観念というのは,合一しているすなわち同一個体であり,同じ秩序ordoで神Deusと関連付けられることになるからです。よって静の場合については考察の対象にすることができません。そこで静が悲しんでいる原因を対象にします。
第三部定理二二は,愛する者を悲しませる原因となっているものを,現実的に存在する人間は否定するといっています。

憎み合っての別れじゃなかったと 明日みんなに言わなきゃね
昔貴方を愛した時も だれかこうして泣いたのかしら
男のセリフから想像できるように,確かにこのふたりは憎み合って別れることになったというのとは違うようです。ただ,女はそのように友人たちに言わなければならないと思い,さらにかつてこの男と付き合うようになったときには,今の自分のようにだれかが泣いたのかもしれない,つまり自分はだれかを泣かせたのかもしれないと想像しています。これは女がこの別れを客観視していることの象徴だといえるのではないでしょうか。
もしも私に勇気があれば ここで貴方を殺したかった
あの娘にあげる心はあげる せめて私に命をほしい
別れを客観視して,どこか心に余裕さえあることを感じさせる女が,同時にこのような怨念ともいうべき強い情念も持ち合わせているのです。そして確かにこのふたつは,女のうちで両立しているのでしょう。同時に,それが両立していたから,これは歌になり得たのだともいえます。どちらかだけだったなら,単なる吐露で,歌としては成立しなかったでしょう。
先生が静の涙を見て悲しみtristitiaを感じ,その後に悲しんでいる自分を表象して「一滴の潤い」すなわち喜びlaetitiaを感じたのは,静の涙を見たときに先生に生じた小なる完全性perfectioへの移行transitioより,悲しんでいる自分を表象したときのより大なり完全性への移行の方が大きかったからです。このゆえに先生の善悪としてみれば,この事態は全体的には善bonumであったのです。しかしもし悲しみによるより小なる完全性への移行の方が大きかったとしたら,先生がたとえ「一滴の潤い」を感じたとしても,全体的には善ではなくて悪malumであったでしょう。
しかし,この場合には全体的には善であったのですから,先生は静の涙を目にすることによって悲しみを感じたのだとしても,それによって泣いている静のことを否定したとはいい得ないことになります。まずこのことから,単にある人間を表象するimaginariことによって悲しみを感じたのだとしても,それだけでその人間を否定しているというわけではない,いい換えればその人間に対して排他的傾向を有しているいうわけではないということが,感情affectusのレベルだけでも理解できます。
ただ,排他的思想といわれるときの思想は意識のレベルのことであり,単純な感情のレベルとは異なっているとみることもできます。そこで今度は先生の意識のレベルも考察してみましょう。ただ,先生が静に対しては排他的感情すら有していないということは明らかで,意識というのは観念の観念idea ideaeですから,もしも無意識的な感情の段階で排他的感情をもっていないのであれば,排他的思想を有するということは不可能です。これはある人間の精神mens humanaのうちにXの観念が存在しないならば,その人間の精神のうちにはXの観念の観念も存在し得ないということから明らかです。第二部定理二一から明らかなように,観念とその観念の観念というのは,合一しているすなわち同一個体であり,同じ秩序ordoで神Deusと関連付けられることになるからです。よって静の場合については考察の対象にすることができません。そこで静が悲しんでいる原因を対象にします。
第三部定理二二は,愛する者を悲しませる原因となっているものを,現実的に存在する人間は否定するといっています。














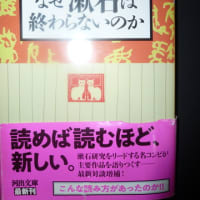







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます