安上がりなところも「極上」と自負しています。植物を
愛で、自給自足のフラワーアレンジ、そして何かを作る、描くなどです。
極上のひとり遊び
「わたしの好きなイタリア」
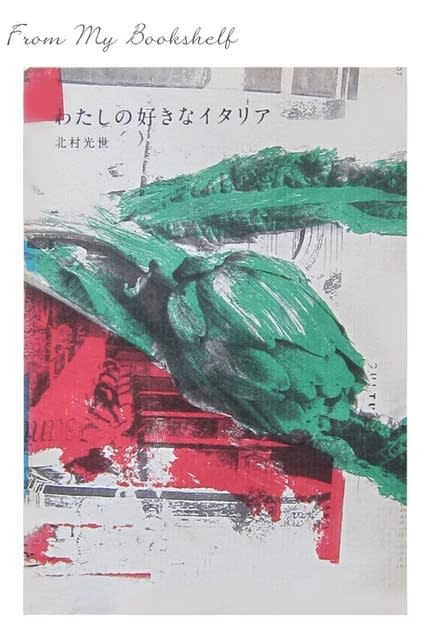
この本を読んで、自分が何故イタリアが好きなのか、
よく分かった気がしています。
著者の北村光世さんは、北イタリアに石のお家を
お持ちになっていて、一年のうち何ヶ月かはそこで過ごされるという、
とっても羨ましい暮らしが記されています。
北村さんは、
「わたしがどんどんイタリアに惹かれていったのは、
イタリアが[自然]をよく理解し、人間は[自然]によって
生かされていることを知っている人たちの国だから」
と仰っています。
この言葉が、とっても腑に落ちました。
私も旅行ではほんの一瞬立ち寄っただけなのですが、食文化や
風景の写真や動画などから、そのようなことをなんとなく
感じていた気がします。
続いて北村さんは、
「もちろんイタリアにもおくればせながら近代化の波はやってきて、
開発で自然が破壊されているところもあります。
でも人々の考えの根底には、私たち人間が生きるために
必要なもの、例えば、衣類や食べ物や家は、すべて
もとはといえば、自然から生まれたものだから、
自然を破壊するのではなく、自然と調和をとりながら
共に生きていかねばならない、という考えが強く存在するのです。
イタリアには、生ハムやチーズなど多くの伝統商品がありますが、
これらの多くは大工場で作られるのではなく、
工房や小さな工場で作られます。
昔ながらの製造法を変えることなく、近代的な科学添加物を
一切加えずに、自然の力で無理に急ぐことなく、
必要な時間をかけて作られているのです。
日本も昔は、このような食品作りをしていたのですが、
経済発展の陰に、この伝統は消えてしまい、代わりに
添加物がたくさん入った便利な食品が生まれました。
イタリアへ行くと、ほっとするのは、食べ物が安心して
食べられるからです。
加工品だけではなく、野菜や果物や肉類なども本来の味を
それぞれ持っているうえに、日本のように、
あちこち探しまわって、やっと質のいい食品が買えるのではなく、
普通のスーパーでも求められるからです。」
とは言え、この書籍は2007年に発行されたものなので、
今現在とは、時代の流れで少し事情が変わっていると思われます。
イタリア産でも添加物を使用しているものを見かけます。
特に加工肉のパンチェッタやグアンチャレなど、
YouTube「イタリアの食卓」のレシピに度々登場するので、
私はお肉はなるべく減らしていますが、たまに使ってみたい気がして
探してみると、イタリア製のものでも、発色剤の亜硝酸Naや
硝酸Kが使われているものがほとんどです。
これらの発色剤は、発がん性や食欲不振、軽度のうつ病などの
原因を疑われています。
無添加のものは、あるにはありますが少ないです。
日本のハムやソーセジ、ベーコンには発色剤以外にも、リン 酸塩、
結着剤、保存料、酸化防止剤、合成着色料、化学調味料などなど、
数えきれないほどの添加物入っているので、それに比べると
圧倒的に少ないですけれど................。
パスタやお菓子類などは、まさかアメリカやカナダの危険な小麦粉を
輸入して作っているとは考えにくいので、オーガニックでなくても
買ったりします。
ここに来て様々な国が、コロナの規制緩和に向かっている中、
「イタリアの食卓」の最新の動画によると、
緩和は進まず、倒産が相次ぎ経済がめちゃめちゃになっているとの事。
イタリアの食を守って来た小さな工場や工房などは、
大丈夫かしら........と、とても気になっています。
動画はこちら。
素晴らしい食文化が守られることを心から願います。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 雑草流フラワ... | 雑草のドライ... » |





