今回も昔のTMSの話です。

昭和39年から42年頃にかけてTMS誌上の特徴のひとつとして「博物館のレイアウトを積極的に紹介していた」事が挙げられます。
今回入手したバックナンバーでは交通科学館・科学技術館・名古屋市立博物館などのレイアウトのグラフがそれぞれ数ページにわたって紹介されていました。
興味深いのはその時期の読者の投書欄に「○○のレイアウトが紹介されていないけれど予定はありますか」という質問に対し「本誌では取り上げるに値する物しか取り上げません」といった意味の回答をしていた事です。
してみると当時は他にもエリミネートが必要なくらいに展示用レイアウトがいっぱいあったという事でしょうか。

16番ですら十分なレイアウト用品のなかったこの時期にこれだけの規模のレイアウトを作り展示していたという事は凄い事だったと思います。
そしてそれらは単なる展示品の域を超えて当時のファンへレイアウトへの夢をかきたてていたのではないでしょうか。
ただ、これらの記事を読んで感心すると同時に気になった事もありました。
それは最近の博物館のレイアウトはコンセプトの面でこの当時から一歩も進歩していないのではないかという懸念です。
確かに広大なスペースに線路が縦横無尽に張り巡らされてはいます。しかし駅はあっても駅前広場がなく周囲の風景に人間の匂いがまるで感じられない。
ただうつろなだけの空間。
そこを走る列車も単なる抜け殻にしか見えない事があります。
これが個人やクラブの所有、或いはレンタルレイアウトならば笑って済みます。
いや、ユーザーの思い入れがストレートに伝わる分だけ単なるギャラリーの立場としてもはるかに楽しめます。
しかし博物館の展示品がそれで良いのでしょうか。
列車といえども世間とは無縁に存在できず「周囲の自然・社会環境との繋がりの中走らせてで初めて列車にも命が吹き込まれる」事を認識できていないのではないかとすら思える事があります。

TrackAheadなどの海外番組で見せてもらった博物館のレイアウトでは「地域の産業・人流・物流の流れといった社会システムをシーナリィとして再現し、その中で列車を走らせる事で鉄道の役割を視覚的に認識させる」事を何より重視した設計がなされています。その点で例えばシカゴの博物館のレイアウトなどは個人的に理想のレイアウトのひとつと見えました。
私の知る限りでそこを外さなかった展示物としてのレイアウトは高輪の物流博物館のそれだけでした(探せばまだあるのかもしれませんが、それはまたこれからの楽しみにしておきたいですね)
日本の博物館のレイアウトがそのコンセプトの点で45年前とほとんど変わっていないのは少し残念な気もします。
何か言いたい放題に書いている気がしてきました。・・・やはり酒が入るとロクな事を書きません(大汗)
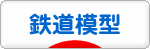
にほんブログ村

にほんブログ村
現在参加中です。気に入ったり参考になったらクリックをお願いします。

昭和39年から42年頃にかけてTMS誌上の特徴のひとつとして「博物館のレイアウトを積極的に紹介していた」事が挙げられます。
今回入手したバックナンバーでは交通科学館・科学技術館・名古屋市立博物館などのレイアウトのグラフがそれぞれ数ページにわたって紹介されていました。
興味深いのはその時期の読者の投書欄に「○○のレイアウトが紹介されていないけれど予定はありますか」という質問に対し「本誌では取り上げるに値する物しか取り上げません」といった意味の回答をしていた事です。
してみると当時は他にもエリミネートが必要なくらいに展示用レイアウトがいっぱいあったという事でしょうか。

16番ですら十分なレイアウト用品のなかったこの時期にこれだけの規模のレイアウトを作り展示していたという事は凄い事だったと思います。
そしてそれらは単なる展示品の域を超えて当時のファンへレイアウトへの夢をかきたてていたのではないでしょうか。
ただ、これらの記事を読んで感心すると同時に気になった事もありました。
それは最近の博物館のレイアウトはコンセプトの面でこの当時から一歩も進歩していないのではないかという懸念です。
確かに広大なスペースに線路が縦横無尽に張り巡らされてはいます。しかし駅はあっても駅前広場がなく周囲の風景に人間の匂いがまるで感じられない。
ただうつろなだけの空間。
そこを走る列車も単なる抜け殻にしか見えない事があります。
これが個人やクラブの所有、或いはレンタルレイアウトならば笑って済みます。
いや、ユーザーの思い入れがストレートに伝わる分だけ単なるギャラリーの立場としてもはるかに楽しめます。
しかし博物館の展示品がそれで良いのでしょうか。
列車といえども世間とは無縁に存在できず「周囲の自然・社会環境との繋がりの中走らせてで初めて列車にも命が吹き込まれる」事を認識できていないのではないかとすら思える事があります。

TrackAheadなどの海外番組で見せてもらった博物館のレイアウトでは「地域の産業・人流・物流の流れといった社会システムをシーナリィとして再現し、その中で列車を走らせる事で鉄道の役割を視覚的に認識させる」事を何より重視した設計がなされています。その点で例えばシカゴの博物館のレイアウトなどは個人的に理想のレイアウトのひとつと見えました。
私の知る限りでそこを外さなかった展示物としてのレイアウトは高輪の物流博物館のそれだけでした(探せばまだあるのかもしれませんが、それはまたこれからの楽しみにしておきたいですね)
日本の博物館のレイアウトがそのコンセプトの点で45年前とほとんど変わっていないのは少し残念な気もします。
何か言いたい放題に書いている気がしてきました。・・・やはり酒が入るとロクな事を書きません(大汗)
にほんブログ村
にほんブログ村
現在参加中です。気に入ったり参考になったらクリックをお願いします。









