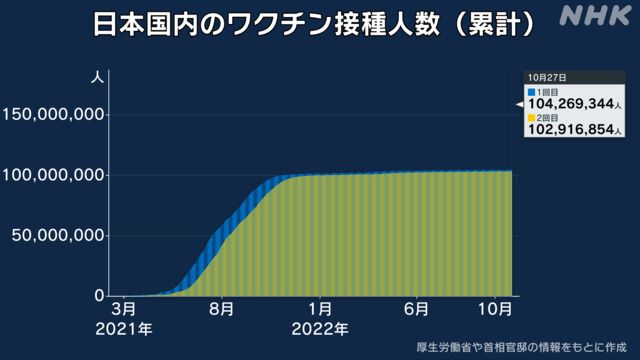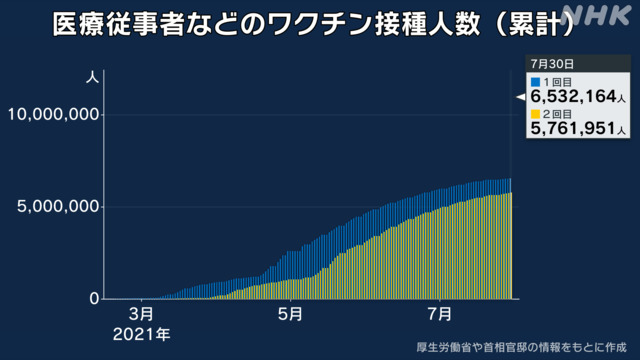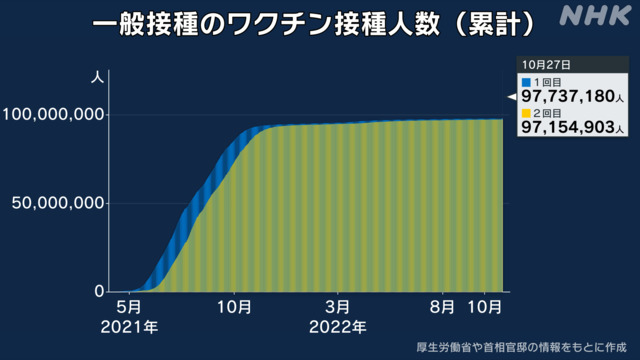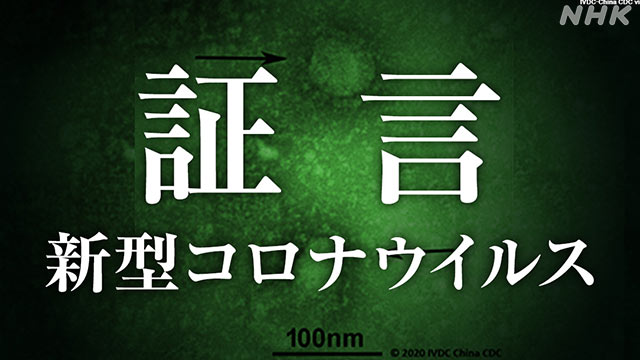あらすじ
1925年、大英帝国博覧会閉会式で、ヨーク公アルバート王子はエリザベス妃に見守られ、父王ジョージ5世の代理として演説を行った。しかし、吃音症のために悲惨な結果に終わり、聴衆も落胆する。
エリザベスはアルバート王子を説得して、言語聴覚士であるオーストラリア出身のライオネル・ローグのロンドンのオフィスをともに訪れる。独自の手法で第一次世界大戦の戦闘神経症に苦しむ元兵士たちを治療してきたローグは、王室に対する礼儀作法に反してアルバートを愛称の「バーティ」で呼びつけ、自身のことは「ローグ先生」ではなく「ライオネル」と呼ばせる。ローグの無作法に反発し帰りかけたアルバートに、ローグはシェイクスピアの『ハムレット』の台詞を朗読できるかどうか、賭けを持ちかける。ローグは音楽が流れるヘッドホンをつけさせ、アルバートには自身の声が聞こえない状態でその声をレコードに録音する。途中で腹を立てて帰ろうとするアルバート王子にローグは録音したばかりのレコードを持たせる。
クリスマス恒例のラジオ中継の後、父王ジョージ5世は、新時代における放送の重要性と共に、アルバートの兄:デイヴィッド王太子は次期国王に不適格であり、アルバート王子が王族の責務をこなせるようにならねばならないと語り、厳しく接する。帰邸後、苛立ったアルバート王子はローグから受け取ったレコードを聴き、自分の滑らかな発声に驚く。王子はローグのもとを再び訪れ、口の筋肉をリラックスさせる練習や、呼吸の訓練、発音の練習などを繰り返し行う。アルバートはローグに吃音症の原因となった自身の不遇な生い立ち(右利きでないことを罰せられ矯正された、乳母に虐待されたなど)や、吃音を揶揄されたこと、末弟ジョン王子の死去-を打ち明け、二人の間に友情が芽生えていく。
1936年1月、ジョージ5世が崩御し、デイヴィッド王子が「エドワード8世」として国王に即位する。しかし、新王が結婚を望んでいた女性、ウォリス・シンプソン夫人はアメリカ人で、離婚歴があるだけでなく2番目の夫といまだ婚姻関係にあったため、王室に大きな問題が起こるのは明白であった。その年のクリスマス、ヨーク公夫妻はバルモラル城で行われたパーティで、城の周辺の木が勝手に切り倒される光景と、国王とシンプソン夫人の下品な姿を目の当たりにする。見かねたアルバート王子が兄王に、英国国教会の長でもあるエドワード8世は離婚歴のある女性とは結婚できないことを指摘すると、王は吃音症治療は王位ほしさからなのかと責め、吃音をからかう。
エドワード8世の醜聞を聞いたローグは、代わりに国王に即位するべきだとアルバートを説得するが、王子は「それは反逆罪に当たる」、「あなたのような平民に言われる筋合いはない」と怒りローグの元から去ってしまう。
結局エドワード8世はウォリスとの結婚を諦めきれず、結婚するが、スタンリー・ボールドウィン首相やウィンストン・チャーチル元海軍大臣らの反対を受け、即位して1年も満たぬうちに退位し、アルバート王子が『ジョージ6世』として即位する事態になる。アルバートは国王の重責に、自分は今まで海軍士官しか務めたことがないとエリザベス妃に不安を吐露する。一方ヨーロッパ大陸では、アドルフ・ヒトラー率いるナチ党政権下のドイツが台頭し、一触即発の機運となっており、大英帝国は国民の統一を促す国王を必要としていた。しかし新国王の吃音症は依然として深刻なままで、王位継承評議会での宣誓は散々なものであった。ジョージ6世夫妻は再びローグを訪ね、謝罪して治療を再開する。
戴冠式に備えるジョージ6世は、ローグにはなんの医療資格も持たないことを知る。カンタベリー大主教コスモ・ラングは、ローグを国王から遠ざけようと試みるが、国王はローグを臨席させると譲らない。国王となることに不安を覚えるジョージ6世の前で、ローグは戴冠式で使われる椅子に座ってみせて国王を挑発する。
激怒してローグを怒鳴り散らす国王は、自らの雄弁さに驚く。戴冠式での宣誓は滞りなく進行し、ジョージ6世はその様子をニュース映画で家族とともに観る。さらに、それに引き続くニュースで、アドルフ・ヒトラーの演説の巧みさに強い印象を受ける。
やがて、ボールドウィン首相の後を継いだネヴィル・チェンバレン首相の宥和政策は失敗し、1939年9月1日のドイツのポーランド侵攻を受けて、9月3日に英国はドイツに宣戦布告、第二次世界大戦が始まる。
同日、ジョージ6世は大英帝国全土に向けて国民を鼓舞する演説を、緊急ラジオ放送で行うことになる。緊迫した状況の中ジョージ6世は、ローグと二人きりの放送室で完璧な演説をこなす。
放送室から出てきた国王は、報道用に堂々と原稿を読む姿を撮影すると、エリザベス王妃、そしてエリザベス王女・マーガレット王女とともに宮殿のバルコニーに出て、待ち構える大衆に手を振る。その様子をローグは満足げに見守るのだった。
解説
現イギリス女王エリザベス2世の父ジョージ6世の伝記をコリン・ファース主演で映画化した歴史ドラマ。
きつ音障害を抱えた内気なジョージ6世(ファース)が、言語療法士の助けを借りて障害を克服し、第2次世界大戦開戦にあたって国民を勇気づける見事なスピーチを披露して人心を得るまでを描く。
共演にジェフリー・ラッシュ、ヘレナ・ボナム・カーター。
監督は「くたばれ!ユナイテッド」のトム・フーパー。第83回米アカデミー賞で作品、監督、主演男優、脚本賞を受賞した。
スタッフ・キャスト
幼少時から吃音に悩み、内向的だったヨーク公アルバート王子が、風変わりな言語セラピストや妻・家族に支えられながらコンプレックスを克服し、英国王ジョージ6世になるまでの実話を描いた人間ドラマ「英国王のスピーチ」が今週末ついに日本公開を迎える。
本年度アカデミー賞で最多12部門のノミネートを果たした本作において、主人公ジョージ6世を熱演したコリン・ファースが、先頃開催された第61回ベルリン国際映画祭に来場。英国王ジョージ6世の役作り、そして期待が高まるオスカー受賞への思いを語ってくれた。(取材・文:森山京子)
コリン・ファース インタビュー
「自分のキャラクターに優しさと敬意をもって演じたつもりだ」

(C)Steve Carty
コリン・ファースの素顔は、スクリーンで見るイメージとあまり変わらない。イギリス紳士らしく丁寧できちんとしている。そのコリンが、突然「Bullshit(でたらめだ!)」などと乱暴な言葉を使ったのでびっくりしてしまった。最近、「僕は王室のファンではない」というコメントを書かれたことに腹を立てたのだ。

「とんでもないデマだ。そんなことを言ったことは一度もないよ、Bullshit!」とかなりのご立腹。「王室が好きだと言ったことはあるよ。チャールズ皇太子が好きだし、彼の環境問題への取り組みや社会活動は素晴らしいと思っている。君主制主義者をどう思うかと聞かれたから、政府のシステムなら民主主義が好きだと答えただけだ。自分たちのリーダーを自分たちが選ぶのは当然じゃないか」
コリンが王様を演じるのは学生の時以来。歴史物ならいざ知らず、今回は記憶に新しい先代の国王なので、似ていないと批判されることは覚悟していたと言う。
「ジェフリー・ラッシュと、彼が演じたローグのお孫さんから借りた日記を研究したよ。僕たちが目指したのはジョージ6世とローグの友情を出来る限り信憑性のあるものにするということ。Bromance(Brother Romance=セクシャル関係ではない男同士の堅い絆)って言葉があるけど、この2人はまさにそれだと思うよ。それと自分のキャラクターに優しさと敬意をもって演じたつもりだ。まだ両方の親族がいるわけだから、彼らを傷つけないようにしたかった」
普段は緊張で堅い表情をしているジョージ6世が、娘たちとのシーンでは優しいパパになっているのも、意図して演じた結果だ。
「僕は、彼と2人の娘の間には大きな愛情があったと信じている。エリザベスがケニア親善訪問に出かける時、重病だった彼は医者の反対を振り切って飛行場まで見送りに行っている。彼の写真は直立不動で堅苦しいものがほとんどだけど、娘と一緒の写真だけは微笑んでいる。暖かい関係だったと思うよ」
コリンや監督たちが王室やローグ家以上に気を遣ったのが吃音に悩む人に対してだ。
「彼らがどう受け止めるか心配だったけど、幸いなことにとてもいい反応があった。世の中で無視されてきた問題に注意を促してくれたとか、彼らの置かれている状況を理解しているとか。映画を見て救われたと言う人もいた。吃音は、これまで笑いの対象として描かれることが多かったからね。実は脚本のデビッド・サイドラーも吃音なんだ。だからこの問題を真っ向から描くのは凄く勇気が要ったと思う。素晴らしい仕事をしたよね」
その吃音の症状をマスターするにはかなりの時間がかかったと言う。

英国王のスピーチ : インタビュー
トム・フーパー監督「英国王のスピーチ」のオスカー像は母による恩恵
第83回アカデミー賞で作品賞、監督賞、主演男優賞、オリジナル脚本賞の4冠に輝いた「英国王のスピーチ」。製作当初は低予算で地味な映画と見なされていた今作をこれほどの成功に導いたのは、トム・フーパー監督の才能によるところが大きい。コリン・ファース、ジェフリー・ラッシュ、ヘレナ・ボナム・カーターという優れた役者を擁し、ヒューマニティとユーモアにあふれた感動的な作品を生み出すまでの過程を、賞レースの真っただ中にいたベルリン国際映画祭期間中にフーパー監督が語った。(取材・文:佐藤久理子)
「この企画と出合ったのは、じつは母のおかげなんだ。4年前この作品の戯曲をロンドンで朗読する会があって、そこに出席した母から教えてもらった。これはすごく面白い話だと思って、さっそく戯曲を書いていたデビッド・サイドラーに映画の脚本も書いてくれるように頼んだんだよ」
とはいえ、奇遇にも時を同じくしてオーストラリアでは、後にスピーチ・セラピストのライオネルを演じることになるジェフリー・ラッシュがこの戯曲を手にしていた。やがて、“オーストラリア・コネクション”によって両者が出会い、プロジェクトが軌道に乗った。
「まずジョージ六世とエリザベス女王役のキャスティングを始めた。ジョージ六世には最初、レイフ・ファインズやポール・ベタニーらが頭に浮かんでいた。コリンの名前が出て来たとき、若干躊躇(ちゅうちょ)したのを覚えているよ。というのも50歳の彼は39歳という映画のなかの王の年齢からはかなり上だし、肉体的に小柄で脆弱(ぜいじゃく)だった王に比べて身長もすらりと高いから。でも、トム・フォードの『シングルマン』を見て大丈夫だと思った。紳士的で控えめだし、寛大でとても人間的なところは、僕の考える王の性格と共通するものがあった。だから一旦彼と決めてからはもう迷いはなかったよ。ヘレナに関しては、ただもうパーフェクトなキャスティングだと思った。彼女がこれまでに演じた女王はかなりエキセントリックだったけれど(笑)、とても演技派だからね」
「現存するライオネルの日記を読んだとき、僕らはふたりの間に特別な絆があると思った。彼の前でジョージ六世は他人には見せないような表情を見せていたし、ライオネルもまた彼に特別な親愛の情を感じていた。彼はジョージ六世が亡くなったあとすぐに引退したらしい。映画の中でふたりが交わす会話で、『Wがつっかえていたな』とライオネルが言うと、王が『僕だとわかるようにわざとしたんだ』と冗談を言うシーンがあるけれど、これはまさしくライオネルの日記に記されていた通りなんだ。彼以外の前では、ジョージ六世はこんなことを絶対に言わなかっただろう」
現在38歳のフーパー監督は、日本での知名度はまだ低いものの、テレビシリーズですでにエミー賞やゴールデン・グローブ賞を受賞している実力派だ。子ども時代から映画に対する強い愛着を持っていたという。
「12歳のときに映画に恋をして、13歳でカメラを手にしていた。将来監督になろうと決めていたんだ(笑)。若いころはベルイマン、タルコフスキー、トリュフォーなど、ヨーロッパの巨匠たちから多大な影響を受けた。その後、コッポラやスコセッシらが撮ったアメリカ映画も見るようになった。当時はイギリスのBBCで優れた映画がたくさん放送されていたから、皮肉なことに僕はテレビからとても大きな映画教育を受けた。最初の短編もチャンネル4のために撮ったものだし、今の僕があるのはテレビのおかげと言えるかもね(笑)」
人生を左右する出会いには必然性がある。吃音に悩んでいたヨーク公(のちのジョージ6世=コリン・ファース)と、医師の免許もなくパッとしない人生を送っていたスピーチ矯正師ローグ(ジェフリー・ラッシュ)の場合も例外ではない。もしこの出会いがなかったら2人の人生はもちろん、イギリスの命運も変わっていただろう。そう思わせるほど、吃音の克服と2人の人生の山場がドラマチックにクロスしている。フィクションを超えた実話の面白さに魅了されてしまった。
とにかくこの映画に出てくるエピソードはどれも面白すぎる。一番驚いたのはヨーク公の悲惨な幼年時代だ。強くて怖い父親と自由奔放な兄に挟まれ、左利きやX脚の矯正を無理強いされ、乳母にまで虐待されていたとは。
そして、純愛物語として有名なエドワード8世の「王冠をかけた恋」は、わがままな兄が突然家業を放り出して自信のない弟に責任を押しつけるという、兄弟の葛藤にフォーカスされている。王室ものとして以上に、威圧的な親が息子を抑圧するファミリードラマとして面白いし、立場が違えば同じ事件でもこんなに違う様相になるというのも興味深い。
ヨーク公の苦悩をベースにした落ち着いたトーンに、ローグとの関係の変化を3段階で表現してアクセントをつけた脚本の構成も見事だ。閉じこもっていた殻から一歩踏み出すヨーク公をユーモラスに見せるトレーニングシーン。
自分の運命はローグに託すしかないと決断する戴冠式のリハーサル。そして、2人の信頼関係が最高の効果を発揮するラストのラジオ放送だ。このシーンで、ローグはオーケストラの指揮者、ジョージ6世はそのタクトに導かれる演奏者のように見えて感動した。ファース、ラッシュ、そしてヘレナ・ボナム・カーターら俳優たちの素晴らしさは言うまでもない。
(森山京子)















![こんな日もある 競馬徒然草 by [古井由吉, 高橋源一郎]](https://m.media-amazon.com/images/I/41yqbl1vy+L.jpg)