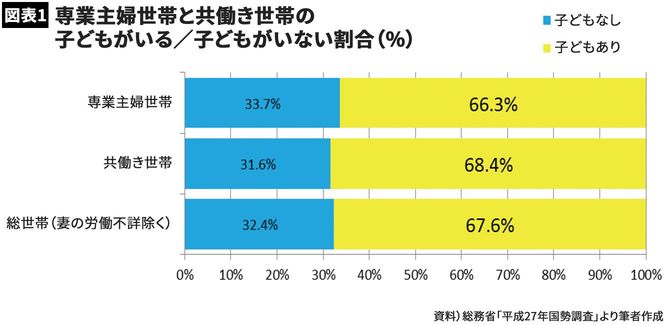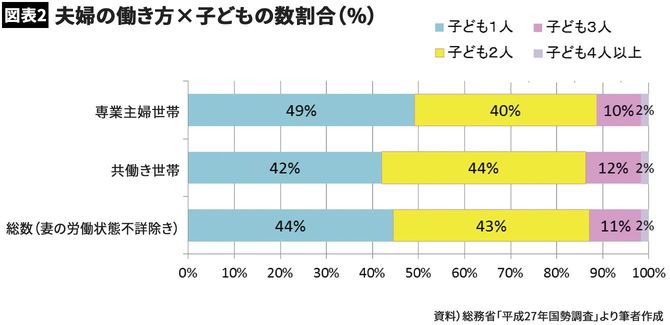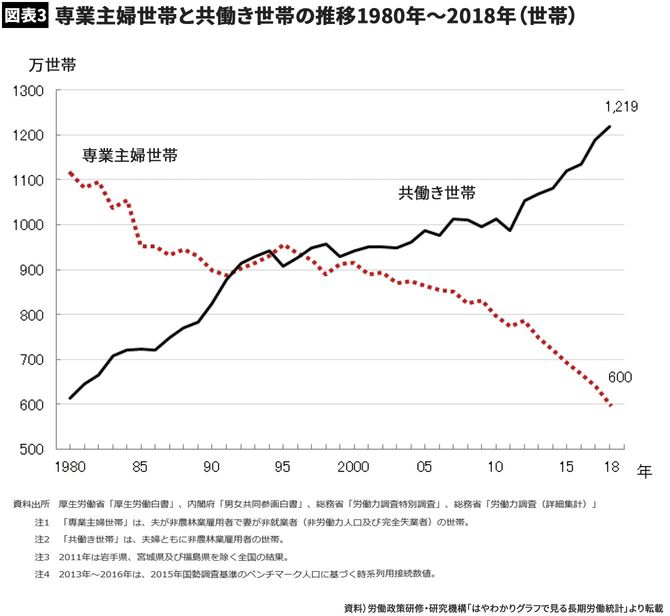小室 直樹 (著)
小室 直樹は、日本の社会学者、評論家。
学位は法学博士。東京工業大学世界文明センター特任教授、現代政治研究所所長などを歴任。
内容(「BOOK」データベースより)
宿命のライバル、日米のたまさかの蜜月が過ぎようとしている。
安保条文の落とし穴、国連憲章にある“敵国条項”に気付いている日本人がどれだけいるだろうか。
資本主義化の道をたどる、中国、ソ連の広大な市場を制するのは日本だ、とアメリカが悟ったならば…。
巨大な人造国家アメリカの本質を徹底的に探る、気鋭の渾身作。
わたしは中学1年の時、この本を非常に面白く感じ一気に読破した記憶があるので、あの時の喜びを今一度と思いネットで注文し、約45年ぶりに再読しましたが、少々拍子抜けしたように感じたことが率直な感想です。
何故かというと、大人になってから小室氏の著作をいくつか読んでいたのですが、それぞれの著書の主要な部分がこの本の中にすでに語られていたからです。
ですから、各著書を再読しているような感じでやや退屈であったことわ意外なことでした。
だからと言って小室氏の著書我つまらないと言うわけではりません。 氏の著書は面白く、刺激的で、意外性な論述がちりばめられ、わたしはこれからも氏の本を読み続けていくでしょう。
この恐るべき言葉を理解しさえすれば、戦後日本とアメリカ、そして極東アジアの関係と
そこで惹起する諸事態に、すべて明確に説明がつく。
このことを理解したとき、私は戦慄した。小室直樹の恐るべき慧眼に。
まだそれは私の中で続いており、これからその衝撃に明確な言葉を当てはめてゆく。
みなさんもはやくその衝撃に撃たれんことをのぞむ。
この本が書かれた約30年前にソ連崩壊と衛星国の独立を言い当てている事、支那の近代化には日本の資本が無くては不可能である事、また、外国人労働者の受け入れについて言及している件はさすがと思わされる。
また日支の接近はアメリカの脅威となる(支那人の手による日本製品が世界を席巻)は予言の書を思わせる…
また、日本の外交音痴は平安朝に常備軍を無くし、遣唐使を廃止して外交を放棄、法律すら無いという世界にも例を見ない『平和国家』を作り上げ、その伝統が今も本質的には残っている。
これが日本人が外国人と大きく違うという喝破される点には大きくうなずかされる。
最終章だが「大東亜戦争はこうすれば勝てた」との件(くだり)の本質は国運を託して大和、武蔵を建造する事で他国戦艦を圧倒する性能を見せつけ「抜かずの政治カード」として外交の切り札とする『ヒトラー』的な発想のできる人材がいなかった事に尽きるのだと思う(日本の自存自衛の為の戦争であり、アメリカとの交戦になるのでは山本五十六あたりでは荷が重かったか)。
日本の自存自衛の戦争であるのに『戦争目的の不徹底』こそが敗因だった事、南京陥落を政治的利用できない外交音痴ぶりが敗因に油を注ぐ事になった事を著者は言いたいのだと思うが…
日米関係とは日中関係である。
この恐るべき言葉を理解しさえすれば、戦後日本とアメリカ、そして極東アジアの関係と
そこで惹起する諸事態に、すべて明確に説明がつく。
このことを理解したとき、私は戦慄した。小室直樹の恐るべき慧眼に。
まだそれは私の中で続いており、これからその衝撃に明確な言葉を当てはめてゆく。
みなさんもはやくその衝撃に撃たれんことをのぞむ。
発想方法が特異であることは確かである。
たとえが 実にやさしく 明解な時がある。
アメリカの生活が長いようだが、日本のマスコミについて、よく知っている。
中国の発展方向についての見方。近代化の推進。基礎投資を必要とする。
マルクスのいう 原始蓄積。中国における労働力は 豊富で安価
日本に対する見方。
単純労働が高く、技術労働と等価に近い。氷の上の乱舞に近い。
日本は一貫性がないことが 特徴だ。
奇跡を実証しようとするアメリカ的発想と
奇跡を信じるか信じないかと考える日本の発想。
さだめ。運命。掟に縛られる日本。
日本は 労働生産性が 意外と低い。それは、ねまわしと真面目さが障害なんでしょうね。
アメリカが つねに 前進し 労働生産性が上がっていくのが不思議なくらいだ。
アメリカの生活が長いようだが、日本のマスコミについて、よく知っている。
中国の発展方向についての見方。近代化の推進。基礎投資を必要とする。
マルクスのいう 原始蓄積。中国における労働力は 豊富で安価
日本に対する見方。
単純労働が高く、技術労働と等価に近い。氷の上の乱舞に近い。
日本は一貫性がないことが 特徴だ。
奇跡を実証しようとするアメリカ的発想と
奇跡を信じるか信じないかと考える日本の発想。
さだめ。運命。掟に縛られる日本。
日本は 労働生産性が 意外と低い。それは、ねまわしと真面目さが障害なんでしょうね。
アメリカが つねに 前進し 労働生産性が上がっていくのが不思議なくらいだ。
小室直樹のことをまったく知らずに今日まで来たのだが、ついに気になる人物になった。
副島隆彦が気になりだしてその繋がりで。
研究社の英和辞典を貶めて、大修館の辞典を高からしめた人物としか知らなかったのだが、小室の教え子らしい。まずは小室からと手近なところで、古いが本書を手にして見た。
伝統的な識者の流れを汲むかのような漢語を多用した流麗な文体で読みやすかった。
「日本たたき」があった時代だったのか、アメリカと日本の文化を比較していて読み物として楽しめた。
75ページ「英国古典経済学の吹く笛におどらされて自由貿易にふみきった国ぐには、みんな国民経済の根底を破壊されて、英国の経済的植民地になってしまった。
「日本たたき」があった時代だったのか、アメリカと日本の文化を比較していて読み物として楽しめた。
75ページ「英国古典経済学の吹く笛におどらされて自由貿易にふみきった国ぐには、みんな国民経済の根底を破壊されて、英国の経済的植民地になってしまった。
たとえば、アイルランドやポルトガルがそのいい例だ。」
なんだかTPPの行く末を予言しているようだ。
なんだかTPPの行く末を予言しているようだ。
とはいえ、アメリカの圧力の前に日本は従わざるを得ないのだ。それなら次はどうすればいいのか、これは副島さんたちから提言してもらうことになるのだろう。
105ページ「日韓関係における韓国人側の根本的民族感情とは何か。それは、文化に関しては、両者は師弟関係にあるという認識である。誤解してはならない。ここで師とは韓国人であり、弟子は日本人の側である。」
105ページ「日韓関係における韓国人側の根本的民族感情とは何か。それは、文化に関しては、両者は師弟関係にあるという認識である。誤解してはならない。ここで師とは韓国人であり、弟子は日本人の側である。」
「明治にいたるまでは、日本人も韓国人も、かたくこのように思いこんでいたのである。」
文鮮明が「日本は韓国の妹であるから兄である韓国を支えなければならない(お金を貢がねばならない)」というようなことを語った文を読んだことがあるが、なるほどここからきていたのだ。
韓国は中国に歴史的にどんなに虐げられてきていても、それは厳父とみなしているために尊敬の念をいだいて忍耐できる。しかし格下である日本の、兄韓国への思い上がりや追越はけっして許してはおけない、という感情が働くというわけだ。
「信仰」の日米のあり方の違いは底なしに深いようだ。ちなみに日本が無宗教なのは、小室先生は指摘していなかったが、日本の文化の形成の基礎となった中国の合理主義、無宗教が影響しているのではないだろうか。
最後に「太平洋戦争はこうすれば勝てた」という章が付け加えられているが、ここにいたるまでの論調からすれば、本章は「日本が勝てなかった理由」ということだろう。
文鮮明が「日本は韓国の妹であるから兄である韓国を支えなければならない(お金を貢がねばならない)」というようなことを語った文を読んだことがあるが、なるほどここからきていたのだ。
韓国は中国に歴史的にどんなに虐げられてきていても、それは厳父とみなしているために尊敬の念をいだいて忍耐できる。しかし格下である日本の、兄韓国への思い上がりや追越はけっして許してはおけない、という感情が働くというわけだ。
「信仰」の日米のあり方の違いは底なしに深いようだ。ちなみに日本が無宗教なのは、小室先生は指摘していなかったが、日本の文化の形成の基礎となった中国の合理主義、無宗教が影響しているのではないだろうか。
最後に「太平洋戦争はこうすれば勝てた」という章が付け加えられているが、ここにいたるまでの論調からすれば、本章は「日本が勝てなかった理由」ということだろう。
アメリカと日本はゾウとアリくらい違うのだから負けて当然、挑んだのは愚かなことだ、という一般常識を覆す論拠として、それならベトナムも北朝鮮も即刻降伏するはずなのにそうでないのはなぜかと、日本の戦略思考のお粗末さを指摘している。
ベトナムはすでにアメリカに勝利しているし、北朝鮮も何度もアメリカを翻弄している。
ベトナムはすでにアメリカに勝利しているし、北朝鮮も何度もアメリカを翻弄している。
それなのに日本はアメリカのポチだ、属州と化している、とかいわれることがある。
その言動の底意には、それでいいのだ、といってような感じがある。従属するようになったのは、日本がアメリカに敗戦し平和憲法を押し付けられたからではなく、アメリカの巧妙な策略によって戦争をしなければならないように追い詰められた挙げ句に粉みじんに打ち砕かれ、わが身を思い知らされたからであるようだ。
小国は勁草たるべし。
米ロ中の狭間に生きる日本は、北朝鮮を反面教師としつつも等距離外交によって米ロ中への平和的逆襲も隠しカードとして模索しておいてもいいのではないだろうか。
ソ連崩壊をソ連全盛期に予測し原因から結果までほぼ完ぺきに予測した氏。その彼が日本のバブル期にも「このままだと日本崩壊の恐れ極めて高い。本書かねばならぬかも※ソ連崩壊と同系」と言っていた。
正に今、その通りに※当時はそうなるとは夢にも思わず。彼の著作は一通り読むべし。










![大衆明治史(国民版): 再校正 GHQ焚書 (いざなみ文庫) by [菊池寛, いざなみ文庫]](https://m.media-amazon.com/images/I/41mp4UC+YrL.jpg)