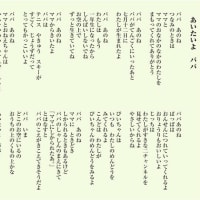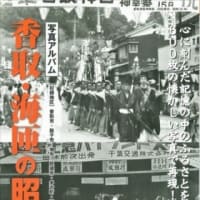1 はじめに
アメリカの仏教学者ケネス・チュンは、「中国における仏教の中国化」という視点の重要性を訴えた。『中国仏教研究入門』を参照しながら以下に考察したい。
2 異宗教としての仏教の伝来と普及
2-1 後漢代から西晋時代の仏教
異民族の宗教としての仏教の中国伝来については、
①北伝のシルクロード経由のルート
②南伝の海路のルート
とある。
①「北伝のシルクロード経由のルート」については早い時代から記録がある。紀元後1世紀頃には仏教が中国に伝来していたと推測できる。
中国人は当初、自国の宗教伝統における「黄老信仰」に基づく神仙方術や不老長生の術に類するものとして仏教をとらえていたであろう。
2-2 仏典の翻訳と格義、偽経の撰述
仏典の翻訳は2世紀半ばにスタートし、7世紀には玄奘の登場で最高となった。
訳経という営み自体が、中国思想を普遍的、統一的なものにしていくという点において非常に重要なものであった。
初期の頃は、つまり後漢の桓帝の時代には、147年大月氏の支婁迦讖が洛陽へ14部27巻の大乗経典を翻訳した。さらに148年、安息の安世高が同じく洛陽に至り、禅観経典、初期仏教経典、アビダルマの論書34部40巻を翻訳した。
3世紀に至って、魏・呉・蜀の三国時代を迎えることとなる。この時代においては多くの経典が翻訳されていった。特に老荘と儒教とをべースに解釈を加えることとなったことが、中国の仏教者たちの独自な仏教経典を撰述しようとした流れにつながっていく。「偽経」と呼ばれるもので、仏教の中国化を論じる上で、非常に重要な研究課題の一つである。
2-3 中国の伝統思想との対決
3世紀半ばころ、中国における仏教は一定の関心を持たれていたことが『弘明集』などによってわかる。『弘明集』の巻頭にあるのが『理感論』である。すべて問答体で、37条からなる。この問いの部分に当時の中国の人々が仏教への批判や疑問を表現している。清貧思想や出家主義、輪廻思想についても率直な疑問が提示されている。そしてその反論の中に、仏教思想や仏教者の考え方が反映されていないというところに、やがて中国固有の仏教を生み出していく発想の基盤と独自性を見るのである。
2-4 仏教教団の成立と仏図澄・道安
西晋末期に優れた僧が登場した。仏図澄、道安、慧遠である。僧侶の集団化が進んだ。
3 南北朝時代の仏教
3-1 北朝の仏教
異民族支配化の宗教政策と仏教ということで、江北中原では、4世紀前半から5世紀前半の100年間にわたって五胡十六国の時代があった。分裂と動乱の時代ともいうべきで、不安定な時代であったからこそ仏教も広まった。また北朝時代の仏教の国家的な性格が、仏教を堕落させた。北魏太武帝の時に廃仏をされている。
3-2 南朝の仏教
老荘や玄学的影響の仏教が発展した。その後の仏教の発展に大きな影響を与えた鳩摩羅什が登場する。5世紀初頭である。父はインド人で、門下3000人を数えた。
4 統一国家と仏教 隋唐時代
4-1 隋の誕生と仏教
中国仏教が最も隆盛したのが、隋・唐の時代である。優れた学僧が幾多も輩出され、教義・教学が整備体系化されたいう点において、「仏教がインド亜流の仏教を脱して真の意味で中国人の仏教を創出した時代であった」と岡部和雄は書いている。
この時期から仏教は国家仏教的色彩を色濃くしていくことになる。煬帝も仏教興隆に力を注ぐことになる。この時期に天台智が登場して新たな統一王朝の政治的役割をイデオロギー的に補完しうるものとして仏教の役割が作られる。
4-2 唐王朝と仏教
「中国仏教史上、最高潮に達した唐代仏教」という定義を鎌田茂雄はしている。
618年高祖が即位する。国際都市長安を擁し、国力は栄えた。
唐国家の国際性のもと、宗教もまた国際的な宗教空間が形成された。外来宗教が伝来して、ゾロアスター教、キリスト教、イスラム教等々が伝えられた。
こうした中で、中国人仏教者も西域やインドへと旅をして、当時の西域の情勢を中国に伝えた。さらに、不空や金剛智が中国に密教を伝えた。もう一つの動きは中国仏教を東アジア圏内に伝えようとした動きである。鑑真和尚、少し時代は下って最澄や空海の中国への留学などがあって、仏教という宗教が大きな役割を果たしていた。
5 仏教諸派の展開
5-1 教理研究の進展と総合化
鳩摩羅什の存在の大きさは、300巻にも及ぶ膨大な経論を翻訳し、南北朝時代に仏典研究が活性化していく起爆剤になったことである。大乗仏典の研究がますます盛んになっていった。そして、中央集権国家の登場によって、新たな仏教諸派が誕生してくることとなる。
6 仏教信仰の多様化と仏教文化の爛熟
仏教行事、儀式の庶民への浸透が中国的な色づけをされながら民衆へ浸透していったのがこの時期である。中国の仏教化と言ってもいい。
また仏教説話にみる庶民信仰の具体化ということでは、弥勒菩薩信仰が登場してくる。
仏教文化の爛熟ということでは、大規模寺院や石窟寺院の文化があげられる。
7 偽経と教相判釈について
7-1偽経とは文字どおりには、後代の人が偽作した教典を意味する。しかし、この呼称は、中国や日本で撰述された教典に限って用いられる。
しかし、偽経の存在は次第に中国で増加し、4世紀の道安の頃には26部30巻であったが、南北朝時代には46部56巻に増え、さらに、隋代には209部490巻、唐代には406部1074巻となった。『大蔵経』に入った経典が1076部5048巻であること(『開元釈経録』)からすれば、その数の多さは凄まじいものがある。
偽経には、中国仏教者の仏教への対応が多種多様に、しかも集約的に示されているという点で重要である。
7-2教相判釈
教えを説いた時期を分類し、どれが最高の教えであるかという点において、あるいは教えの相や時期によって、お経を判別し解釈する。これを教相判釈という。教相は教えのすがた、実際に示されている教えのことである。教相判釈は、中国独自のお経を解釈する学問として発達する。仏教の中国化である。
天台大師智の登場によって、仏教の中国化の条件が整いつつあった。智は江南に在住して、法華経をもって天台宗を大成していった。総合的な仏教思想に優れ、教観双備と言われて讃えられた。
8 おわりに
仏教の中国化と中国の仏教化という課題は、時期的に限定できるものではなく、表裏一体で発展を見たということである。
参照文献
岡部和雄・田中良昭編 『中国仏教研究入門』2006 大蔵出版 pp.3-22
木村清孝著 『中国仏教思想史』 1991 世界聖典刊行協会 PP.16-27
鎌田茂雄著 『新中国仏教史』 2001 大東出版社 p.122
木村清孝著 『中国仏教思想史』 1991 世界聖典刊行協会 PP.53-66
大正大学仏教学科編 『仏教とはなにか その歴史を振り返る』 1999 大法輪閣 pp.160-161
アメリカの仏教学者ケネス・チュンは、「中国における仏教の中国化」という視点の重要性を訴えた。『中国仏教研究入門』を参照しながら以下に考察したい。
2 異宗教としての仏教の伝来と普及
2-1 後漢代から西晋時代の仏教
異民族の宗教としての仏教の中国伝来については、
①北伝のシルクロード経由のルート
②南伝の海路のルート
とある。
①「北伝のシルクロード経由のルート」については早い時代から記録がある。紀元後1世紀頃には仏教が中国に伝来していたと推測できる。
中国人は当初、自国の宗教伝統における「黄老信仰」に基づく神仙方術や不老長生の術に類するものとして仏教をとらえていたであろう。
2-2 仏典の翻訳と格義、偽経の撰述
仏典の翻訳は2世紀半ばにスタートし、7世紀には玄奘の登場で最高となった。
訳経という営み自体が、中国思想を普遍的、統一的なものにしていくという点において非常に重要なものであった。
初期の頃は、つまり後漢の桓帝の時代には、147年大月氏の支婁迦讖が洛陽へ14部27巻の大乗経典を翻訳した。さらに148年、安息の安世高が同じく洛陽に至り、禅観経典、初期仏教経典、アビダルマの論書34部40巻を翻訳した。
3世紀に至って、魏・呉・蜀の三国時代を迎えることとなる。この時代においては多くの経典が翻訳されていった。特に老荘と儒教とをべースに解釈を加えることとなったことが、中国の仏教者たちの独自な仏教経典を撰述しようとした流れにつながっていく。「偽経」と呼ばれるもので、仏教の中国化を論じる上で、非常に重要な研究課題の一つである。
2-3 中国の伝統思想との対決
3世紀半ばころ、中国における仏教は一定の関心を持たれていたことが『弘明集』などによってわかる。『弘明集』の巻頭にあるのが『理感論』である。すべて問答体で、37条からなる。この問いの部分に当時の中国の人々が仏教への批判や疑問を表現している。清貧思想や出家主義、輪廻思想についても率直な疑問が提示されている。そしてその反論の中に、仏教思想や仏教者の考え方が反映されていないというところに、やがて中国固有の仏教を生み出していく発想の基盤と独自性を見るのである。
2-4 仏教教団の成立と仏図澄・道安
西晋末期に優れた僧が登場した。仏図澄、道安、慧遠である。僧侶の集団化が進んだ。
3 南北朝時代の仏教
3-1 北朝の仏教
異民族支配化の宗教政策と仏教ということで、江北中原では、4世紀前半から5世紀前半の100年間にわたって五胡十六国の時代があった。分裂と動乱の時代ともいうべきで、不安定な時代であったからこそ仏教も広まった。また北朝時代の仏教の国家的な性格が、仏教を堕落させた。北魏太武帝の時に廃仏をされている。
3-2 南朝の仏教
老荘や玄学的影響の仏教が発展した。その後の仏教の発展に大きな影響を与えた鳩摩羅什が登場する。5世紀初頭である。父はインド人で、門下3000人を数えた。
4 統一国家と仏教 隋唐時代
4-1 隋の誕生と仏教
中国仏教が最も隆盛したのが、隋・唐の時代である。優れた学僧が幾多も輩出され、教義・教学が整備体系化されたいう点において、「仏教がインド亜流の仏教を脱して真の意味で中国人の仏教を創出した時代であった」と岡部和雄は書いている。
この時期から仏教は国家仏教的色彩を色濃くしていくことになる。煬帝も仏教興隆に力を注ぐことになる。この時期に天台智が登場して新たな統一王朝の政治的役割をイデオロギー的に補完しうるものとして仏教の役割が作られる。
4-2 唐王朝と仏教
「中国仏教史上、最高潮に達した唐代仏教」という定義を鎌田茂雄はしている。
618年高祖が即位する。国際都市長安を擁し、国力は栄えた。
唐国家の国際性のもと、宗教もまた国際的な宗教空間が形成された。外来宗教が伝来して、ゾロアスター教、キリスト教、イスラム教等々が伝えられた。
こうした中で、中国人仏教者も西域やインドへと旅をして、当時の西域の情勢を中国に伝えた。さらに、不空や金剛智が中国に密教を伝えた。もう一つの動きは中国仏教を東アジア圏内に伝えようとした動きである。鑑真和尚、少し時代は下って最澄や空海の中国への留学などがあって、仏教という宗教が大きな役割を果たしていた。
5 仏教諸派の展開
5-1 教理研究の進展と総合化
鳩摩羅什の存在の大きさは、300巻にも及ぶ膨大な経論を翻訳し、南北朝時代に仏典研究が活性化していく起爆剤になったことである。大乗仏典の研究がますます盛んになっていった。そして、中央集権国家の登場によって、新たな仏教諸派が誕生してくることとなる。
6 仏教信仰の多様化と仏教文化の爛熟
仏教行事、儀式の庶民への浸透が中国的な色づけをされながら民衆へ浸透していったのがこの時期である。中国の仏教化と言ってもいい。
また仏教説話にみる庶民信仰の具体化ということでは、弥勒菩薩信仰が登場してくる。
仏教文化の爛熟ということでは、大規模寺院や石窟寺院の文化があげられる。
7 偽経と教相判釈について
7-1偽経とは文字どおりには、後代の人が偽作した教典を意味する。しかし、この呼称は、中国や日本で撰述された教典に限って用いられる。
しかし、偽経の存在は次第に中国で増加し、4世紀の道安の頃には26部30巻であったが、南北朝時代には46部56巻に増え、さらに、隋代には209部490巻、唐代には406部1074巻となった。『大蔵経』に入った経典が1076部5048巻であること(『開元釈経録』)からすれば、その数の多さは凄まじいものがある。
偽経には、中国仏教者の仏教への対応が多種多様に、しかも集約的に示されているという点で重要である。
7-2教相判釈
教えを説いた時期を分類し、どれが最高の教えであるかという点において、あるいは教えの相や時期によって、お経を判別し解釈する。これを教相判釈という。教相は教えのすがた、実際に示されている教えのことである。教相判釈は、中国独自のお経を解釈する学問として発達する。仏教の中国化である。
天台大師智の登場によって、仏教の中国化の条件が整いつつあった。智は江南に在住して、法華経をもって天台宗を大成していった。総合的な仏教思想に優れ、教観双備と言われて讃えられた。
8 おわりに
仏教の中国化と中国の仏教化という課題は、時期的に限定できるものではなく、表裏一体で発展を見たということである。
参照文献
岡部和雄・田中良昭編 『中国仏教研究入門』2006 大蔵出版 pp.3-22
木村清孝著 『中国仏教思想史』 1991 世界聖典刊行協会 PP.16-27
鎌田茂雄著 『新中国仏教史』 2001 大東出版社 p.122
木村清孝著 『中国仏教思想史』 1991 世界聖典刊行協会 PP.53-66
大正大学仏教学科編 『仏教とはなにか その歴史を振り返る』 1999 大法輪閣 pp.160-161