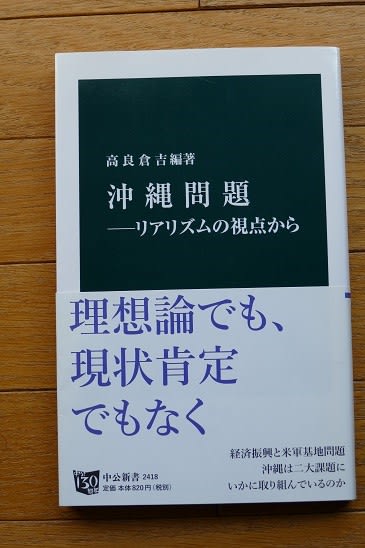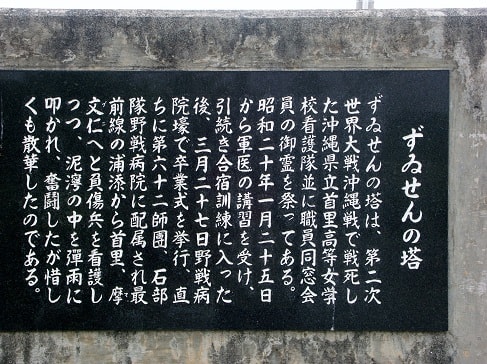昨日、ときおり愛読している公式サイトの【 介護ポストセブン 】の『健康』面を見ている中、
『 デジタル画面の見過ぎで『脳過労』のチェックリスト 脳疲労の解決法 』
このような見出しを見たりした。
まもなく私は喚起させられて、
『デジタルによる『脳過労』のチェックリスト、時代遅れの高齢者の私でも、受診して、苦笑し・・。』、
と題してブログの投稿文を認(したた)めたりした。
今回は、この記事の続編として、
“脳過労”は、認知症につながる危険性大!? 知らないうちに陥る「デジタル依存症」、
と題された掲載されていた。
この記事の原文は、『女性セブン』2020年6月25日号に掲載された記事のひとつで、
関連の公式サイトの【 介護ポストセブン 】に6月24日に配信され、
無断であるが記事の後半部分を転載させて頂く。

《・・
●目や首の痛みの原因「脳過労」とは
前回のデジタルによる『脳過労』のチェック項目にある現象の多くは、
中高年になれば、経験するものだと思う人もいるかもしれないが、その原因は老化だけではない。
24時間途切れることなく情報が流れる現代。
便利な半面、私たちの目や首は、酷使されている。
と同時に、脳には処理能力の限界を超えたゴミ(不要な情報)がたまっていく。
これにより、心身の不調が生じるというのだ。
「毎日テレビやスマホをよく見る人の目や首の痛みは、『脳過労』が原因の可能性があります」
そう言うのは、脳のエキスパートである脳神経外科医の奥村 歩さん。
「たとえば、首が痛いと思っても、実は痛みを感じているのは、脳なので、
脳過労で誤作動が起こると、悪くもないのに体のあちこちが痛くなったり、イライラする。
目や首、姿勢などにいくら気をつけても、
脳の体調管理システムが疲れていては、不調は解消されないでしょう」(奥村さん・以下同)

●脳にゴミがたまり認知症につながる可能性も
特に、忙しい女性は、要注意だという。
「家事や子育て、近所づきあいと、女性は男性よりマルチタスク
(複数の作業をこなす能力。
一見効率がよさそうだが、実は効率が低下し、脳の疲労度を高めるといわれている)に長けています。
いまは働く女性が増え、昔以上に脳は、クタクタ。
息抜きのつもりで見ているテレビやスマホが、さらに脳や体を疲れさせているのです」
脳の処理能力が落ちると、記憶力、思考力、集中力、判断力、コミュニケーション力、
体力などが低下。
脳のゴミは40~50代から、たまり始めるため、その先の認知症につながる危険性も高まる。
さらに恐ろしいのは「とりあえず見る」という行為が、依存症の一種であるとの指摘。
「脳は、疲れると手っ取り早く快感が得られるものに依存しがちです。
たとえば、飲酒やギャンブルが代表的ですが、デジタル依存も同じ性質です。
ハードルが低いという点では、むしろ飲酒などより危険かもしれません」

☆目と首をデジタル情報のシャットアウトで守る!「ぼんやり」して脳を活性化
●ぼんやりする時間を作る
そんな怖い脳過労を軽減するには、どうしたらよいのか。
「20年ほど前に発見された『デフォルト・モード・ネットワーク(以下DMN・詳細は下段図)』が
機能する時間を作ることが大切です」
かつては、脳は活動しているときにのみ、働いていると思われていたが、
この発見により、ぼんやりしているときにこそ、
脳内では、ものすごい勢いで情報の取捨選択や優先順位付け、
さらには心身を安定させる働きまでもが行われていることが解明されたのだ。
「現代人は、視覚から得る情報が多いため、目や首が酷使され、疲労に直結しやすい。
そのため、過労を助長させるテレビやスマホ、ラジオなどの人工的な視覚・聴覚情報を遮断し、
ぼんやりと何も考えないDMNの時間を作ることが大切なのです」

意識的にぼんやりするには、皿洗いやぞうきんがけ、青竹踏みなどのリズミカルで単純な作業、
散歩などがおすすめだ。
その際、歌詞のないクラシック音楽なら流してもOK。
「衰えがちな嗅覚や聴覚を鍛えるためにも、季節を鼻や耳で感じながら、歩くのも効果的。
電車の窓から過ぎゆく景色を眺めたり、入浴もいいですね。
いずれも目的を持たず、無心でいることが重要です」
テレビやスマホを見る前に、「いま、必要なのか」を自問することも忘れてはいけない。
「私はDMNを、デジタルから離れて“我に返る行為”だと思っています。
DMNが活性化されれば、脳は何歳になっても進化を続け、心身の健康につながるのです」
【デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)とは・・・】

脳について知ると脳疲労を減らすことができる(写真/koti/PIXTA)
脳内あり、無意識にぼんやりとしているときに働く機能で、
脳が使うエネルギーの75%前後が、ここで消費されているという。
前頭葉の内側前頭前野や後帯状皮質、その他の脳領域から構成されている。
情報の整理整頓や傷ついた脳を修復するほか、
DMNのハブ(集積機)である前頭葉では、心身の体調管理も行われている。
リンゴが落ちるのを見たニュートンが万有引力を発見し、
山中伸弥教授がシャワー中にiPS細胞のアイディアを思いついたなど、
クリエーティブなひらめきにも、かかわっているといわれている。・・》

私は記事を読みながら、知らないうちに陥る『デジタル依存症』は、
『脳過労』となり、やがて認知症につながる危険性がある、と学び震撼させられたりした。
私が多少救いのある日常生活として、スマホは使えず所有したいない、
そしてテレビの番組は、ニュース、天気情報、ドキュメンタリ番組を視聴するくらいで、
私の知人には、テレビがお友達、或いはスマホが片時も放さない人もいるが、
私は無縁となっている。

私は東京の世田谷区と狛江市に隣接した調布市の片隅みに住んでいる身であるが、
私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、たった2人だけ家庭であり、
そして私より5歳若い家内と共に、古ぼけた一軒屋に住み、ささやかに過ごしている。
こうした中で、私は健康でなければ、自身の日頃のささやかな願いも叶わないので、
歩くことが何より健康体の源(みなもと)と思い、そして適度な熟睡する睡眠、或いは程ほどの食事が、
セカンドライフの私なりの健康体の三種の神器として思い、年金生活16年半を過ごしてきた。

私は民間会社の中小業に35年近く勤めて2004年(平成16年)の秋に定年退職をした身であるが、
定年後、多々の理由で年金生活を始めた・・。
私が年金生活の当初から、平素の買物を自主的に専任者となり、
独りで殆ど毎日のように家内から依頼された品を求めて、買物メール老ボーイとなっている。
こうした中、最寄のスーパーに買物に行ったり、
或いは駅前までの片道徒歩20分ぐらいのスーパー、専門店に行ったりしているが、
根がケチなせいか利便性のよい路線バスに乗るのことなく、歩いて往還している。
その後、独りで自宅から数キロ以内の遊歩道、小公園などをひたすら歩き廻ったりして、
季節の移ろいを享受している。

午後からの大半は、随筆、ノンフィクション、小説、近現代史、総合月刊雑誌などの読書が多く、
或いは居間にある映画棚から、20世紀の私の愛してやまい映画を自宅で鑑賞したり、
ときには音楽棚から、聴きたい曲を取りだして聴くこともある。
この間、私は年金生活を過ごしている中で、何かと身過ぎ世過ぎの日常であるので、
日々に感じたこと、思考したことなどあふれる思いを
心の発露の表現手段として、ブログの投稿文を綴ったりしている。

そして私は愛読しているブログの数多くの御方の投稿文を読ませて頂いたり、
コメントを頂戴したり、返信をしたりしている。
或いは数多くの御方の投稿文を読ませて頂く中で、ときおりコメントをしたりしている。
こうして私はブログに関しては、ほぼ毎日3時間前後は要して、過ごしている。
こうして年金生活を過ごしたりし、ときおり小庭の手入れをしたり、
家内と共通趣味のひとつである国内旅行を遊学している。
このように年金生活を過ごしてきたが、今年の2月の上旬の頃から、
新型コロナウイルスの烈風に伴い、私の日常生活は影響があったりしたが、
何とか以前のような修復している。

今回、「現代人は、視覚から得る情報が多いため、目や首が酷使され、疲労に直結しやすい。
そのため、過労を助長させるテレビやスマホ、ラジオなどの人工的な視覚・聴覚情報を遮断し、
ぼんやりと何も考えないDMNの時間を作ることが大切なのです」、
と私は学びながら、のんびり屋の私は、微苦笑しながら、そうですよねぇ・・同意を深めたりしている。