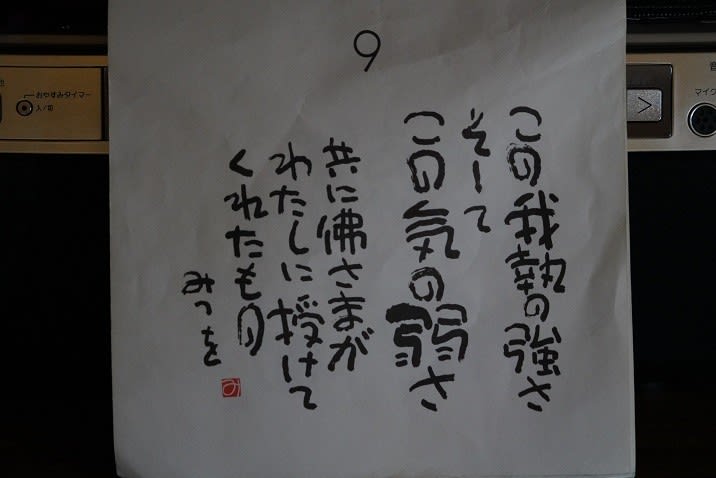先程、ヤフージャパンから配信された記事を見ている中、
『 「血栓」を溶かし、つくらないために食べたい4大食品【血栓をつくらない!】 』、
と題された見出しを見たりした。
私は東京の調布市に住む年金生活の78歳の身であるが、
『 「血栓」を溶かし、つくらないために食べたい4大食品【血栓をつくらない!】 』、
と題された見出しを見たりした。
私は東京の調布市に住む年金生活の78歳の身であるが、
私より5歳若い家内と共に、雑木の多い小庭の中で、
古ぼけた戸建てに住み、ささやかに過ごしている。
古ぼけた戸建てに住み、ささやかに過ごしている。
こうした中、私は恥ずかしながら糖尿病の予備軍であり、
過ぎし年に、心臓の痛みで救急車で病院に搬送されたこともあり、
何かと「血栓」には注視している。
今回、《・・「血栓」を溶かし、つくらないために食べたい4大食品・・》、
真摯に学びたく、記事を読んでしまった・・。
この記事は、【サライ.jp】に掲載された記事で、2月12日に配信され、
無断であるが、記事を転載させて頂く。
《・・ 脳梗塞、心筋梗塞、肺塞栓など、突然症状が起き、
短時間のうちに亡くなってしまう“突然死”。
糖尿病治療の名医であり、生活習慣病の予防にも詳しい医学博士・板倉弘重先生によると、
その要因のひとつとなるのが、血管にできるかたまり“血栓”だといいます。
ですが、その血栓は、外から見ただけではわからず、
自覚症状もありません。
だからこそ、血栓を予防することや、
できても溶かして、流すことがとても重要になります。

そこで今回は、板倉先生監修の『血栓をつくらない!』(宝島社)から、
血栓をつくらない&できた血栓を溶かすために、
積極的に食べたい4大食品をご紹介します。 監修/板倉弘重
短時間のうちに亡くなってしまう“突然死”。
糖尿病治療の名医であり、生活習慣病の予防にも詳しい医学博士・板倉弘重先生によると、
その要因のひとつとなるのが、血管にできるかたまり“血栓”だといいます。
ですが、その血栓は、外から見ただけではわからず、
自覚症状もありません。
だからこそ、血栓を予防することや、
できても溶かして、流すことがとても重要になります。

そこで今回は、板倉先生監修の『血栓をつくらない!』(宝島社)から、
血栓をつくらない&できた血栓を溶かすために、
積極的に食べたい4大食品をご紹介します。 監修/板倉弘重
【納豆】ナットウキナーゼが血栓だけを溶かす!
◆1日1パックの納豆で突然死リスクを減らす
国立がん研究センターなどが実施している「JPHC研究」で、
発酵性大豆食品の摂取が多い人は、
循環器疾患の死亡リスクが低いという研究結果が発表されました。
大豆の発酵食品とは、味噌や納豆。
この 「JPHC研究」研究では、
1日に発酵性大豆食品を50g(納豆1パック程度)食べている人は、
ほとんど食べない人に比べて、
循環器疾患の死亡リスクが10%低いそうです。
納豆のネバネバには、
ナットウキナーゼというたんぱく質分解酵素が含まれています。
このナットウキナーゼが、血栓のおもな成分であるフィブリンを分解したり、
血液をサラサラにしてくれる効果があるのです。
血栓ができやすいのは夜、寝ている間なので、
夕食に納豆を1パック食べるのがおすすめです。
納豆は、食物繊維やたんぱく質、カルシウムなど栄養面でも
優れた食品ですから、ぜひ日々の食習慣に取り入れましょう。

◆血栓に効く! 納豆の食べ方
・食べるなら夜が効果的
・タレは混ぜたあとにかける
・1日1パック(50g)を目安に食べよう
・加熱はしないほうが血栓には効く
国立がん研究センターなどが実施している「JPHC研究」で、
発酵性大豆食品の摂取が多い人は、
循環器疾患の死亡リスクが低いという研究結果が発表されました。
大豆の発酵食品とは、味噌や納豆。
この 「JPHC研究」研究では、
1日に発酵性大豆食品を50g(納豆1パック程度)食べている人は、
ほとんど食べない人に比べて、
循環器疾患の死亡リスクが10%低いそうです。
納豆のネバネバには、
ナットウキナーゼというたんぱく質分解酵素が含まれています。
このナットウキナーゼが、血栓のおもな成分であるフィブリンを分解したり、
血液をサラサラにしてくれる効果があるのです。
血栓ができやすいのは夜、寝ている間なので、
夕食に納豆を1パック食べるのがおすすめです。
納豆は、食物繊維やたんぱく質、カルシウムなど栄養面でも
優れた食品ですから、ぜひ日々の食習慣に取り入れましょう。

◆血栓に効く! 納豆の食べ方
・食べるなら夜が効果的
・タレは混ぜたあとにかける
・1日1パック(50g)を目安に食べよう
・加熱はしないほうが血栓には効く
◆納豆と一緒に食べたい食材
◎納豆+大葉
納豆にはビタミンKが含まれ、大葉にはビタミンC・E、β-カロテンが豊富。
組み合わせることで、ビタミンバランスがよくなります。
また、大葉のポリフェノールの抗酸化作用で、血管を若々しく保ちます。
◎納豆+大葉
納豆にはビタミンKが含まれ、大葉にはビタミンC・E、β-カロテンが豊富。
組み合わせることで、ビタミンバランスがよくなります。
また、大葉のポリフェノールの抗酸化作用で、血管を若々しく保ちます。
◎納豆+酢
どちらも血栓対策におすすめの食品。
酢と一緒に摂ることで、納豆に含まれる鉄分の吸収率がアップ。
高血圧や高血糖、高コレステロールなど血栓の原因となる生活習慣病の予防になります。
どちらも血栓対策におすすめの食品。
酢と一緒に摂ることで、納豆に含まれる鉄分の吸収率がアップ。
高血圧や高血糖、高コレステロールなど血栓の原因となる生活習慣病の予防になります。
◎納豆+キムチ
発酵食品同士の組み合わせで、
キムチに含まれる乳酸菌と納豆菌がいい相乗効果をもたらし、
腸内環境を整えてくれます。
キムチに含まれる唐辛子には、血行を促すカプサイシンも含まれています。
キムチに含まれる乳酸菌と納豆菌がいい相乗効果をもたらし、
腸内環境を整えてくれます。
キムチに含まれる唐辛子には、血行を促すカプサイシンも含まれています。

【玉ねぎ】血液をサラサラにして血栓予防
細胞を傷つける活性酸素から血管を守るケルセチンが含まれています。
ケルセチンは、ポリフェノールの一種で、
身の黄色い色素部分や皮に豊富にあります。
血管拡張の働きをする一酸化窒素を邪魔する活性酸素をとらえてくれ、
血管のダメージを抑えてくれます。
また、血栓を溶かしてくれる作用をもつ硫化アリル、
その一種で血管の壁を柔軟に保つ働きのあるアリシンなど、血栓予防、
できた血栓を溶かす、動脈効果予防など、血管にさまざまな
いい影響をもたらしてくれる血液サラサラ&血管強化食材の代表です。
栄養を効率よく摂取するなら、
1日50g(1/4個)を目安に、生で食べるのがおすすめ。
水にさらすとケルセチンが溶けてしまいます。
生で食べる際には極力水にさらさず、
加熱する場合はスープごといただくようにしましょう。
皮はお茶にすることで、ケルセチンを効率よく摂取できます。
玉ねぎの食べ方
・水には極力さらさない
・みじん切りがベスト
・加熱する際は油で炒める
・1日50g(1/4個)食べよう

赤玉ねぎ
◆納豆と一緒に食べたい食材アリシンを含む野菜
アリシンは、ねぎ類に含まれるにおいと辛味成分ですから、
玉ねぎだけではなく、長ねぎやにんにくなどにも含まれています。
赤玉ねぎ
玉ねぎにふくまれるアリシンやケルセチンに加え、
赤紫色の色素アントシアニンの抗酸化力でダブルの効果が期待できます。
アリシンは、ねぎ類に含まれるにおいと辛味成分ですから、
玉ねぎだけではなく、長ねぎやにんにくなどにも含まれています。
赤玉ねぎ
玉ねぎにふくまれるアリシンやケルセチンに加え、
赤紫色の色素アントシアニンの抗酸化力でダブルの効果が期待できます。
◆クエン酸は、フルーツからも補える
酢には、クエン酸も含まれています。
クエン酸は、お掃除でもカルキや水アカを落としてくれますが、
体内では血管内に溜まった余分なカルシウムを溶かしてくれる効果が。
クエン酸は、レモンやライムなど柑橘系にも多いので、
お酢と合わせて日々の食事にぜひ取り入れましょう。
酢には、クエン酸も含まれています。
クエン酸は、お掃除でもカルキや水アカを落としてくれますが、
体内では血管内に溜まった余分なカルシウムを溶かしてくれる効果が。
クエン酸は、レモンやライムなど柑橘系にも多いので、
お酢と合わせて日々の食事にぜひ取り入れましょう。

【フィッシュオイル】
血栓・動脈硬化を予防するDHA・EPAが豊富!
◆血管年齢を下げる毎日食べたい青魚
さばやさんま、あじなど青魚に含まれる多価不飽和脂肪酸のEPA(エイコサペンタエン酸)、
DHA(ドコサヘキサエン酸)は、血流をよくし、
血管の健康維持に欠かせない脂質です。
EPA(エイコサペンタエン酸)は、
血液の粘度を下げて血栓をできにくくし、
動脈硬化を予防してくれる働きがあり、
足の血栓症予防の薬として認可されています。
そして、このEPAの働きを高めるのがDHA(ドコサヘキサエン酸)で、
中性脂肪を減らす働きや脳を活発する効果もあります。
EPAやDHAは、熱に弱い油なので、
生のまま食べるのが一番効率のよい摂取法です。
加熱する際は、油が下に落ちてしまう魚焼きグリルより、
小麦粉などをまぶしてフライパンで焼くほうが油を逃さずに調理できます。
また、魚の缶詰やしらすも、手軽にEPAやDHAが摂取できます。
EPAやDHAが含まれているサプリメントもありますので、
魚が苦手な人は活用するのも手です。

◆血栓に効く! 魚の油のとり方
・朝に食べるのがおすすめ!
・油を逃さない調理を
・1日1g(刺身5切れ程度)
・缶詰も賢く利用しよう
さばやさんま、あじなど青魚に含まれる多価不飽和脂肪酸のEPA(エイコサペンタエン酸)、
DHA(ドコサヘキサエン酸)は、血流をよくし、
血管の健康維持に欠かせない脂質です。
EPA(エイコサペンタエン酸)は、
血液の粘度を下げて血栓をできにくくし、
動脈硬化を予防してくれる働きがあり、
足の血栓症予防の薬として認可されています。
そして、このEPAの働きを高めるのがDHA(ドコサヘキサエン酸)で、
中性脂肪を減らす働きや脳を活発する効果もあります。
EPAやDHAは、熱に弱い油なので、
生のまま食べるのが一番効率のよい摂取法です。
加熱する際は、油が下に落ちてしまう魚焼きグリルより、
小麦粉などをまぶしてフライパンで焼くほうが油を逃さずに調理できます。
また、魚の缶詰やしらすも、手軽にEPAやDHAが摂取できます。
EPAやDHAが含まれているサプリメントもありますので、
魚が苦手な人は活用するのも手です。

◆血栓に効く! 魚の油のとり方
・朝に食べるのがおすすめ!
・油を逃さない調理を
・1日1g(刺身5切れ程度)
・缶詰も賢く利用しよう
魚を毎日食べるコツ
◆魚を毎日食べるコツ 魚は、
「下ごしらえや調理が面倒」とおっくうになりがちですが、
手軽に摂取する方法もたくさん。
代表的なのは缶詰。
また、しらすはイワシなどの稚魚で、DHA・EPAを含んでいますので、
料理に混ぜたりかけたりしてプラスしましょう。・・ 》
「下ごしらえや調理が面倒」とおっくうになりがちですが、
手軽に摂取する方法もたくさん。
代表的なのは缶詰。
また、しらすはイワシなどの稚魚で、DHA・EPAを含んでいますので、
料理に混ぜたりかけたりしてプラスしましょう。・・ 》
注)記事の原文に、あえて改行を多くした。


今回、糖尿病治療の名医、生活習慣病の予防にも精通されている板倉弘重さんの監修で
《・・「血栓」を溶かし、つくらないために食べたい4大食品・・》を学び、
78歳の私は遅ればせながら学び、多々教示させられながら、
微笑んでしまった。
私は既に納豆、青魚の代わりにサバの味噌煮の缶詰、
玉ネギなど愛食しているので、
そうですよねぇ・・と微笑み返しをしてしまった。
しかしながら、苦手なキムチは敬遠しているので、
代わりに何か・・と思案したりしている。

いずれにしても、もとより健康でなければ、自身の日頃のささやかな願いも叶わないので、
歩くことが何より健康体の源(みなもと)と思い、そして適度な熟睡する睡眠、或いは程ほどの食事が、
セカンドライフの私なりの健康体の三種の神器として思い、年金生活を丸18年を過ごしてきた。
そして好奇心をなくしたらこの世は終わりだ、と信条している私は、
体力の衰えを感じている私でも、その時に応じて溌剌とふるまったりしている。
《・・「血栓」を溶かし、つくらないために食べたい4大食品・・》を学び、
78歳の私は遅ればせながら学び、多々教示させられながら、
微笑んでしまった。
私は既に納豆、青魚の代わりにサバの味噌煮の缶詰、
玉ネギなど愛食しているので、
そうですよねぇ・・と微笑み返しをしてしまった。
しかしながら、苦手なキムチは敬遠しているので、
代わりに何か・・と思案したりしている。

いずれにしても、もとより健康でなければ、自身の日頃のささやかな願いも叶わないので、
歩くことが何より健康体の源(みなもと)と思い、そして適度な熟睡する睡眠、或いは程ほどの食事が、
セカンドライフの私なりの健康体の三種の神器として思い、年金生活を丸18年を過ごしてきた。
そして好奇心をなくしたらこの世は終わりだ、と信条している私は、
体力の衰えを感じている私でも、その時に応じて溌剌とふるまったりしている。
こうした中で、70歳の頃から体力の衰えを実感し、
ときおり物忘れもあり、独り微苦笑をしたりしている。
このような私でも、あと1年半少しで・・80歳の誕生日を迎える時に、
何とか健康寿命で迎えたい、と念願している。