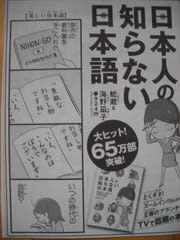(写真は新聞広告から転載。 写真をクリックしていただきますと少し大きくなります。)
私など人に贈り物をする時には今尚、今回の表題の「つまらないものですが、どうかお受け取り下さい…」等々、ついつい口にしてしまう世代の人間である。
ところが残念なことに現在の日本の若い世代の人々の間では、この手の言葉は既に死語化していて奇異な表現であるらしいのだ。
上記写真は現在65万部突破!大ヒット中という漫画本の新聞広告を写したものであるが、「日本人の知らない日本語」と題したこの漫画本の広告の中に一つの4コマ漫画が掲載されていた。
いつもながら写真が見づらいため( )、以下にこの4コマ漫画の内容を文章にて紹介しよう。
)、以下にこの4コマ漫画の内容を文章にて紹介しよう。
登場人物の若い女性が海外で使用されている“日本語会話例文集”を手に入れたのだが、その中に以下の日本語会話が記載されている。
「素敵なお召し物ですね」
「いえ、こんなのは“ぼろ”でございます」
それを見た若い女性が「いつの時代の会話?」と驚き、焦りおののく… 、といったごとくの内容である。
この広告の4コマ漫画を見て、驚いたのは私の方である。
と言うのも冒頭に既述の通り、私などこれに類似した会話は日常茶飯事であるからだ。“ぼろ”とまでは言わずとも、会話の相手から「あら、素敵な洋服ね」などと褒められると、ついつい「大したことないわ。安物なのよ~」なんて咄嗟に反応するのは、一種の礼儀と私は心得ているのだけれど…
いや、相手と親しい間柄であるならば「ちょっと奮発したのよ~」などと本音の会話にもなろう。 一方、懇親の仲でもない相手に対しては褒められた御礼こそ素直に伝えても、まさか子どもじゃあるまいし、「これ、高価なんですよ~」等と声高々に応じる単細胞人間は日本では少数派なのではなかろうか??
皆さんはいかがであろう。
しかもこの漫画本の題名が「日本人の知らない日本語」ときている。
広告だけ見て本の中身を読まずしてブログでコメントするのも筆者に対して失礼な話だが、上記の会話のごとくの日本の伝統でもある“謙遜の文化”が、若い世代に「知らない日本語」と明瞭に表現されるほど現代日本社会は廃れ去っているのであろうか??
話が変わって、たまたま本日(10月7日)、NHK昼間の番組「スタジオパーク」にフリーキャスターのジョン・カビラ氏が出演し、氏の日本語と英語のバイリンガル人生についてトークを繰り広げているのを見聞した。
そのトークの中で、日本の“謙遜の文化”について触れ、氏の日本人である父親に対してはずっと謙譲語あるいは丁寧語を使い続ける人生である旨語られていたのが興味深かったものだ。
ジョン・カビラ氏に限らず、諸外国の人々にとって日本の“謙遜の文化”は今や世界的に既存の事実であり、自国にはないその文化を高く評価する諸外国からの風潮に私は今まで多く触れてきている。 日本人の謙遜の礼儀とハートを自分は好むと言う諸外国の人々からの賞賛を、今までに私は何度も経験してきているのだ。
今回の広告4コマ漫画の“ぼろ”の表現は極端で誰しも驚くであろうが(これは漫画ゆえにデフォルメした表現であり、日常的には使用されない言葉であろうと私は捉えているのだが)、自己を謙(へりくだ)る時に「つまらないもの」等の否定的表現を用いることが謙る場面での単なる“慣習”であることを社会的合意として一旦理解出来たならば、それは既に“美学”の域に達しているのである。
そのような我が国の伝統的文化である謙遜の美学が、次世代からけんもほろろに「知らない」と驚かれ否定される程受け継がれていないとすれば、既に何の取り得もなくなりつつあるこの日本は、今後一体何を目指せばよいのであろうか?
「つまらないもの」と言う言葉を真に「つまらないもの」と受け取る単細胞さで自分本位に世渡りするのではなく、一人ひとりがその時の空気を客観的に読める繊細さを備え、その言葉に相手の思慮深さを慮り、謙遜の文化を次世代まで継承できる日本社会でありたいものである。




私など人に贈り物をする時には今尚、今回の表題の「つまらないものですが、どうかお受け取り下さい…」等々、ついつい口にしてしまう世代の人間である。
ところが残念なことに現在の日本の若い世代の人々の間では、この手の言葉は既に死語化していて奇異な表現であるらしいのだ。
上記写真は現在65万部突破!大ヒット中という漫画本の新聞広告を写したものであるが、「日本人の知らない日本語」と題したこの漫画本の広告の中に一つの4コマ漫画が掲載されていた。
いつもながら写真が見づらいため(
 )、以下にこの4コマ漫画の内容を文章にて紹介しよう。
)、以下にこの4コマ漫画の内容を文章にて紹介しよう。登場人物の若い女性が海外で使用されている“日本語会話例文集”を手に入れたのだが、その中に以下の日本語会話が記載されている。
「素敵なお召し物ですね」
「いえ、こんなのは“ぼろ”でございます」
それを見た若い女性が「いつの時代の会話?」と驚き、焦りおののく… 、といったごとくの内容である。
この広告の4コマ漫画を見て、驚いたのは私の方である。

と言うのも冒頭に既述の通り、私などこれに類似した会話は日常茶飯事であるからだ。“ぼろ”とまでは言わずとも、会話の相手から「あら、素敵な洋服ね」などと褒められると、ついつい「大したことないわ。安物なのよ~」なんて咄嗟に反応するのは、一種の礼儀と私は心得ているのだけれど…
いや、相手と親しい間柄であるならば「ちょっと奮発したのよ~」などと本音の会話にもなろう。 一方、懇親の仲でもない相手に対しては褒められた御礼こそ素直に伝えても、まさか子どもじゃあるまいし、「これ、高価なんですよ~」等と声高々に応じる単細胞人間は日本では少数派なのではなかろうか??

皆さんはいかがであろう。
しかもこの漫画本の題名が「日本人の知らない日本語」ときている。
広告だけ見て本の中身を読まずしてブログでコメントするのも筆者に対して失礼な話だが、上記の会話のごとくの日本の伝統でもある“謙遜の文化”が、若い世代に「知らない日本語」と明瞭に表現されるほど現代日本社会は廃れ去っているのであろうか??

話が変わって、たまたま本日(10月7日)、NHK昼間の番組「スタジオパーク」にフリーキャスターのジョン・カビラ氏が出演し、氏の日本語と英語のバイリンガル人生についてトークを繰り広げているのを見聞した。
そのトークの中で、日本の“謙遜の文化”について触れ、氏の日本人である父親に対してはずっと謙譲語あるいは丁寧語を使い続ける人生である旨語られていたのが興味深かったものだ。
ジョン・カビラ氏に限らず、諸外国の人々にとって日本の“謙遜の文化”は今や世界的に既存の事実であり、自国にはないその文化を高く評価する諸外国からの風潮に私は今まで多く触れてきている。 日本人の謙遜の礼儀とハートを自分は好むと言う諸外国の人々からの賞賛を、今までに私は何度も経験してきているのだ。
今回の広告4コマ漫画の“ぼろ”の表現は極端で誰しも驚くであろうが(これは漫画ゆえにデフォルメした表現であり、日常的には使用されない言葉であろうと私は捉えているのだが)、自己を謙(へりくだ)る時に「つまらないもの」等の否定的表現を用いることが謙る場面での単なる“慣習”であることを社会的合意として一旦理解出来たならば、それは既に“美学”の域に達しているのである。
そのような我が国の伝統的文化である謙遜の美学が、次世代からけんもほろろに「知らない」と驚かれ否定される程受け継がれていないとすれば、既に何の取り得もなくなりつつあるこの日本は、今後一体何を目指せばよいのであろうか?
「つまらないもの」と言う言葉を真に「つまらないもの」と受け取る単細胞さで自分本位に世渡りするのではなく、一人ひとりがその時の空気を客観的に読める繊細さを備え、その言葉に相手の思慮深さを慮り、謙遜の文化を次世代まで継承できる日本社会でありたいものである。