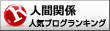主日礼拝 イザヤ1・10-20
お帰りなさい。七日の旅路を守られ主の礼拝へと導かれましたことを感謝します。
先週はノーベル物理学賞に日本人三人の方々が受賞されました。又ノーベル平和賞の発表もあり日本国憲法9条がとれなかったのは残念でしたね。しかし、すべての子供の教育を受ける権利のために危険を顧みず活動するパキスタンの女子青年マララさん17歳と、インドで不当に就労させられている子供たちの解放を支援する活動を長きに亘り続けてこられたサティアルティさんが受賞されました。素晴らしいですよね。お二人の受賞は、多くの人々にインパクトを与え、平和な世界が築かれるため人がどうあるべきかを考えさせてくれるよい機会となりましたことに感謝したいと思います。
また、先週に引き続き台風19号接近しているということで今回は非常に大型と聞いております。風も強まっていますが、その影響が気がかりです。どうか大きな被害が出ませんようお祈りいたしましょう。
さて、本日はイザヤ書1章から「神の告発と招き」と題し、御言葉を聞いていきたいと思います。この「告発」ということで、先週は二つの出来事に目が留まりました。
一つは、アスベスト公害についての被害者の方々の「告発」です。最高裁がその訴えを認め、国に過ちがあったとの判決を下したというニュースでした。もっと早い対策がとられていれば、という被害者の方々の訴えは、人のいのちよりも経済成長を最優先にしてきた日本の国と社会に対する「告発」です。そしてもう一つは、香港の学生たちによるデモです。真の開かれた選挙が行われるために非暴力で訴えている彼らに向かって催榴弾を投じ力で制圧しようとしている為政者たち。学生たちの叫びは民主的な選挙を認めようとしない権力の横暴に対する「告発」であります。正義はどこにあるのか?今の時代の私たち自身、「告発」する者であり、「告発」される者でもあります。そんな思いでこのイザヤ書をご一緒にひもといていきたいと考えております。
先週は6章より預言者イザヤの召命の記事を読みました。彼はその時、主の臨在に触れ、主の御使いらが「聖なるかな」と、その栄光を賛美するのを聞くのでありますが。イザヤは御使いらと共に主を賛美することができませんでした。それは、ユダの国の民を裁き、断罪した自分もまたその罪人の一人であることを思い知らされたからです。
イザヤは「わたしは汚れた唇の者。汚れた唇の民の中に住む者」、もう自分は滅される者でしかない、とその罪を主に告白するのであります。しかし主は、その罪を告白するイザヤの咎と罪を赦し、主の預言者として立て民のもとへ派遣していく、というそのようなエピソードでありました。
大事なことは、イザヤ自身もまた唇の汚れた者である、という罪の自覚をもって主の言葉を伝えるか否かによって全くそのメッセージの内容が変わってくるということです。自分は彼らのようではない、とか。彼らはどうして改めないのか、というように。自分は高い所から又、外側からの視線で人を裁き、断罪するのであればそれは偽善そのものになります。私たちもまたイザヤが真に主に立ち帰って、新しく生まれ変わったように、主と相対して、いつも自分の立ち位置を確認しながら、主の御業に励んでいきたいと思います。
ところで、本日1章のイザヤに臨んだ「ユダの審判」から始まります主の語られた御言葉自体は間違いないもの、揺るがぬ真実でありました。それは天の法廷さながらであり、被告のユダに向けて、原告である神さまが「告発」なさっているという大変厳粛な場面であります。その神の告発の中心は、ユダの礼拝(祭儀)にありました。
主なる神さまは11節以降で次のように厳しくユダを告発します。
「お前たちのささげる多くのいけにえが わたしにとって何になろうか。雄羊や肥えた獣の脂肪の献げ物に わたしは飽いた。雄牛、小羊、雄山羊の血をわたしは喜ばない。こうしてわたしの顔を仰ぎ見に来るが 誰がお前たちにこれらのものを求めたのか わたしの庭を踏み荒らす者よ。」 大変厳しいお言葉であります。さらに続けて「むなしい献げ物を再び持って来るな。香の煙はわたしの忌み嫌うもの。新月祭、安息日、祝祭など 災いを伴う集いにわたしは耐ええない。お前たちの新月祭や、定められた日の祭を わたしは憎んでやまない。それはわたしにとって、重荷でしかない。それを担うのに疲れ果てた。お前たちが手を広げて祈っても、わたしは目を覆う。どれほどの祈りを繰り返しても、決して聞かない。」どうして彼らの礼拝を神さまはこんなにも嫌がられたのでしょう。それには2つのことを知る必要があります。1つは、これらの告発を受けたのは、ユダのエルサレムに住む権力者や富める人たちであったということです。もう1つは、彼らの繁栄が社会的に弱い立場におかれた人々の上に成り立つものであったという事です。
ウジヤ王の治世下、ユダの国は経済的に繁栄します。そういう中で、神殿では数多くの献げものがささげられます。ところが、エルサレムの神殿から一歩出た社会では、その豊かさとは裏腹に生活困窮者があふれかえっていました。この神さまのお言葉は「礼拝」を行う事そのものを否定されたということではありません。神さまは「礼拝」を捧げている一人ひとりの実際の生き方を、ここで問うておられるのです。神を礼拝していると言っても、実際に神の愛と赦しをもって、それぞれの生かされている場に恵みを受けた者として相応しい歩みがなされていないのなら、献げもの、いけにえも虚しいではないか、と嘆いておられるのです。
主なる神さまは15節以降で次のように言われます。
「お前たちの血にまみれた手を 洗って清くせよ。悪い行いをわたしの目の前から取り除け。悪を行うことをやめ 善を行うことを学び 裁きをどこまでも実行して 搾取する者を凝らし、孤児の権利を守り やもめの訴えを弁護せよ。」
このウジヤ王の時代は、経済成長を遂げるその一方で社会の階級化が進んでいき、神殿で礼拝をする者たちの大半は裕福で経済力や地位のある者たちであったことが推測されます。繁栄とその豊かさに酔いしれる彼らの心は鈍くなり、神殿の祭儀や礼拝はもはや彼らに神の救いと戒めとを思い起こさせるものとはならなかったのです。結果、不正や搾取がまかり通り、社会的に弱い立場におかれた人たちが顧みられる事はありません。
話は変わりますが、日本の敗戦後の焼け野原から再生し、経済成長を遂げてきたのは今の後期高齢者の方々でありますが、さらに経済、産業を底支えしてきたのは人手不足の最中、よせばと呼ばれる釜崎や山谷での日雇い労働者の方々であったことを、決して忘れてはならないことを、私は20数年前大阪に来たときにその歴史と実体を遅まきながら知らされたのですが。今日もまた、原発事故後の過酷な処理作業のために、釜ヶ崎からフクシマに雇われ使い捨てのようにされていく生活困窮者の方々がおられ、そのような現状にも拘わらず原発再稼働に向け、事故の際誰がその収拾のために働くのかあてもないまま事を進めようとする人たちがいるという現実であります。過酷な負担や危険を弱い立場のおかれた人に負わせている社会の構図を知るとき、イザヤではありませんが、「ああ本当に私たち人間は罪深い。なんと罪深いのか」と思い知らされるのであります。同じ過ちを繰り返さないために、やはり再稼働は人の道理に反すると思います。
話を戻しますが。主なる神さまは、16節以降で「悪い行いをわたしの目から取り除け。悪を行うことをやめ、裁きをどこまでも実行して 搾取する者を凝らし 孤児の権利を守りやもめの訴えを弁護するように」と命じます。
先程も言いましたが。これはユダにおいていわゆる地位や立場のある祭司、預言者、役人、地主や商業主の人たちに向けられた言葉であります。主が彼らに求められるのは「自己吟味の徹底」であります。1章2節以降に「わたしは子らを育てて大きくした。しかし、彼らはわたしに背いた。牛は飼い主を知り らばは主人の飼い葉桶を知っている。しかし、イスラエルは知らず わたしの民(ユダの民)は見分けない」と主が指摘しているように、イスラエルの民のルーツは、もとは小さく貧しい民であり、奴隷のように扱われ、寄留者であったのに、主なる神さまが、そのさまよい行く小さきイスラエルを選び、モーセを通して解放させられたうえに、このユダの人々が存在しているということであります。それは、ただ神の憐れみ以外の何ものでもなかったということを、忘れてはならないということです。ユダの人々は、その神の憐れみをもって神と人を愛して生きることが、期待されているのです。
また、主は、ユダの虐げられる生活困窮者の訴えに耳を傾けておられ、その苦悩や痛みをご存じであられます。しかし人はなかなか他の人の苦悩や痛みに気づくことができません。このイザヤの時代から700年余りの時を経て、遂にメシヤ、救い主がお生まれになります。イザヤ書53章にはそのメシヤは輝かしい風格も好ましい容姿もなく、彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。そのようなお方として来られると預言されています。それは、神さま自ら苦悩と痛みを負う者となられた、ということであります。私たちはこのメシヤ、イエス・キリストを通して、苦しみ痛む人に寄り添い、共に歩まれる神さまを見、私たち自身もこの慰めと励ましのうちに隣人の痛みに無関心でいることがないように促されるのであります。
さてそして、今日の箇所の中心部分である18節以降を読んでみたいと思います。
「論じ合おうではないか、と主は言われる。たとえ、お前たちの罪が緋のようでも 雪のように白くなることができる。たとえ、紅のようであっても 羊の毛のようになることができる。お前たちが進んで従うなら 大地の実りを食べることができる。かたくなに背くなら、剣の餌食となる。主の口がこう宣言される。」
これは単に、議論や討論をすることが大事ということを言っているのではありません。私たちは互いに論じ合うとき、お互いに向き合って顔と顔、目と目を合わせ会話します。そのように神と私が向き合う姿勢を神さまは求めておられるということです。
それは真に神に立ち返って生きる、ということでもあります。そこに「たとえ、お前たちの罪が緋のようでも雪のように白くなることができる。たとえ、紅のようであっても 羊の毛のようになることができる」という驚くばかりの恵みが、与えられるのです。それはまさに、私どもにとりましてはイエス・キリストの贖いであります。
主なる神さまは、ユダの人々に「わたしと向き合って生きるように」と招かれ、主に自ら進んで従う中に、ユダの民の祝福があることを大地の実りにたとえて示されます。
主イエスの十字架の贖いによる赦しと救いを受けた私たちも又、今日の箇所は決して耳ざわりのよい話ではないでしょう。しかしイエス・キリストの愛と救いが、主の大きな自己犠牲の上に与えられているものであることを知るとき、私たちもまた、「主の告発と招き」に謙遜に耳を傾ける者でありたい、と願う者であります。
今日は「神の告発と招き」と題し、御言葉を聞いてきました。
主は罪人を断罪するために告発されたのではありません。それはユダの人々、この地上の人々が真の神さまに立ち返り、愛と憐れみの救いに与り、その喜びをもって恵みに相応しく生き、真の幸いを得ることを何よりも願っておられるのです。
最後にヨハネ3章16-17節を読んで宣教を閉じたいと思います。
「神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。」
今週も主の救いの招きの言葉をもって世に遣わされてまいりましょう。
お帰りなさい。七日の旅路を守られ主の礼拝へと導かれましたことを感謝します。
先週はノーベル物理学賞に日本人三人の方々が受賞されました。又ノーベル平和賞の発表もあり日本国憲法9条がとれなかったのは残念でしたね。しかし、すべての子供の教育を受ける権利のために危険を顧みず活動するパキスタンの女子青年マララさん17歳と、インドで不当に就労させられている子供たちの解放を支援する活動を長きに亘り続けてこられたサティアルティさんが受賞されました。素晴らしいですよね。お二人の受賞は、多くの人々にインパクトを与え、平和な世界が築かれるため人がどうあるべきかを考えさせてくれるよい機会となりましたことに感謝したいと思います。
また、先週に引き続き台風19号接近しているということで今回は非常に大型と聞いております。風も強まっていますが、その影響が気がかりです。どうか大きな被害が出ませんようお祈りいたしましょう。
さて、本日はイザヤ書1章から「神の告発と招き」と題し、御言葉を聞いていきたいと思います。この「告発」ということで、先週は二つの出来事に目が留まりました。
一つは、アスベスト公害についての被害者の方々の「告発」です。最高裁がその訴えを認め、国に過ちがあったとの判決を下したというニュースでした。もっと早い対策がとられていれば、という被害者の方々の訴えは、人のいのちよりも経済成長を最優先にしてきた日本の国と社会に対する「告発」です。そしてもう一つは、香港の学生たちによるデモです。真の開かれた選挙が行われるために非暴力で訴えている彼らに向かって催榴弾を投じ力で制圧しようとしている為政者たち。学生たちの叫びは民主的な選挙を認めようとしない権力の横暴に対する「告発」であります。正義はどこにあるのか?今の時代の私たち自身、「告発」する者であり、「告発」される者でもあります。そんな思いでこのイザヤ書をご一緒にひもといていきたいと考えております。
先週は6章より預言者イザヤの召命の記事を読みました。彼はその時、主の臨在に触れ、主の御使いらが「聖なるかな」と、その栄光を賛美するのを聞くのでありますが。イザヤは御使いらと共に主を賛美することができませんでした。それは、ユダの国の民を裁き、断罪した自分もまたその罪人の一人であることを思い知らされたからです。
イザヤは「わたしは汚れた唇の者。汚れた唇の民の中に住む者」、もう自分は滅される者でしかない、とその罪を主に告白するのであります。しかし主は、その罪を告白するイザヤの咎と罪を赦し、主の預言者として立て民のもとへ派遣していく、というそのようなエピソードでありました。
大事なことは、イザヤ自身もまた唇の汚れた者である、という罪の自覚をもって主の言葉を伝えるか否かによって全くそのメッセージの内容が変わってくるということです。自分は彼らのようではない、とか。彼らはどうして改めないのか、というように。自分は高い所から又、外側からの視線で人を裁き、断罪するのであればそれは偽善そのものになります。私たちもまたイザヤが真に主に立ち帰って、新しく生まれ変わったように、主と相対して、いつも自分の立ち位置を確認しながら、主の御業に励んでいきたいと思います。
ところで、本日1章のイザヤに臨んだ「ユダの審判」から始まります主の語られた御言葉自体は間違いないもの、揺るがぬ真実でありました。それは天の法廷さながらであり、被告のユダに向けて、原告である神さまが「告発」なさっているという大変厳粛な場面であります。その神の告発の中心は、ユダの礼拝(祭儀)にありました。
主なる神さまは11節以降で次のように厳しくユダを告発します。
「お前たちのささげる多くのいけにえが わたしにとって何になろうか。雄羊や肥えた獣の脂肪の献げ物に わたしは飽いた。雄牛、小羊、雄山羊の血をわたしは喜ばない。こうしてわたしの顔を仰ぎ見に来るが 誰がお前たちにこれらのものを求めたのか わたしの庭を踏み荒らす者よ。」 大変厳しいお言葉であります。さらに続けて「むなしい献げ物を再び持って来るな。香の煙はわたしの忌み嫌うもの。新月祭、安息日、祝祭など 災いを伴う集いにわたしは耐ええない。お前たちの新月祭や、定められた日の祭を わたしは憎んでやまない。それはわたしにとって、重荷でしかない。それを担うのに疲れ果てた。お前たちが手を広げて祈っても、わたしは目を覆う。どれほどの祈りを繰り返しても、決して聞かない。」どうして彼らの礼拝を神さまはこんなにも嫌がられたのでしょう。それには2つのことを知る必要があります。1つは、これらの告発を受けたのは、ユダのエルサレムに住む権力者や富める人たちであったということです。もう1つは、彼らの繁栄が社会的に弱い立場におかれた人々の上に成り立つものであったという事です。
ウジヤ王の治世下、ユダの国は経済的に繁栄します。そういう中で、神殿では数多くの献げものがささげられます。ところが、エルサレムの神殿から一歩出た社会では、その豊かさとは裏腹に生活困窮者があふれかえっていました。この神さまのお言葉は「礼拝」を行う事そのものを否定されたということではありません。神さまは「礼拝」を捧げている一人ひとりの実際の生き方を、ここで問うておられるのです。神を礼拝していると言っても、実際に神の愛と赦しをもって、それぞれの生かされている場に恵みを受けた者として相応しい歩みがなされていないのなら、献げもの、いけにえも虚しいではないか、と嘆いておられるのです。
主なる神さまは15節以降で次のように言われます。
「お前たちの血にまみれた手を 洗って清くせよ。悪い行いをわたしの目の前から取り除け。悪を行うことをやめ 善を行うことを学び 裁きをどこまでも実行して 搾取する者を凝らし、孤児の権利を守り やもめの訴えを弁護せよ。」
このウジヤ王の時代は、経済成長を遂げるその一方で社会の階級化が進んでいき、神殿で礼拝をする者たちの大半は裕福で経済力や地位のある者たちであったことが推測されます。繁栄とその豊かさに酔いしれる彼らの心は鈍くなり、神殿の祭儀や礼拝はもはや彼らに神の救いと戒めとを思い起こさせるものとはならなかったのです。結果、不正や搾取がまかり通り、社会的に弱い立場におかれた人たちが顧みられる事はありません。
話は変わりますが、日本の敗戦後の焼け野原から再生し、経済成長を遂げてきたのは今の後期高齢者の方々でありますが、さらに経済、産業を底支えしてきたのは人手不足の最中、よせばと呼ばれる釜崎や山谷での日雇い労働者の方々であったことを、決して忘れてはならないことを、私は20数年前大阪に来たときにその歴史と実体を遅まきながら知らされたのですが。今日もまた、原発事故後の過酷な処理作業のために、釜ヶ崎からフクシマに雇われ使い捨てのようにされていく生活困窮者の方々がおられ、そのような現状にも拘わらず原発再稼働に向け、事故の際誰がその収拾のために働くのかあてもないまま事を進めようとする人たちがいるという現実であります。過酷な負担や危険を弱い立場のおかれた人に負わせている社会の構図を知るとき、イザヤではありませんが、「ああ本当に私たち人間は罪深い。なんと罪深いのか」と思い知らされるのであります。同じ過ちを繰り返さないために、やはり再稼働は人の道理に反すると思います。
話を戻しますが。主なる神さまは、16節以降で「悪い行いをわたしの目から取り除け。悪を行うことをやめ、裁きをどこまでも実行して 搾取する者を凝らし 孤児の権利を守りやもめの訴えを弁護するように」と命じます。
先程も言いましたが。これはユダにおいていわゆる地位や立場のある祭司、預言者、役人、地主や商業主の人たちに向けられた言葉であります。主が彼らに求められるのは「自己吟味の徹底」であります。1章2節以降に「わたしは子らを育てて大きくした。しかし、彼らはわたしに背いた。牛は飼い主を知り らばは主人の飼い葉桶を知っている。しかし、イスラエルは知らず わたしの民(ユダの民)は見分けない」と主が指摘しているように、イスラエルの民のルーツは、もとは小さく貧しい民であり、奴隷のように扱われ、寄留者であったのに、主なる神さまが、そのさまよい行く小さきイスラエルを選び、モーセを通して解放させられたうえに、このユダの人々が存在しているということであります。それは、ただ神の憐れみ以外の何ものでもなかったということを、忘れてはならないということです。ユダの人々は、その神の憐れみをもって神と人を愛して生きることが、期待されているのです。
また、主は、ユダの虐げられる生活困窮者の訴えに耳を傾けておられ、その苦悩や痛みをご存じであられます。しかし人はなかなか他の人の苦悩や痛みに気づくことができません。このイザヤの時代から700年余りの時を経て、遂にメシヤ、救い主がお生まれになります。イザヤ書53章にはそのメシヤは輝かしい風格も好ましい容姿もなく、彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。そのようなお方として来られると預言されています。それは、神さま自ら苦悩と痛みを負う者となられた、ということであります。私たちはこのメシヤ、イエス・キリストを通して、苦しみ痛む人に寄り添い、共に歩まれる神さまを見、私たち自身もこの慰めと励ましのうちに隣人の痛みに無関心でいることがないように促されるのであります。
さてそして、今日の箇所の中心部分である18節以降を読んでみたいと思います。
「論じ合おうではないか、と主は言われる。たとえ、お前たちの罪が緋のようでも 雪のように白くなることができる。たとえ、紅のようであっても 羊の毛のようになることができる。お前たちが進んで従うなら 大地の実りを食べることができる。かたくなに背くなら、剣の餌食となる。主の口がこう宣言される。」
これは単に、議論や討論をすることが大事ということを言っているのではありません。私たちは互いに論じ合うとき、お互いに向き合って顔と顔、目と目を合わせ会話します。そのように神と私が向き合う姿勢を神さまは求めておられるということです。
それは真に神に立ち返って生きる、ということでもあります。そこに「たとえ、お前たちの罪が緋のようでも雪のように白くなることができる。たとえ、紅のようであっても 羊の毛のようになることができる」という驚くばかりの恵みが、与えられるのです。それはまさに、私どもにとりましてはイエス・キリストの贖いであります。
主なる神さまは、ユダの人々に「わたしと向き合って生きるように」と招かれ、主に自ら進んで従う中に、ユダの民の祝福があることを大地の実りにたとえて示されます。
主イエスの十字架の贖いによる赦しと救いを受けた私たちも又、今日の箇所は決して耳ざわりのよい話ではないでしょう。しかしイエス・キリストの愛と救いが、主の大きな自己犠牲の上に与えられているものであることを知るとき、私たちもまた、「主の告発と招き」に謙遜に耳を傾ける者でありたい、と願う者であります。
今日は「神の告発と招き」と題し、御言葉を聞いてきました。
主は罪人を断罪するために告発されたのではありません。それはユダの人々、この地上の人々が真の神さまに立ち返り、愛と憐れみの救いに与り、その喜びをもって恵みに相応しく生き、真の幸いを得ることを何よりも願っておられるのです。
最後にヨハネ3章16-17節を読んで宣教を閉じたいと思います。
「神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。」
今週も主の救いの招きの言葉をもって世に遣わされてまいりましょう。