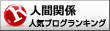主日礼拝宣教 列王記上18章20~40節 (平和をおぼえて)
本日は平和を覚えての礼拝として主に捧げています。
先ほどSさんから戦争体験を通しての貴重な証言・あかしを伺いました。
戦争を知らない世代が増えていくなかにあって、過去の過ちを繰り返さないために
も、実際に戦争をご体験された方からの貴重な証言をお聞きすることができ感謝します。
本日の聖書箇所は、バアルの預言者450人と主の預言者エリヤとの真の神を巡る対決の場面でありますが。アハブ王はエリヤの要請どおりバアルの預言者450人をカルメル山に集めました。
そこでエリヤはすべての民に近づいて問いかけます。
「あなたたちは、いつまでどっちつかずに迷っているのか。もし主が神であるなら、主に従え。もしバアルが神であるなら、バアルに従え。」
ところが「民はひと言も答えなかった」というのです。
それはまさに、民がどっちつかずの状態であったということを表していました。
先週申しましたように、アハブ王は異国の王女イゼベルと政略結婚しました。それにより北イスラエルの地にイゼベルが持ち込んだバアルの神殿を建てて拝んだり、アシュラ像を建立したりとしていくうちにその民たちも惑わされて、主なる神から心が離れていったのです。人々は護国豊穣をもたらすとされるバアルの偶像礼拝をなし、主の目に悪とされることを行っていました。
エリヤは王や民の心が神ならざるものに向かっていることが嘆かわしくてなりません。人々は、主なる神さまを忘れてはいないけれども、バアルも大切だと、まさにどっちつかずの宙ぶらりんの状態にあったのです。
明日8月15日この国の71回目の終戦記念日を迎えますが。
戦時中の教会は、クリスチャンであることと日本国民であることとの間で自らを問われました。そのような中で、天皇を現人神として拝することと、教会で主なる神を礼拝することとが混在していった近代の歴史があります。
それは、エリヤが民に問うた「どっちちかず」という問題性を今日のわたしたちの課題として示してします。
戦時下という異常な状況の中でなされたことに、今のまがりなりにも平和のうちにいるわたしたちが安易に批判することはできませんが。そのような時代と過ちが二度と繰り返されることがないように平和の祈りと決意を新たにもつときとして覚えたいと願います。
8・15の平和祈祷集会(関西連合社会委員会主催)が大阪教会で行われます。こちらにもどうぞ足をお運びくださり、ともに祈りを合わせたいと願っております。
さて、エリヤは「どっちつかずに迷っている民」に対してある提案をします。
それは犠牲の裂かれた雄牛を、エリヤとバアルの預言者450人の双方の薪の上に火をつけず載せておいて、自たちの神の御名を呼んで火をもって答える神こそ神であるはずだ、というものでした。
バアルの預言者たち450名は朝から真昼まで、祭壇の周りを廻りながらバアルの名を呼び、「バアルよ、我々に答えてください」と祈るのですが、何の答えもありません。彼らが祭壇のまわりを飛び回って叫ぶ様子を見たエリヤが嘲笑って、「神は不満なのか、それとも人目を避けているのか、旅にでも出ているのか。恐らく眠っていて、起こしてもらわなければならないのだろう」と挑発すると、バアルの預言者たちはさらに大声を張り上げ、剣や槍で体を傷つけ、血を流してまで必死にバアルの神に叫ぶのであります。それでも薪に火はつきません。
一方主の預言者エリヤは、イスラエルのすべての民に向かって「わたしの近くに来なさい」と呼びかけます。民が彼の近くに来ると、エリヤはそこでまず何をなしたでしょうか。
それは、バアルの神々を祀るために「壊された主の祭壇を、彼はすべての民の前で修復した」のです。このエリヤの行為は、神に罪を犯し荒廃していた民が自分たちに与えられた本来の祝福の源、「生ける救いの神の祭壇を築き直す」そのことを象徴的に表していました。
エリヤは31節以降にこのように行ったとあります。
「先祖ヤコブの子孫の部族の数に従って12の石を取り、その石を用いて主の御名のために祭壇を築いた。そこに献げものの雄牛を薪の上において、4つの瓶の水を3回、合計これも12回という数ですが水を注いだ」のです。
かつては同じ一つの民であった12の部族。それが北と南に分裂してしまったのですが。そのイスラエルの12部族の大本、その根源は、かつて囚われの奴隷状態から導き出された救いの神にある。その事がここに示されているように思えます。この光景はその場に集まった民のひとり一人に先祖より伝えられてきた「生ける主なる神」のみ恵みと慈しみ、又戒めをもしみじみと思い起こさせたのではないでしょうか。そういった彼らの魂といいますか、アイデンティティーの修復作業がここで丹念になされているということであります。
わたしたちクリスチャンも時に世の中の動きや力、誘惑や弱さの中でこの民のように主の救いの恵みを忘れ、どっちつかずのような状態になることはないでしょうか。
そんな時、エリヤが主の祭壇を築き直したように、心の祭壇を築き直さなければならないでしょう。如何にわたしは主の憐れみと犠牲によって救い出され、どのように滅びから導き出されたかを思い起こす。わたしの救いの原点に立ち返ることの大切さを、ここのところは表しているんですね。
さらに、エリヤは主にこう祈ります。
「アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ、あなたがイスラエルにおいて神であること、またわたしがあなたの僕であって、これらすべてのことをあなたの御言葉によって行ったことが、今日明らかになりますように。わたしに答えてください。主よ、わたしに答えてください。そうすればこの民は、主よ、あなたが神であり、彼らの心を元に返したのは、あなたであることを知るでしょう。」
ここでエリヤははっきりと民の先祖の名を連ね、「あなたがわたしたちの神であることをお示しください」と民の前で祈ります。
主の預言者エリヤは、騒々しく自虐的なバアルの預言者たちとは対照的に、神によって与えられる知恵と霊性をもって、又、生ける主への確信をもって呼びかけ、祈るのであります。
そうしたところ、祭壇の上に主の火が降って、牛と薪は焼き尽くされたというのであります。
この主の火については、創世記19章で、主が偶像の町ソドムとゴモラの上に天から、硫黄の火を降らせ滅ぼされたとされる、その硫黄の火を示しているともいわれていますので、まあバアルの偶像礼拝における審きともとれますけれども。一方で、新約時代に生きるわたしたちは、あのペンテコステの炎、火を彷彿とさせます。贖いの犠牲の上に主の火が臨み、主がその栄光をあらわされた。それはわたしたちのための贖い捧げものとなられた主イエス・キリストによって聖霊の火が下り、今も注がれ続ける御霊の火です。焼き尽くされた犠牲の捧げものは、神の民に対する愛とご自身が情熱の神のであるということを物語っています。
それほどまでにご自身の民を、又、救いに与るわたしたちを愛しておられるということであります。
さて、これを見たすべての民はひれ伏したとあります。このことをして人々のうちに聖なる主への畏れが生じたのです。彼らは「主こそ神です。主こそ神です」と繰り返し口にしました。イスラエルの民はそれぞれ、もはや世の権力や偶像によらず、又周りの人がしているからというのでもなく、自ら進んで「主こそ神、主こそ神です」と主体的にいのちの基となる神を告白して主を賛美します。
彼らは自分たちの依って立つ処、存在の源がアブラハム、イサク、ヤコブの神にあり、囚われの地より導き出した生ける主であることを再び見出し、主に立ち返る者となったのですね。
エリヤが、「主よ、あなたが答えてくだされば、この民は、主よ、あなたが神であり、彼らの心を元に返したのは、あなたであることを知るでしょう」と祈ったそのとおりになったのです。主が民の「心を元に返した」という出来事は、まさにエリヤがまず民たちとともに壊れた主の祭壇を入念に修復して、救いと恵みの原点を思い起こさせ、備えていったからではないでしょうか。
これはわたしたちにとって日常的にいえば、一緒に奉仕したり、作業したり、集会を持ったりすることもそうですね。もちろん礼拝や祈りの場はその最たるものでありますが。そうやって主の前に祭壇を築き直す作業が、主体的な信仰をゆたかに育んでくれるのですね。
今回のエピソードを宗教間の対立という構図で読みますと、本来のメッセージは見えてきません。この対決は、どっちつかずの民が、本来の救いの神に立ち返って生きるための戦いです。エリヤは民に命じ、バアルの預言者を粛清しますが。それは、救いを妨げる自分の中に潜む敵、罪と徹底的に戦うことの必要性を示していると読むべきでしょう。
先週は、やもめとエリヤのお話でした。
そこでの大きなテーマは、「何を第一とするか」です。
エリヤは一握りの粉でパンを焼き、息子と死を待つばかりというやもめに、「恐れてはならない。帰って、あなたの言ったとおりにしなさい。だが、まずそれでわたしのために小さいパン菓子を作って、わたしに持って来なさい。その後あなたとあなたの息子のために作りなさい。なぜならイスラエルの神、主はこう言われる。主が地の面に雨を降らせる日まで、壺の粉は尽きることなく、瓶の油はなくならない」と伝えます。
エリヤを通して語られた主の御言葉の真意は、「まず、すべてを造り、すべてを治めておられる主なる神さまに、それを捧げなさい」ということです。エリヤは異教のやもめに生ける主なる神さまを指し示し、その「神に信頼をし、従って命を得なさい、きっとあなたがたを顧みてくださる」と、そう伝えたのです。
エリヤはほんとうの神さまを知らないやもめに、生けるいのちの源なる神さまを示して、その神によって、いのちを得るよう促しました。やもめは神の言葉に全存在をかけて、「行ってエリヤの言葉どおりにした」のです。すると、「彼女もエリヤも、彼女の家の者も、幾日も食べ物に事欠かなかった。主がエリヤによって告げられた御言葉のとおり、壺の粉は尽きることなく、瓶の油もなくならなかった」のであります。まさに「何を第一としていくか。」「何によていのちを得るか」というメッセージが、実は今日の「戦い」のエピソードの中にも込められているのです。
今日わたしは生ける主を第一としているでしょうか。ヨハネ黙示録3章15節をとおして主はこのように警告しておられます。「わたしはあなたの行いを知っている。あなたは、冷たくもなく熱くもない。むしろ、冷たいか熱いか、どちらかであってほしい。熱くも冷たくもなく、なまぬるいので、わたしはあなたを口から吐き出そうとしている。」
「神との交わり、人との関わり、生の全領域において、まず「神の国と神の義」を求めていくことが期待されています。わたしたちが心を定めてそのように生きていくところに、主の答えと祝福が用意されています。「主の祭壇を建て直す」ことが、どっちつかずのわたしたちが抱えるあらゆる問題の解決につながっていくのです。
祈りましょう。
本日は平和を覚えての礼拝として主に捧げています。
先ほどSさんから戦争体験を通しての貴重な証言・あかしを伺いました。
戦争を知らない世代が増えていくなかにあって、過去の過ちを繰り返さないために
も、実際に戦争をご体験された方からの貴重な証言をお聞きすることができ感謝します。
本日の聖書箇所は、バアルの預言者450人と主の預言者エリヤとの真の神を巡る対決の場面でありますが。アハブ王はエリヤの要請どおりバアルの預言者450人をカルメル山に集めました。
そこでエリヤはすべての民に近づいて問いかけます。
「あなたたちは、いつまでどっちつかずに迷っているのか。もし主が神であるなら、主に従え。もしバアルが神であるなら、バアルに従え。」
ところが「民はひと言も答えなかった」というのです。
それはまさに、民がどっちつかずの状態であったということを表していました。
先週申しましたように、アハブ王は異国の王女イゼベルと政略結婚しました。それにより北イスラエルの地にイゼベルが持ち込んだバアルの神殿を建てて拝んだり、アシュラ像を建立したりとしていくうちにその民たちも惑わされて、主なる神から心が離れていったのです。人々は護国豊穣をもたらすとされるバアルの偶像礼拝をなし、主の目に悪とされることを行っていました。
エリヤは王や民の心が神ならざるものに向かっていることが嘆かわしくてなりません。人々は、主なる神さまを忘れてはいないけれども、バアルも大切だと、まさにどっちつかずの宙ぶらりんの状態にあったのです。
明日8月15日この国の71回目の終戦記念日を迎えますが。
戦時中の教会は、クリスチャンであることと日本国民であることとの間で自らを問われました。そのような中で、天皇を現人神として拝することと、教会で主なる神を礼拝することとが混在していった近代の歴史があります。
それは、エリヤが民に問うた「どっちちかず」という問題性を今日のわたしたちの課題として示してします。
戦時下という異常な状況の中でなされたことに、今のまがりなりにも平和のうちにいるわたしたちが安易に批判することはできませんが。そのような時代と過ちが二度と繰り返されることがないように平和の祈りと決意を新たにもつときとして覚えたいと願います。
8・15の平和祈祷集会(関西連合社会委員会主催)が大阪教会で行われます。こちらにもどうぞ足をお運びくださり、ともに祈りを合わせたいと願っております。
さて、エリヤは「どっちつかずに迷っている民」に対してある提案をします。
それは犠牲の裂かれた雄牛を、エリヤとバアルの預言者450人の双方の薪の上に火をつけず載せておいて、自たちの神の御名を呼んで火をもって答える神こそ神であるはずだ、というものでした。
バアルの預言者たち450名は朝から真昼まで、祭壇の周りを廻りながらバアルの名を呼び、「バアルよ、我々に答えてください」と祈るのですが、何の答えもありません。彼らが祭壇のまわりを飛び回って叫ぶ様子を見たエリヤが嘲笑って、「神は不満なのか、それとも人目を避けているのか、旅にでも出ているのか。恐らく眠っていて、起こしてもらわなければならないのだろう」と挑発すると、バアルの預言者たちはさらに大声を張り上げ、剣や槍で体を傷つけ、血を流してまで必死にバアルの神に叫ぶのであります。それでも薪に火はつきません。
一方主の預言者エリヤは、イスラエルのすべての民に向かって「わたしの近くに来なさい」と呼びかけます。民が彼の近くに来ると、エリヤはそこでまず何をなしたでしょうか。
それは、バアルの神々を祀るために「壊された主の祭壇を、彼はすべての民の前で修復した」のです。このエリヤの行為は、神に罪を犯し荒廃していた民が自分たちに与えられた本来の祝福の源、「生ける救いの神の祭壇を築き直す」そのことを象徴的に表していました。
エリヤは31節以降にこのように行ったとあります。
「先祖ヤコブの子孫の部族の数に従って12の石を取り、その石を用いて主の御名のために祭壇を築いた。そこに献げものの雄牛を薪の上において、4つの瓶の水を3回、合計これも12回という数ですが水を注いだ」のです。
かつては同じ一つの民であった12の部族。それが北と南に分裂してしまったのですが。そのイスラエルの12部族の大本、その根源は、かつて囚われの奴隷状態から導き出された救いの神にある。その事がここに示されているように思えます。この光景はその場に集まった民のひとり一人に先祖より伝えられてきた「生ける主なる神」のみ恵みと慈しみ、又戒めをもしみじみと思い起こさせたのではないでしょうか。そういった彼らの魂といいますか、アイデンティティーの修復作業がここで丹念になされているということであります。
わたしたちクリスチャンも時に世の中の動きや力、誘惑や弱さの中でこの民のように主の救いの恵みを忘れ、どっちつかずのような状態になることはないでしょうか。
そんな時、エリヤが主の祭壇を築き直したように、心の祭壇を築き直さなければならないでしょう。如何にわたしは主の憐れみと犠牲によって救い出され、どのように滅びから導き出されたかを思い起こす。わたしの救いの原点に立ち返ることの大切さを、ここのところは表しているんですね。
さらに、エリヤは主にこう祈ります。
「アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ、あなたがイスラエルにおいて神であること、またわたしがあなたの僕であって、これらすべてのことをあなたの御言葉によって行ったことが、今日明らかになりますように。わたしに答えてください。主よ、わたしに答えてください。そうすればこの民は、主よ、あなたが神であり、彼らの心を元に返したのは、あなたであることを知るでしょう。」
ここでエリヤははっきりと民の先祖の名を連ね、「あなたがわたしたちの神であることをお示しください」と民の前で祈ります。
主の預言者エリヤは、騒々しく自虐的なバアルの預言者たちとは対照的に、神によって与えられる知恵と霊性をもって、又、生ける主への確信をもって呼びかけ、祈るのであります。
そうしたところ、祭壇の上に主の火が降って、牛と薪は焼き尽くされたというのであります。
この主の火については、創世記19章で、主が偶像の町ソドムとゴモラの上に天から、硫黄の火を降らせ滅ぼされたとされる、その硫黄の火を示しているともいわれていますので、まあバアルの偶像礼拝における審きともとれますけれども。一方で、新約時代に生きるわたしたちは、あのペンテコステの炎、火を彷彿とさせます。贖いの犠牲の上に主の火が臨み、主がその栄光をあらわされた。それはわたしたちのための贖い捧げものとなられた主イエス・キリストによって聖霊の火が下り、今も注がれ続ける御霊の火です。焼き尽くされた犠牲の捧げものは、神の民に対する愛とご自身が情熱の神のであるということを物語っています。
それほどまでにご自身の民を、又、救いに与るわたしたちを愛しておられるということであります。
さて、これを見たすべての民はひれ伏したとあります。このことをして人々のうちに聖なる主への畏れが生じたのです。彼らは「主こそ神です。主こそ神です」と繰り返し口にしました。イスラエルの民はそれぞれ、もはや世の権力や偶像によらず、又周りの人がしているからというのでもなく、自ら進んで「主こそ神、主こそ神です」と主体的にいのちの基となる神を告白して主を賛美します。
彼らは自分たちの依って立つ処、存在の源がアブラハム、イサク、ヤコブの神にあり、囚われの地より導き出した生ける主であることを再び見出し、主に立ち返る者となったのですね。
エリヤが、「主よ、あなたが答えてくだされば、この民は、主よ、あなたが神であり、彼らの心を元に返したのは、あなたであることを知るでしょう」と祈ったそのとおりになったのです。主が民の「心を元に返した」という出来事は、まさにエリヤがまず民たちとともに壊れた主の祭壇を入念に修復して、救いと恵みの原点を思い起こさせ、備えていったからではないでしょうか。
これはわたしたちにとって日常的にいえば、一緒に奉仕したり、作業したり、集会を持ったりすることもそうですね。もちろん礼拝や祈りの場はその最たるものでありますが。そうやって主の前に祭壇を築き直す作業が、主体的な信仰をゆたかに育んでくれるのですね。
今回のエピソードを宗教間の対立という構図で読みますと、本来のメッセージは見えてきません。この対決は、どっちつかずの民が、本来の救いの神に立ち返って生きるための戦いです。エリヤは民に命じ、バアルの預言者を粛清しますが。それは、救いを妨げる自分の中に潜む敵、罪と徹底的に戦うことの必要性を示していると読むべきでしょう。
先週は、やもめとエリヤのお話でした。
そこでの大きなテーマは、「何を第一とするか」です。
エリヤは一握りの粉でパンを焼き、息子と死を待つばかりというやもめに、「恐れてはならない。帰って、あなたの言ったとおりにしなさい。だが、まずそれでわたしのために小さいパン菓子を作って、わたしに持って来なさい。その後あなたとあなたの息子のために作りなさい。なぜならイスラエルの神、主はこう言われる。主が地の面に雨を降らせる日まで、壺の粉は尽きることなく、瓶の油はなくならない」と伝えます。
エリヤを通して語られた主の御言葉の真意は、「まず、すべてを造り、すべてを治めておられる主なる神さまに、それを捧げなさい」ということです。エリヤは異教のやもめに生ける主なる神さまを指し示し、その「神に信頼をし、従って命を得なさい、きっとあなたがたを顧みてくださる」と、そう伝えたのです。
エリヤはほんとうの神さまを知らないやもめに、生けるいのちの源なる神さまを示して、その神によって、いのちを得るよう促しました。やもめは神の言葉に全存在をかけて、「行ってエリヤの言葉どおりにした」のです。すると、「彼女もエリヤも、彼女の家の者も、幾日も食べ物に事欠かなかった。主がエリヤによって告げられた御言葉のとおり、壺の粉は尽きることなく、瓶の油もなくならなかった」のであります。まさに「何を第一としていくか。」「何によていのちを得るか」というメッセージが、実は今日の「戦い」のエピソードの中にも込められているのです。
今日わたしは生ける主を第一としているでしょうか。ヨハネ黙示録3章15節をとおして主はこのように警告しておられます。「わたしはあなたの行いを知っている。あなたは、冷たくもなく熱くもない。むしろ、冷たいか熱いか、どちらかであってほしい。熱くも冷たくもなく、なまぬるいので、わたしはあなたを口から吐き出そうとしている。」
「神との交わり、人との関わり、生の全領域において、まず「神の国と神の義」を求めていくことが期待されています。わたしたちが心を定めてそのように生きていくところに、主の答えと祝福が用意されています。「主の祭壇を建て直す」ことが、どっちつかずのわたしたちが抱えるあらゆる問題の解決につながっていくのです。
祈りましょう。