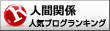礼拝宣教 テサロニケ一3・1~13 沖縄(命どぅ宝の日)を覚えて
本日は6月23日の「沖縄(命どぅ宝)の日」をおぼえつつ、礼拝を捧げています。
バプテスト女性連合前会長さんが聖書教育の中で次のように書かれておられます。
「2008年から毎年6月23日前後に3泊4日の沖縄学習ツアーをスタート。全国から友が集い、沖縄戦の追体験と基地の課題を身をもって知る旅にでかけています。参加者は戦跡を辿り、そこで非業の最期を遂げた人々の声なき声に耳を澄ませ、悲しみや痛みに思いを馳せます。また辺野古のキャンプシュワブの前で長年座り込みを続ける地元の方々から、基地がどれほど人々のいのちと生活を脅かしているかを直接伺います。沖縄バプテスト連盟の女性会の方々とも、回を重ねるごとに相互理解が深まり、親しい友との再会もツアーの楽しみの一つとなりました。
辺野古で出会った80代の女性は『戦争で何もかも失った私らにとって、この海は命をつなぐ宝の海だった。魚やモズクをとって子どもに食べさせ何とか生き延びたさぁ。その美(ちゅ)ら海を孫子の代まで残してやりたい、なんでそれが許されないの?もう戦争なんかこりごりさ』と語られました。人々は今日もまた、忍耐強く座り非暴力による基地反対を表明し続けているのです。
キリストの心を自らの心とする私たちは、もはや沖縄の苦しみを見過ごしにすることはできません。私たちもまた沖縄を苦しめている一人であるのですから。沖縄に行くと、そこで人々に寄り添い続けるキリストにお会いできるのです。沖縄の平和はすなわち私たちの平和、「平和を実現する者は幸い」と言われる主に従って、誠実に歩みたいと願っています。」
命どぅ宝、命こそ宝。辺野古の埋め立てが再開されました。今も続く苦闘を強いられる沖縄の叫びを知って、命と平和への祈りを共に捧げてまいりましょう。
本日はテサロニケ一3章から「苦難に直面しながらも」と題し、御言葉に聞いていきたいと思います。
「愛と信仰のために」
前章17節以降によれば、パウロはテサロニケを離れた後、幾度もテサロニケの信徒たちに会いに行こうと切に願いますが、「サタンによって妨げられて」実現しなかったとのことです。それが病のためであったのか、敵対する勢力による妨げだったのかは分かりませんが。
そこでパウロは、1節「もはや我慢できず」、口語訳では「これ以上耐えられなくなって」、代わりに福音のために働く神の協力者テモテをサロニケの教会に送るのです。
サタンの働きは、人が福音を聞いて、主イエスを信じ、受け入れることを妨げます。
それだけではありません。主イエスを信じ、受入れた人の信仰をも奪おうとするのです。
まあですから、パウロはそのようなことが愛するテサロニケの信徒たちにあってはならないと、さらに5節でも(1節と5節は同じ原語です)「これ以上耐えられなくなって」(口語訳)と重ねてその思いを吐露したのです。
テサロニケの信徒たちを襲う苦難を思うとき、パウロの心も耐えられないほど深く痛んでいたということであります。パウロはテサロニケの信徒たちの苦しみや痛み、彼らのことが心配でたまらなかったのです。
先週の箇所では、パウロの母の心、父の心というようなテサロニケの信徒たちへの愛情を知らされたわけですが。その愛するテサロニケの信徒たちが迫害に遭うばかりでなく、
サタン、誘惑するものの惑わしによって、彼らに語り伝えて来た主イエスにある福音が台無しにされ、その信仰まで奪い去られてしまうのではないかと、気が気でならなかったのです。
だから、パウロは2-3節、テサロニケの信徒たち「励まして、信仰を強め、苦難に遭ってもだれ一人動揺することがないようするため」、福音の同労者テモテをテサロニケ教会に遣わすのですね。
一人のひとが福音を信じ、主イエスを救い主として受け入れたというところでハッピーエンドではなく、信仰の歩み、主にある歩みは一生涯続くことによってキリストに結ばれた証しが立てられていきます。
パウロの思いというのは単なる信仰のサポーターという領域を超え、まさに親心でテサロニケの信徒たちを愛するのですが。私は牧師という立場からこのパウロのような情熱・パッションを持ち得るのか問われるものでありますが。
このパウロの愛の源はとりもなおさず主イエス・キリストの愛にありました。
私たちもまた、その主イエスの愛に与った者として、互いに励まし、信仰を強め、苦難に遭っても誰も動揺することがないよう共に生き、生かされていることのです。
「励ます者も励まされる」
さて、パウロはサロニケの教会から帰って来たテモテの報告を受け、「あなたがたの信仰と愛について、うれしい知らせを伝えてくれました」と大変喜んでいます。
その「うれしい知らせ」とは、1章3節にもありました苦難の中でテサロニケの教会が「信仰による働きと愛のための労苦」を惜しまず勤しんでいた、といううれしい知らせです。
パウロは4節で「あなたがたのもとにいたとき、わたしたち(主を信じるキリスト者)がやがて苦難に遭うことを、何度も予告しました」と記しています。
そうして実際にテサロニケの教会は困難や苦難に直面します。
すると彼らはパウロの教えを忘れず、その困難や苦難の中で、その信仰が弱まるどこかますます主に従い、主に依り頼んで生きる信仰者とされていったのです。
「クリスチャンになったらいつも問題が解決され、すべてうまくいくからあなたも信じたらいいですよ。」と言うなら、それは神を自分の思い通りに動かそうとする偶像礼拝と変わりありません。
パウロが初めから伝えたのは、主イエスが神に従い、人を愛するために十字架にかかられたこと。その主イエスを神が三日目によみがえらせてくださったことでした。
主イエスの愛と苦難によって救われた私たちも又、世にあっての苦難や困難は尽きませんが、むしろそこで主イエスがわがうちに生き、聖霊がお働きくださっていることを身をもって知ることができるのではないでしょうか。
昨今の状況も、まさにそのような時であると言えるでしょう。
パウロはローマの信徒への手紙の5章で、「苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生む。希望はわたしたちをあざむきません。聖霊によって神の愛がわたしたちに注がれているのです」と書き記していますが。
テサロニケの信徒たちも又、その苦難に直面しながらも「信仰による働きと愛のための労苦」を実践していたのであります。
又、この3章で、パウロがテサロニケの信徒たちにぜひ会いたいと望んでいるように、テサロニケの信徒たちも又パウロたちにしきりに会いたがっていることをテモテから知らされたパウロは、喜びに満たされ「うれしい知らせ」と、その思いを言葉にしています。
たとえ遠く離れていても、又試みる勢力が働こうとも、テサロニケの教会とパウロとの主イエスにある深い絆は決して揺らぐことはなかったのです。
パウロはそれらの報告を受けて、7-8節で次のように書き綴っています。
「兄弟たち、わたしたちは、あらゆる困難と苦難に直面しながらも、あなたがたの信仰によって励まされました。あなたがたが主にしっかりと結ばれているなら、今、わたしたちは生きているといえるからです。」
驚くことにあの使徒のパウロがテサロニケの信徒の信仰によって「わたしは励まされました」と言うんですね。
パウロが一方的にテサロニケ教会の信徒たちを励ましたというのではなく、実にテサロニケの教会の信徒の信仰による「生きた証と愛の労苦」とを知って、パウロ自身が彼らのその信仰に励ましを受けているのですね。
ここでパウロが、「あなたがたが主にしっかりと結ばれているなら、今、わたしたちは生きているといえるからです」と、書き綴った言葉にハッとさせられます。
パウロは使徒でしたが、自分だけが一人孤高の信仰を保っていることで満足する人では決してなかったのです。主にある人々とのよき信仰の分かち合いを離れては、キリストの使徒としての存在理由を見出せなかったのです。
神さまと一対一で向き合う関係は大切でありますが。
同時に、主に結ばれたきょうだいしまいが共に主の福音の働きや主の愛の業に携わり、共に与っていくことを通して、互いが励まされ、ゆたかにされていくのです。(今日の命どぅ宝の日やバプテスト連盟で共に担う世界祈祷の働きなどもその一つですね。)
今日の箇所で、パウロ自らテサロニケの教会を訪問したくてもできないとき、キリストの福音のために働く神の協力者であり、同労者であるテモテが立てられました。あらゆる点で優れていた信仰者パウロにも思うようにできないことがいくつもあったのです。
又テサロニケの信徒たちも、パウロにとってはかけがえのない神の協力者、福音のための同労者となり、相互に励まし支える存在とされたのですね。
私たちの主にある交わりも同様です。
キリストにあって共に生き、生かされていく私たちとされたいと願います。
最後に、パウロはテサロニケの信徒たちのことをおぼえながら祈ります。
テサロニケの信徒たちの信仰と愛に励まされて喜びにあふれ、神に感謝をささげたパウロは、さらにその愛する彼らの信仰に必要なものがあるなら補いたいと日夜祈り続けるのです。
まあ、大抵はもうこれで大丈夫だろうと思えたら祈らなくなることが多いのではないでしょうか。しかしパウロはその愛のゆえに「絶えず祈り続けた」というのです。
さて、ここでパウロは3つの点について祈っています。
1つは、何よりもテサロニケの信徒たちとの再会が叶うことです。もう一度顔と顔を合わせ福音を分かち合いたいと切に願ったのです。
けれども先にも触れたとおり、テサロニケへの再訪が実現しない。どのような熱意と願望をもっても神が道を開いてくださらなければそれはできないとパウロは知っていました。
又、どんなに難しく困難に思えるような状況にあっても神が道を開いてくださるなら、それができると確信していました。
パウロはこのテサロニケ教会の再訪も、この道を開いてくださるのは神御自身であることを信じて祈ります。
2つめは、テサロニケの信徒たちの愛が増し加わることです。あれだけテサロニケの信徒たちの愛に励まされたパウロなのになぜこのように祈ったのでしょうか。
困難や苦難に直面しながらも教会はこれまでにない愛の一致を生みだしたのでしょう。しかしその一方で、苦しみに動揺する者もいたのでしょう。
非常に厳しい事態におかれた時、教会内の関係もギスギスとし、軋轢を引き起こしやすくなります。又、社会の状況と同じように排他的、独善的になってしまうかもしれない。そういった人間の弱さをパウロは知ったうえで、「神が、あなたがた相互の愛とすべての人に対する愛とを、増し加えて豊かにして下さるように」と切実に祈るのです。
そして3つめは、主イエスの来臨に際して、「その心を強められ、神の前で聖なる、非の打ちどころのない者としてくださるように」と、祈ります。
主イエスは世の終わりの前兆として、「民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる・・・・偽預言者も大勢現れ、多くの人を惑わす。不法がはびこるので、多くの人の愛が冷える」(マタイ24・7-12)と、仰せになりました。
まさに今の時代状況とこの世の終わりの前兆とが重なってくるようですが。
けれども、私たちはそこで特別に慌てふためいたり、世の風潮に流されるのではなく、
日常と変わることなく主にある互いの愛とすべての人への愛に勤しみ、励んでいくことが、主の来臨に備えるふさわしい在り方なのです。
本日は「沖縄・命どぅ宝の日」をおぼえる日の礼拝です。
世に生かされている一人ひとりの命とその存在が大切にされていくように祈り求め、それぞれの場へと遣わされてまいりましょう。