礼拝宣教 コヘレト7・15-24
7章冒頭でコヘレトは「死ぬ日は生まれる日にまさる。弔い(葬儀)の家に行くのは/酒宴(婚礼)の家に行くのにまさる。そこには人の終わりがある。命あるものよ、心せよ」とさとします。メメントモリという言葉をご存知の方もおられるでしょう。これはラテン語で「自分がいつか必ず死ぬことを忘れるな」といういましめでありますが。
この7章全体を読みますと、コヘレトは人間にとって避けることの出来ない死と罪の問題に触れていることがわかります。人は世にあってどんな良い人も悪い人も誰もが死ぬべき存在である、だから今をどう生きるかを私たちに問いかけるのです。
創世記2章によれば、主なる神は御自分がお造りなられた最初の人(アダム)がエデンの園でご自身とのよき関係性を保ち、平安のうちに永らえるようにと心から願われたのです。そして最初の人アダムに「園のすべての木から取って食べなさい。ただし善悪の知識の木からは、決して食べてはならない。食べると死んでしまう」と命じられたのです。ところが人アダムはエバと一緒にその神の命じられたことを破り善悪の木の実をとって食べ、その罪のゆえに死ぬべき者となってしまった、ということです。
コヘレトは29節で次のように言います。「神は人間をまっすぐに造られたが/人間は複雑な考え方をしたがる、ということ」。引照付聖書には創世記3章6-7節が引照とあります。そこにあるのは誘惑の声に乗じて自分や他者、そして神さまにまで言い訳し、理屈をこねて何とか欲を満たし隠そうと画策しようとする人間の見苦しい姿です。神さまは本来まっすぐに人をお造りになられたのですが、人はその神の意に反して何につけ真っ直ぐではなくややこしいのです。それが神との関係性、人との関係性を損ねていると言えるでしょう。そのことがまさに罪なのであります。
使徒パウロは、ローマの信徒への手紙6章23節で、「罪が支払う報酬は死です」と記しました。そうした罪の行き着くところは空しさと滅びであり、神との断絶であります。
では、この人間にとって避けて通ることのできない死と罪の問題を念頭におきながら、今日の15~22節のところを丁寧に見ていきたいと思います。
コヘレトは言います。「この空しい人生の日々に/わたしはすべてを見極めた。善人がその善のゆえに滅びることもあり/悪人が悪のゆえに長らえることもある」(15節) これはこういった社会の矛盾を目の当りにしていたのでありましょう。そこには社会正義が実行されていないという嘆きと告発が根底にあるように思います。先週の箇所にも「虐げられる人と権力ある者」の話が出てまいりましたが。今日の7節の「賢者さえも、虐げられれば狂い/賄賂をもらえば理性を失う」といった事は、社会構造としても働き人の世の正しさや人としての営みをいつの時代も損なってきたのです。
しかし、コヘレトは驚くべきことを次に語ります。
「善人すぎるな、賢すぎるな/どうして滅びてよかろう。悪事をすごすな、愚かすぎるな/どうして時もこないのに死んでよかろう」。これは何か書籍コーナーに置いてある啓発本や、処世術を教えているような感がありますけど。まあ、悪事をすごすな、愚かすぎるな、ということはわかりますが。それにしてもひっかかりますのは、「善人すぎる、賢すぎる」ことが、どうして「滅びる」ことになるのでしょうか?みなさんはなぜだと思いますか?
それを知るにはまず、20節の「善のみを行って罪を犯さないような人間は/この地上にはいない」という事実を知る必要があります。
使徒パウロもローマの信徒への手紙3章9節で「ユダヤ人もギリシャ人も皆、罪の下にあるのです。義人はいない、一人もいない」と記しています。
たとえ人はいくら善人、義人、賢い人と称賛されようとも、神の前にはまったく自分を正当化することができない一人の罪人、刑法・犯罪を犯すか否かに関係なく罪人であることに変わりないのです。先に申しましたように、どんなに自分を正当化しようとしてああだこうだと言ってみても、しょせん人間は複雑な考え方、様々な言い訳をしながら自分の欲を満たそうとする者に変わりないのであります。たとえ、自分で善人になろう、正しくなろう、賢くあろうとして努めたとしても、そうであればある程、自分よりも正しくない、努力もしていないと思う人が、良い報いを受けているような姿を見るなら、その報われているように思える人に対する怒りと不公平感の嫉妬が燃え上がるものです。
先日、ちょうどこのメッセージの原稿を準備していた時いらしたある方から、「天国のたとえ」についてイエスさまが話された「ぶどう園の労働者」のお話について藤木正三という牧師(大阪教会の新会堂を建築施工して頂いた藤木工務店創設者の御曹司でもあられた方)が書かれた本をご紹介頂き、パラっと目を通していました。するとそこに、まさに不公平感の嫉妬や怒りに燃える人たちの姿が記されていたのです。
このぶどう園の主人は労働者を招きます。その招いた時間帯は労働者によって違い、労働時間も各々異なるのです。そうして、主人は賃金を皆一律に1デナリオンで約束します。そうして賃金の支払いが短い労働時間の者から支払われていきます。もう仕事が終わる前の5時頃雇われた人は1デナリオンをもらいます。ところが3時からの人、お昼からの人と、同様に1デナリオンの賃金をもらいます。そして最初に雇われた人の番が来た時、その人は心ひそかに朝から一日中働いたのだから、もっともらえるに違いないと思います。ところが主人はその人にも同じ1デナリオンを支払うのです。すると1デナリオンをもらったこの人は主人に向かって、「この最後の者たちは1時間しか働かなかったのに、あなたは一日中、労苦と暑さを辛抱した私たちと同じ扱いをされました」と、不平不満をもらします。このことについて藤木牧師は、「天国は恵みの論理の支配するところで、報酬の論理の支配するところではないこと」を解説されます。そして「彼らは報酬の論理に心奪われて、これだけ神さまのために一生懸命に働いたのだから天国に行けるなどと考えていた」と指摘されます。私たちクリスチャンにとって主イエス・キリストによる罪の赦しだけが「救いの道」でありますが。それが、自分の奉仕や働き、業を救いの条件のように考えるようになると、神の救いの恵みは異質なものになってしまうでしょう。そこにはおごりと高慢が生じるばかりです。さらに藤木牧師は、「しかし疑問が残るのは、なぜその支払いを最後の者からはじめたのか、最後の者からはじめて順々に最初の者に渡すように順序を逆にしたのであろうか。それは神さまの恵みを比較し、他と比べるということをまさに浮かび上がらせるためにそうした、と考えます」と言っておられます。そうですよね。私たちは人と比べ、人より善くありたい、どう評価されているかということが気になります。正しくあろう、立派であろうと、熱心に努力することは大事なことです。しかし、それが行きすぎますと人と比較し、人をさげすんだり、逆に妬みややっかみといった念が生じていくるのです。
ここでコヘレトは、「一つのことをつかむのはよいが/ほかのことからも手を放してはいけない」と言います。
この一つのことって何を言っているんでしょうか?コヘレとは単に教訓として言っているのではありません。潔癖すぎて他を排除する生き方。一つの事を追い求めるばかりで与えられている恵みや出会いに気づけない人生。「善人すぎて、賢すぎて滅びる」「悪事をすごし、愚かな生き方をして死んでしまう」。そのどちらの滅びの道をも避けるためには何が必要かを、コヘレトは語っているのであります。それこそが「神を畏れ敬う」という生き方だと言うのです。まあ今礼拝で使用している新共同訳(口語訳並びに改定版新共同訳はそこを正しく訳しています)は、ここの「神を畏れる者はどちらも得る」という訳は誤解を生じやすいといえます。正しくは、「神を畏れ敬う者は、そのいずれをも避ける」という意味です。です。すなわち神に打ち砕かれた魂、謙虚な心をもって常に生きるということであります。私たちにとりましてそれは、主イエスの罪の赦し。十字架の贖いによって与えられた恵みこそ、私の恵み、私の救いであるのだといつも確認し続け、その恵みのもと謙虚に日々歩むことに他なりません。コヘレトは、いつもたえずその時々に「神を畏れ敬え」と命じます。コヘレトはそうする時、18節にありますように、「神をかしこむ者は、このすべてから逃れ出るのである」と、口語訳でお読みしましたが、そのように罪と滅びから逃れる道について語っているのです
そしてさらにコヘレトは21節以降でこう語ります。「人の言うことをいちいち気にするな。そうすれば、僕があなたを呪っても/聞き流していられる。あなた自身も何度となく他人を呪ったことを/あなたの心はよく知っているはずだ」。
これは人を無視しなさいということとは違います。人から言われることを過度に心に留めて、それに囚われるあまり自分の心を患わせないようにしなさいということであります。又逆に、あなたも自分の発した言葉によって人の心を患わせていないかどうか、ということを主の前にあって吟味することが時に必要であるということです。
先にイエスさまの「ぶどう園の労働者」のたとえのお話をいたしましたが。神さまがお与え下さる「天国」は恵みの論理が支配するところであります。それは神さまが一人ひとりに恵みのギフトとして与えて下さっているものであります。それを人と比較して見たところで何になるでしょう。人の言葉や考え、人の言うことにいちいち影響されてしまうことになりますと、せっかくの恵みを見失うことになりかねません。そんなもったいないことはありません。先ほどのぶどう園の労働者のたとえで、主人は不満を口にする者に対して、「あなたに与えられた分は約束どおりだ。それともわたしの気前よさを妬むのか」と言われました。主の恵みはわたしに十分なのです。
さて、こうして罪と死を念頭に思いめぐらしてきたコヘレトは23-24節で次のように告白するに至るのです。これも口語訳でお読みします。「わたしの知恵をもってすべての事柄を試みて、『わたしは知者となろう』と言ったが、遠く及ばなかった。物事の理は遠く、また、はなはだ深い。だれがこれを見出すことができよう」。
コヘレトが見出した人生の知恵は優れたものでありますが。しかし彼は今、そうした人生の知恵を過度に評価しようとはいたしません。彼はその知恵もまた一部分でしかないことを謙虚に認めているのです。
それは私たち自身一人ひとりが見出していくべき人生の課題であり、神の御前に与えられています地上のいのちと時間を如何に生きるかという問いでありましょう。
私たちは主イエス・キリストの到来によって、罪の囚われから解放され、神の義による救いの恵みに与っているのです。このことに日々謙虚にされ、主こそ畏れ敬うべきお方として歩んでまいりたいと思います。
今日のコヘレトの言葉7章を締めくくるにあたり、もう一度礼拝の始めに招詞で読まれたローマの信徒への手紙3章21節-24節を読んで宣教を閉じます。 「ところが今や、律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて、神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆、罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリスト・イエスによる贖いの業を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです」。










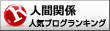

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます