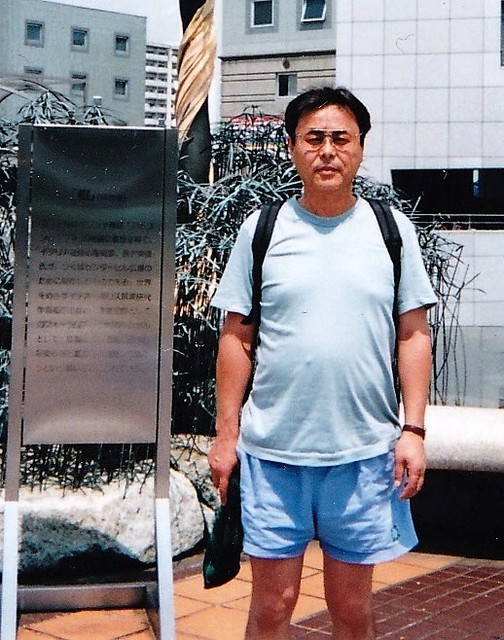すこし間が空きましたが、前回の続きです。
方丈記です、鴨長明です。
『ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。世の中にある人と栖(すみか)と、又各のごとし。』
光文社古典新訳文庫の「方丈記」640円+税を買い求め読んでいます。
まあ、それほど売れる本ではないと思います。買い求める方々は、やはり、40代から60代迄でしょうか。そうです、わたし、68歳で買い求めました。
70代に入ると、たぶん、もう、無常感どころではなく、命の灯は消える寸前、無常感に浸っている余裕は、もう無いのです。死は身近な現実となるのです。
でも、鴨長明さんは58歳で方丈記を書き記し、その4年後に亡くなっています。当時の日本人の平均寿命(主に貴族)は男性が33歳と云われています。
でも、まあ、乳幼児期を乗り越えた人は、それなりに60歳位までは生きていたようですから、鴨長明さんは当時としては、それなりの寿命。
※明治期の画家 菊池容斎 画 Wikipediaより転載・・・しかし、菊池容斎さんも、見た事も無い700年も前の方を、よく描くものです。まあ、それとなく、なんとなく、鴨長明的、方丈記的な雰囲気は感じられます。
死期を迎えつつある年齢にして、方丈記を綴った動機は何だったのか?
地震とか、竜巻とか、大火とか、疫病とか、飢餓とかを目の当たりにして、
『世の中にある人と栖(すみか)と、又各のごとし。』
とあるのです。人は分かるのですが、栖(すみか) 住む家を、同列にする、その発想に、いろいろな思いが、迷いが、込められている、と思います。
家屋敷とは、地位、名誉、権力、富の象徴です。人も権力も無常と云う事です。
人も権力も、無常と、云いつつ、説きつつ、でもしかし、死ぬ間際まで俗世間への欲望を抱き続けていた、そんな方だった気がするのです。
死ぬ5年前に、鎌倉に赴き将軍源実朝の和歌指導役を藤原定家と争い敗れ、翌年、方丈記を書き記し、2年後にこの世を去るのです。
そもそもです。いつの世も、俗世間から隔絶し、あばら家で自由気ままに暮らす方は、それなりに居るのです。
死期を間近にして方丈記を記し、無常「感」を自らと、世間に説いた行為は、それなりの悟りではなく、世俗的欲望への思いを断ち切れない、迷いの現れだと思うのです。
自然災害、天変地異に対して、無常「感」に浸るのは、それなりに、素直で情緒的な反応だと思います。
方丈記の無常「感」は、「観」ではなく、感情的で、情緒的で、美意識的で、日本的な感情であり、仏教の「無常」は、思想的、体系的なものであり、無常「観」なのだと、思うのです。
美意識的には、それなりの価値観として、受け入れやすいのです。
自然災害、天変地異が多く、コメを主食とし、木と藁の住居に住む、東北アジアの住民には、無常感は、それなりに受け入れやすいのかも。
でも、しかし、地震や、台風や、川の氾濫や、火災や、干ばつ等、自然災害、天変地異に立ち向かっての、治山治水、衣食住の確保してきたのが人間の歴史です。
それでも、時として、世の無常感に浸り、我が身の不幸を運の悪さを嘆き、それでも、翌日には、生きるため、食うために、無常感から抜け出して、世俗的な欲望の中に身を置いて、それなりの充足感に浸るのが、それなりのフツウの人。
年がら年中、無常感に浸っていては、フツウの人は、生きては、食べては、行けないのです。
それにしても、鴨長明は生活の糧はどうしていたの? 妻や子供は? 居たの? 棄てたの?
それにしても、この菊池容斎さんが描いた鴨長明、坊主頭に無精ひげ、 どこか私に似ているのです。
もう少し、鴨長明、方丈記に思い馳せてみたいと思います。
それでは、また。