近竹鶴河。
(近松門左衛門(ちかまつもんざえもん))(竹田出雲(たけだいずも))(四世(よんせい)鶴屋南北(つるやなんぼく))(河竹黙阿弥(かわたけもくあみ))
[ポイント]
1.人形浄瑠璃および歌舞伎のおもな脚本家は、近松門左衛門→竹田出雲→四世鶴屋南北→河竹黙阿弥とつづく。
[解説]
(元禄)
1.近松門左衛門(1653~1724)は武士の出身。現実の社会や歴史に題材を求め、義理と人情の板ばさみに悩む人びとの姿を、人形浄瑠璃や歌舞伎の脚本によって描いた。近松の作品は人形遣い辰松八郎兵衛(?~1734)らが演じ、竹本義太夫(たけもとぎだゆう)(1651~1714)らによって語られて民衆の共感をよんだ。その語りは、義太夫節という独立した音曲(おんぎょく)に成長していった。
(宝暦)
2.竹田出雲(二世)(1691~1756) は、大坂道頓堀の芝居小屋竹本座の座元(経営責任者)で初代の子。代表作(いずれも合作で延享年間初演)は『菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)(1746)』『義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)(1747)』『仮名手本忠臣蔵(かなでほんちゅうしんぐら)(1748)』。
(文化文政)
3.四世鶴屋南北(1755~1829)は、奇抜な仕掛けや早替りなどのケレンを多く作品に取り込む。化け物や妖怪が多く登場するなど、血なまぐさくおどろおどろしい作風で、南北において日本的なものの爛熟が見られる。代表作は『東海道四谷怪談(よつやかいだん)』。
(天保~明治)
4.河竹黙阿弥(1816~1893)は、前半の幕末期には伝統的な歌舞伎脚本を書く。その期の名作が『三人吉三廓初買(さんにんきちざくるわのはつがい)』。明治の演劇近代化の波の中で、日本的なものを払拭(ふっしょく)して西洋的な合理性を加えるが、かえって歌舞伎本来の良さを失う。
〈2016慶大・商AB方式:「
また、歌舞伎では鶴屋南北の『東海道四谷怪談』や河竹黙阿弥の作品など、(カ)町人の日常生活を写実的にとらえた作品が人気をあつめた。
問6 下線部(カ)で述べられている歌舞伎の脚本を何というか。漢字4文字で書きなさい。
(答:生世話物 ※文化文政期以降、とくに写実性のつよい生粋(きっすい)の世話物を生世話物(きぜわもの)(真世話物)と称した)〉
〈2014早大・教育:「
問9 下線部e文政の時代に活動していた文人をすべて選べ。
ア柳亭種彦 イ曲亭馬琴
ウ近松門左衛門
エ三浦梅園 オ松尾芭蕉
カ富永仲基 キ井原西鶴
(答:ア・イ ※ウ近松・オ芭蕉・キ西鶴は元禄期(17世紀後半)、エ梅園は明和・天明期(18世紀後半)、カ仲基は享保・元文期(18世紀前半))〉
〈2012立大・全学部2/6実施:「
問4.これに(歌舞伎)関する説明として正しいのはどれか。次のa~dから1つ選べ。
a.河竹黙阿弥による白浪物は、元禄時代の歌舞伎の代表作である
b.坂田藤十郎は、江戸の歌舞伎役者として活躍し、荒事を確立した
c.竹本座は、幕府から興行が公認された歌舞伎劇場である江戸三座の1つであった
d.『東海道四谷怪談』は、鶴屋南北(四世)によって書かれた生世話物である」
(答:d〇 ※a×幕末に盛行。「白浪」とは盗賊のこと、b×江戸・荒事→上方・和事、c×人形浄瑠璃の劇場)〉

















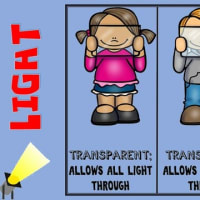








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます