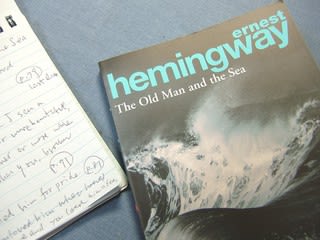
この本を初めて読んだのは確か中学生の頃でしたから、ざっと25年以上も前になります。新潮文庫の訳書で、薄い本でしたから2日か3日で一気に読んでしまった記憶があります。
先日『ロング・グッドバイ』を読み終わって、少し軽い(というか薄い)本がいいなぁと思いながら丸善の書架の前を行ったり来たり。色々候補があったなかで、チャンドラーへと続くハードボイルドの系譜を辿るべく選んだ一冊です。
あらすじは殆ど覚えていて、物語の展開がどうなるかは分かっているのに、読み始めるとその文章に一気に引き込まれました。英語自体は平易ですし、妙に凝った言い回しも出てきませんが、逆に読み飛ばすのが勿体無いような表現がたくさん出てきます。
このブログをご覧の方は何らかの形で釣りや魚にご興味をお持ちの方が多いと思うので、この本の内容はご存じの方も多いでしょう。老人が一人で海に出て、生涯二度と出会わないかも知れないという大物に巡り合うお話です。ただ大きな魚を釣り上げるだけでないところがこの物語の深さですが、そこにヘミングウェイの世界観、人生観が表れていると思います。同時に、魚と海、自然に対する畏敬の念に溢れていて、読み手はそれを、その素直な文体を以って直截的に感じ取ります。
今回は会社帰りの電車の中で、珍しく所々メモを取りながら読んだのですが、例えば老人が、死闘の末に捕らえた魚に対してこんな風に語りかけます。
"Never have I seen a greater, or more beautiful, or a calmer or more noble thing you, brother."
(魚よ、お前ほど偉大で、美しく、物静かで、高貴なやつを見たことがない。)
そしてまた、こんな風に考えます。
"You did not kill the fish only to keep alive and to sell for food, he thought. You killed him for pride and because you are a fisherman. You loved him when he was alive and you loved him after. If you love him, it is not a sin to kill him."
(魚を殺したのは、自分が生きるため、売って食料を得るためではない。彼は自分のプライドに掛けて、自分が漁師であるがゆえに魚を殺したのである。(魚が)生きている時に愛し、死んでからもまた愛するのだ。愛していれば(魚を)殺すことは罪にはならない。)
この本の面白さは、魚を捕らえた後の出来事と老人の心境の変化にあるのですが、襲い掛かるサメを "a moving appetite"(動く食欲)と呼び、彼らに対して次第になすすべがなくなっていく過程で、
"I wish it were a dream and that I had never hooked him. I'm sorry about it, fish."
(これが夢なら良かった、(魚を)掛けなければ良かった、魚よ、すまない。)
"I shouldn't have gone out so far, fish.... I'm sorry, fish."
(こんなに遠くに来なければ良かった、許してくれ。)
こんな風に思うようになります。私はここら辺にヘミングウェイ独特の厭世観が感じられると思うのですが、それが少しも皮肉っぽく読めないところがこの物語の素直な力だと思います。読み手は途中から結末が分かっていて、それをどうやっても避けることが出来ないということを、老人と同じ思考のプロセスを辿りながら思い知らされることになります。
随分と久しぶりの再読でしたが、これは間違いなく名作です。英語も比較的平易で短い(ペーパーバックで99頁)お話ですから、釣りと魚に興味のある方は是非読んでみて頂きたいと思います。

Ernest Hemingway
The Old Man and the Sea
(Arrow Books)

















それにしても、ピックアップされる文章にドキッ!としました。
普段の自分って釣りの時、どんな風に考えてるんだろうって・・・
当時は今ほど釣りに嵌まってなかったんで、久しぶりに読み返してみようかな~。
あ、もちろん訳書の方ですが・・・
この歳になって引っ掛かったような気がしています。
釣りが生身の命を相手にしている以上、自分が普段から
そこに尊厳とか畏敬の念を持って接しているかどうか・・・
相手は魚に限りませんが、そんなことを考えさせられる物語でした。