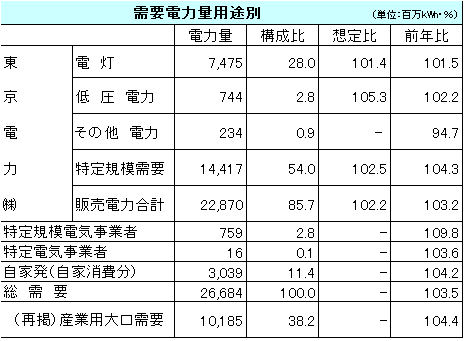防衛事務次官の更迭をめぐる小池防衛大臣と塩崎官房長官の揉め事が取り上げられています。
事務次官などの任免は官房長官・副長官で構成する人事検討会議の承認事項だと思っていたので (参照) 単なる小池大臣のフライングと見ていたのですが、朝の民放ニュース番組的には小池大臣の意向を官邸が横槍を入れた風なトーンで伝えられています。
ところで各省庁の幹部の人事権については branchさんのまとめによれば以下のようになっています。
まず、原則として、各省の職員の任命権については、各大臣に属している。その根拠は一般には 国家公務員法 第55条第1項 なのだが、防衛省職員のほとんどは特別職である(同法第2条第3項第16号)ため同法の適用がなく、 自衛隊法 第31条第1項※3 がその根拠ということになる。なお、念のために述べておくが、事務次官を含めて防衛省職員のほとんどは、自衛官でなくても自衛隊員である(同法第2条第5項)。
では、防衛大臣が任意にその権限をもって事務次官を任命できるかというと、そうではない。経緯をたどれば、橋本総理(当時)が自ら会長を務めた行政改革会議にさかのぼる。その 最終報告(平成9年12月3日)において、内閣機能の強化の観点から、内閣及び内閣総理大臣の補佐・支援体制に対する抜本的変革の一として「各省庁の次官、局長等幹部人事については、行政各部に対する内閣の優位性を明確にするため、各大臣に任免権を残しつつ、任免につき内閣の承認を要することとする。」との文言が盛り込まれた。これを踏まえ、 中央省庁等改革基本法に「国の行政機関の事務次官、局長その他の幹部職員については、任命権者がその任免を行うに際し内閣の承認を要することとするための措置を講ずるものとする。」との規定(第13条)が設けられ、これに基づく措置として、中央省庁等改革推進本部における検討の結果、「国の行政機関の事務次官、局長その他の幹部職員の任免について、閣議決定により内閣の承認を要するものとする。」こととされ 、それは「事務次官、局長その他の幹部職員の任免に際し内閣の承認を得ることについて」(平成12年12月19日閣議決定)により具体化され、幹部職員についてはあらかじめ閣議決定により承認を得た後に任免を行うこととし、それに先立って官房長官及び 3官房副長官からなる閣議人事検討会議を開催することとなったのである。
また
「守屋氏退任」の意向変わらず 小池防衛相
(2007年08月15日14時25分 朝日新聞)
によれば
小池防衛相は15日の閣議後の記者会見で、内閣改造まで一時凍結された守屋武昌事務次官の交代人事について「私は環境相として人事をやった経験もあり、何ら順序を間違えていない」と述べ、小池氏が防衛相を留任した場合には当初の構想通り、守屋氏を退任させる考えを示した。
小池氏は、人事の凍結を決めた塩崎官房長官に対しては「根回しの最中に報道が出たため(塩崎氏が)不快に感じていることについて謝罪した」と明らかにした。また、省内の混乱で「士気の低下に懸念を持っている」と述べ、事態を早く収拾する考えを示した。
と、手続きは守っていること、リークしたのは自分ではないことを主張しているようです。
しかしその後に続く 守屋氏が「自分の人事を聞いてなかった」と怒っている点について、
小池氏は「この件のみならず、携帯に夜電話しても返事が翌朝ということがよくあった。危機管理上、どうかと思う。この件も2回も電話した」と批判した。
と説明していますが、これではほとんど痴話げんかですね。
そもそも自分の人事について守屋次官が拒否権があるとか事前に知らせないからといて文句を言うのは妙な感じがします。
それに対して小池大臣もまた妙な説明をしていますが、人事権以前に指揮命令権はあるのですから、話があれば呼びつければいいだけですし、携帯電話に出ないことではなく「緊急連絡を取る方法が携帯電話しかない」ということのほうが危機管理上はどうかと思うのですが・・・
内閣改造が日程に上っている今、何で就任早々の大臣が(自分が再任される保証のない)内閣改造前の次官更迭にこだわるのか、と考えると、留任を画策するためにこの時期に手続きを無視してフライングすることで人気のない現執行部との対立を演出し首を切られにくくすることを画策したのではないか、という風に勘ぐってしまいます。
そうだとしたら「内閣改造を控えているのは承知だが自らが留任しないことも考え、大臣の地位にあるうちに獅子身中の虫を退治することが防衛省のために必要と考えた」くらいの大見得を切ったほうが格好良かったと思います。
それとも、早々に留任の内示をもらっていたので先走ってしまったのでしょうか。
ニュースの取り上げ方を見ると、当初小池大臣のケンカ相手は塩崎官房長官だったようなのですが、今日の報道を見ると「守屋次官対小池大臣」という構図に変わりつつあるようですが、いずれにしても何でこの時期にこんなことが問題に?という話ではあります。
人事検討会議では何かというと「女性か民間人を登用しろ」と○○の一つ覚えのように言っているという噂の塩崎官房長官ですので、女性に振り回されることになったのも仕方ないかもしれませんが。