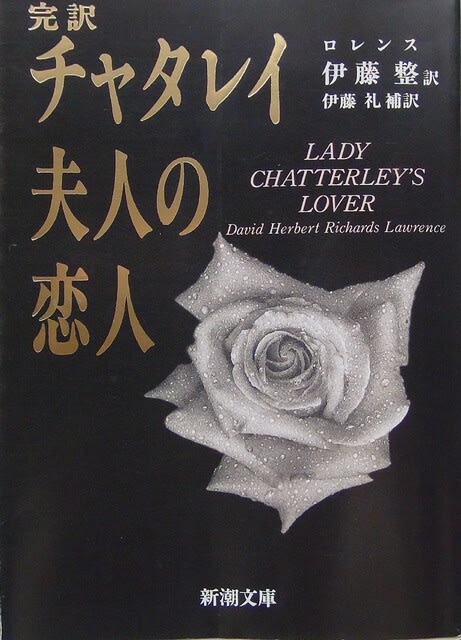人間時間があれば何かが出来るというのは必ずしも正しくないように思う。振り返ってみると、むしろ仕事が忙しく、あるいは仕事に追われているときほど、他のこともやりたくなったような気がする。一つのことに神経を集中すると、それに対するバランスをとろうとするようなもので、無関係なことに手を出したいと思うようになる。例えば、時間に余裕のない出張なのに、空港の待ち時間に本を読みたくなるようなことだ。また、期限を切られた仕事が山積みになっているのに何か楽器に触れてみたい、と思うような。
読書と言うと、学生時代は知り合いや親戚に頼まれて週に数回の家庭教師のアルバイトをしていた程度で多忙と言うにはほど遠く時間には余裕があり、また、当時第二外国語としてフランス語を履修していたこともあったので、とりあえずフランスの小説を中心にして読み始めた。そうすると、子供の頃読んだ(児童文学全集などで)時にはよく理解が出来なかった話の筋や主人公の性格、社会背景などがだんだん理解できるようになり、読む楽しさをどんどん増えた。それは文学だけでなく絵画や音楽にも触れる機会が増えたからだろう、さまざまな角度からの読み方が出来るようになったからだと思う。
その時はいろんなジャンルの小説を片っ端から読んでゆく、と言う感じでいわば質より量と言ったぐあいだった。特に18世紀のフランス文学には、複雑怪奇な人間関係、微妙な心理描写や贅沢三昧の貴族社会の生活、よく考えれば決してありえないような(スーパーマンとしか思えないような)冒険譚など、とにかく読んで楽しいという印象があった。そして、こんなに派手な浪費をする王族や貴族階級がいるのだから、流血のフランス革命が起きたのもおかしくはなかったのだと得心した(それは特権階級が貴族から共産党員にかわった1990年代の東欧諸国にもいえる)。
その点、国王がフランスほどの絶対権力を持っていなかったイギリスは、華やかな宮廷を舞台にした小説よりも厳しい自然を背景にした小説が多かったように思う。フランスの豊かな大地と比べるとイギリスは耕作には適していない。陰鬱な、どちらかと言うと地味な小説になるのも無理はないのかと。
それでは、人間時間が有り余るようになったらどうなるのだろう。ちょうど張りつめていたゴム風船が、少しづつ空気が抜けて行って、しわが深く刻まれてくるような、枯れてゆくようなことになり、すべての物事に対して緊張感を失ってしまうのだろうか。まだそういうところに至ってはいないがいつか必ず老いがやって来る。
かつてスコットランドの南の地方を車で通った時、道路の端に小さな駐車スペースがあり、そこに後ろが木枠の小型の乗用車が止まっていてその横にあるベンチに赤いウールのコートを着た老婦人と灰色のツイードのジャケットにハンチングの老紳士のカップルが並んで座っていた。二人は話をする様子でもなくどこまでも見渡せるなだらかな丘陵からの少し肌寒い風に吹かれながら紅茶を飲みサンドイッチを食べていた。時間を行き来するこはできないが、その時は、自分もいつかはそうなるのだろう、と言う漠とした予感のようなものを感じたことがある。
自動車と言えば金属とガラスの塊、と言う非人間的な響きをもつが、あの時代にはまだ木のぬくもりが感じられる車が片田舎をゆっくりと走っていた。
Morris Minor 1000 Traveler(1971)