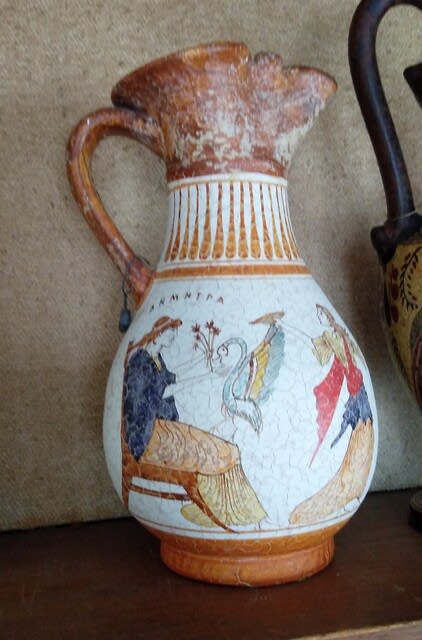海外駐在と言うことではイギリスとアメリカだけだが、出張ではヨーロッパだけでなく随分多くの国を訪れた。幸い東南アジアの国々にも足を伸ばす機会を持つことが出来た。たった一回のところもあれば、何度も訪れたところもある。それらの国の中で、今の寒い時期には特に南の国の暖かさが恋しく感じられる。
詳細については言えないが、極めて厳しい仕事で訪れた国の一つがベトナム。取り扱った事案が困難を極めた、ということであって、ベトナムの人々や自然環境といったことが原因ではない。本当に運が良かったのと、周囲の人に助けられて(全員ではないが)、何とか乗り切ったことは今でも忘れがたい。ベトナムには北部の首都ハノイと南部の商都ホーチミン、都合3回訪れた。8年ほど前になるがその最後の時に、現地の方から頂いたのがミンロン社製のプレート、題して「ベトナムの人々(Vietnamese People)」。
このプレートについている説明書によれば、「古くからの伝説によればベトナム人は、妖精と龍の子孫。このプレートは、妖精の化身である不死鳥と龍を彫ったもので、この龍は11世紀からベトナムを支配していたリー王朝時代の龍の複製。また、ベトナムは多くの民族により成り立っていることから、このプレートの外縁にはそれぞれの民族の特徴、文物、生活の様子を彫り込んである」とある。
この国での経験には厳しいものと楽しかったものの両方がある。このプレートを渡してくれた方はそれとなくこちらのそんな気持ちを汲んで、ベトナム文化の活き活きとした美しさを現わしたプレートを贈ってくれたに違いない。色褪せることのない独特の色調、熟練の技で細部まで精密に彫られたこのプレートを眺めていると辛い記憶は頭から去り、楽しい思い出が勝るようになる。熱帯特有のスコールが突然降り出し、また、突然に上がるホーチミンの、広い車道一杯に拡がっていたオートバイの列があの時のベトナムの熱気を物語っていた。