
インド初の女性刑事をヒロインにした歴史ミステリ。第二次世界大戦が終わり、インドが独立したあたりの経緯は本当に知らないことばかりで、ガンジーとかネールとかの名前がかろうじて頭にあるだけだ。
300年におよぶイギリス統治が立ちゆかなくなり、しかしプライドだけは高い旧宗主国の人間たちとその支持者。
パキスタンとの分割独立という最悪の選択のなかで(なにしろ線引きはインドに来たこともない役人が行ったのだとか)衝突し合う国民たち。そんな状況と同時に女性の地位も圧倒的に低い。そのようななかで起こる殺人事件。
なぜ通報が無能で有名な署になされたか……歴史とフェミニズムと殺人と。満足しました。ちなみに、作者は男性だそうです。
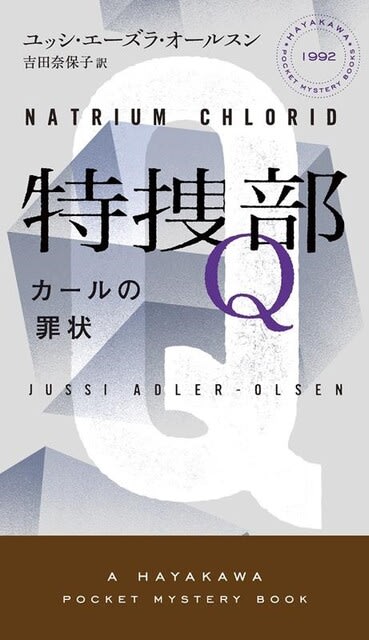
「アサドの祈り」はこちら。
長く続いてきたこのシリーズも9作目。予定されている最終作まであと1作だ。今回も北欧ミステリらしく犯行は残虐で、しかし精緻な構造になっているし、ユーモアのたっぷりだ。このシリーズが終わるのはさみしいなあ。
未解決事件を掘り起こす、個性あふれる(あふれすぎの)メンバーで組織される特捜部Q。最初は単なるコメディリリーフかと思われたアサドは家族にふりまわされ、ローセの性格の奇矯さはみがきがかかっている。
そして、このシリーズを貫く主人公カール自身の事件がついに動き出す。どのような幕引きになるのであれ、やっぱり終わるのはさみしい。

平成3年12月11日夕刻。神奈川県下で前代未聞の二児同時誘拐事件発生。30年後、封じられていた過去が動き出す……
「罪の声」「騙し絵の牙」の塩田武士の新作。新聞記者出身だけあって、冒頭の誘拐の描写はリアルだ。
なぜわざわざ二人をほぼ同時にさらうかといえば、犯人がどれだけ計算したかはともかく、警察の対応が物理的にしんどくなるのだった。当時の最先端の捜査ツールが足りなくなり、犯人に警察の介入を気取られてしまう(のではないか)あたり、芸が細かい。
衝撃的なオープニングだが、この小説の主眼は、誘拐された少年のその後である。作中で何度もふれられている松本清張の某作品、そしてその映画化された超大作に肌合いは近い。
美術の世界にわたしは昏いが、写実派が(写真の登場などで)不当に貶められていたことは初めて知った。しかし、カメラは単眼だが、人間は複眼で見る以上、写真とは違う作品が出来上がる道理は理解できる。そして、登場する写実派画家の絵があまりにも正確なので、彼の人生を追跡する人々を驚かせる仕掛けもうまい。
後半は、ある夫婦と子どものお話になる。そしてラブストーリーだ。読む人によって感じ方は違うだろうが、ラストをハッピーエンドととるか、ある人物の不在を強調しているととるか……にしても傑作でした。

年末のミステリランキングをチェックしていて、どう考えてもこれはわたし向きではないかと勘が働く本がある。そういうのはたいがい当たりだ。
デイヴィッド・ベニオフの「卵をめぐる祖父の戦争」がそうだったし、ドン・ウィンズロウの「ストリート・キッズ」もそうだった。
2021年版「このミステリーがすごい!」において、この「ザリガニの鳴くところ」は第2位。トップが無敵のホロヴィッツ「その裁きは死」。あの「指差す標識の事例」や「死亡通知書」よりも上なのである。なんかあるぞこの作品には。
でも貧乏だから図書館に期待するしかない。だから英米文学の棚に行って
「ザリガニザリガニザリガニ……」
とつぶやきながら(危ない人物だ)捜しても一向に見つからない。でも先日、ついに見つけましたザリガニ。
さっそく読み始める。
舞台はアメリカ南部の湿地帯。時代は1960年代から70年代。横暴な父親のために家族が次々に出奔し、ついには一人きりで(学校教育もうけずに)生きていかなければならなくなった少女。序盤は彼女のサバイバルで読ませる。そんな彼女に、読み書きを教えてくれたやさしい青年は、しかし進学のためにその土地を離れていく。
そんなとき、殺人事件が起きる。事件当時、現場近くで“目撃”されていた少女は果たして犯人なのか……
おおお面白いぞ。彼女のある種の才能が花開いていく成長物語でもある。
この作品は動物学者であるオーエンズにとってのなんと処女小説。しかも全米大ベストセラー作品で映画化もされています。大当たりではあったけれども、こんなにメジャーな小説だったのかザリガニ(笑)。
人生というのは実はとても長い。物理的に短いものであっても、それでも人生は長い。そのことの喜びと悲しさを一気に描く。まいった。
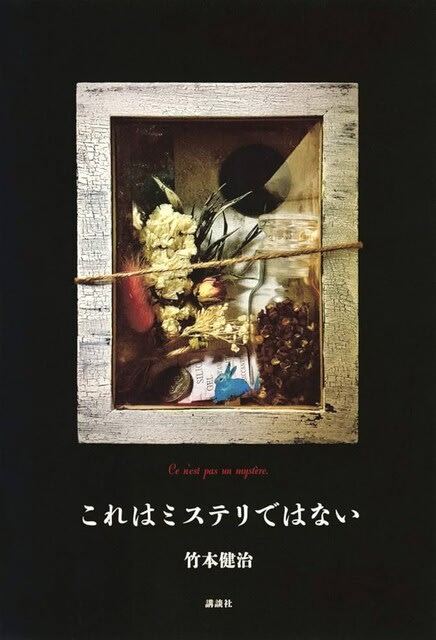
ひねくれものの竹本健治がこう主張するのだから、それはもうミステリに決まっています。
濃霧のために孤立した保養所における殺人。大学のミステリクラブの人間関係を推理する、“居合わせた”高校生たち。そのなかのひとりが名探偵で……んもうミステリど真ん中じゃないですか。まあ結末はとんでもないものでしたが。

山形在住の、村山弁ばりばりのヒロイン。「探偵は女手ひとつ」の続篇です。
前回は雪かきで稼いでいたけれど、今回は雪が少ないせいで稼ぎが少ない。で、風俗の送迎などでしのいでいる。そんななかで行方不明者の捜索を依頼され、動き回るうちにひとりの女性に行き着く……生活に追われ、しかし実直に生きる女性探偵と、その真逆な容疑者の対比がすばらしい。
今回も山形県内を駆け回る探偵がうれしい。地元作家による地元ヒロイン。シリーズ化期待。酒田まで来てくんねがずー。

おお、「13・67」の陳浩基、「元年春之祭」の陸秋槎の短篇が載ってるじゃないの、と読み始める。
もちろんすばらしい作品がつまっているんだけど、ラストの島田荘司「相馬樓 雪の幻」を読んでびっくり。え、これって酒田が舞台なの?ってことはこの相馬楼って、酒田の料亭のあの相馬楼?
いやはや。ヒロインの名前が駒子ということからもお分かりのように、川端康成の「雪国」を徹底的に意識したこの作品には、酒田名物の船箪笥が重要なモチーフとして登場するのだ。
それだけではなく、最後の著者紹介でまたびっくり。妙に艶めかしい作品を寄せた石黒順子って、酒田出身だったのっ!中華作品がお目当てだったのに地元がらみで驚いてばかり。いやーしかしびっくりした。
えーと、そしてわたしはなぜかその相馬樓に所属する酒田舞妓にこの週末幻惑されていたのでした。この本のことを訊くべきだった!

ある建設会社の課長3人が次々に不審死。はたして事故か殺人か。課長のうちのひとりの娘が警視庁捜査一課の刑事。関係者だから当然捜査から外される。娘はそのことに不満たらたらで、あろうことか単独で捜査を開始して……
とにかくこのヒロインにはイライラさせられっぱなし。自分を抑えることができず、まわりに迷惑をかけては自己嫌悪に沈む、その連続なのである。これで捜一の刑事なのか。やれやれ。
刑事を辞めた壮絶に優秀な探偵がメインキャラクターではあるけれど(おそらくモデルはホロヴィッツのホーソーンだ)、そちらもどうもうまく機能していない。手練れの中山七里にしては残念な。

















