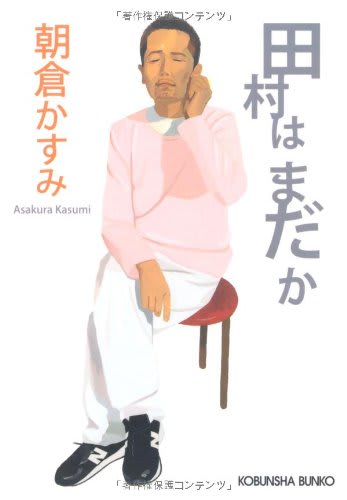オピニオンサイト「iRONNA」に、SMAP解散について、以下のコラムを寄稿しました。
「SMAPノムコウ」にも、
きっと何かが待っている
2016年12月31日をもって、解散することになったSMAP。あらためて、その軌跡を振り返り、また彼らの今後について考えてみたい。
SMAPが結成されたのは1988(昭和63)年である。翌89年1月には、年号が昭和から平成へと変わった。SMAPは昭和最後の年に誕生したアイドルグループなのだ。
CDデビューが91年。この年は、いわゆる“バブル崩壊”の年であり、そこから「失われた20年」とか、「失われた25年」などといわれる年月が始まった。つまり実質的には25年間の活動だったSMAPは、“平成という名の長い低成長期”と共に歩んできたわけだ。
そんなグループが、天皇の譲位が話題となってきた今、解散する。そう聞けば、「時代の変わり目」といった言葉をつい連想してしまう。確かに、“ひとつの時代”の終幕を象徴する出来事なのかもしれない。
また、多くのヒット曲を持つSMAPだが、彼らの「シングル売上げランキング」のトップ10を見ていると、意外に思うことがある。
1位の「世界に一つだけの花」(2003年)と、3位の「ライオンハート」(00年)の2曲を除けば、他は第2位の「夜空ノムコウ」をはじめ全てが90年代の楽曲なのである。音楽的なピークは90年代だったとも言えるのだ。
それにも関わらず、現在までSMAPとして存続してこられたのは、5人それぞれが単独活動も可能な才能を持っていたからであり、その集合体としてのグループが輝いていたからだ。
2017年から、「SMAPのいない芸能界」、そして「SMAP不在の時代」が始まる。寂しいことではあるが、ファンはもちろん、業界もまた受け入れるしかない。そして、慣れていくしかない。
その一方で、5人の新たな活躍を見る楽しみが待っていると思いたい。ただし、乱暴な予想としては、5人とも「ソロ歌手」という選択はしないだろう。音楽的に、個人でSMAPの実績を超えるのは、かなり難しい。むしろ音楽以外の場、タレントや俳優としての活動が中心になるはずだ。
キムタクドラマから木村拓哉ドラマへ
まずは木村拓哉だが、今後、ますます演技力に磨きをかけるだろう。その萌芽は、すでに2015年春のドラマ『アイムホーム』(テレビ朝日系)にあった。これは、いわゆる“キムタクドラマ”ではなかったのだ。脚本も演出も脇役も、ひたすら木村をカッコよく見せることだけに奉仕するのがキムタクドラマなら、この作品は違った。そこにいたのは“キムタク”ではなく、一人の俳優としての“木村拓哉”だった。
主人公は、事故で過去5年の記憶を失った家路久(木村)。なぜか妻(上戸彩)や息子の顔が白い仮面に見えてしまう。彼らへの愛情にも確信がもてない。その一方で、元妻(水野美紀)と娘に強い未練をもつ自分に戸惑っている。
原作は石坂啓の漫画で、仮面が邪魔して家族の感情が読み取れないというアイデアが秀逸だった。その不気味さと怖さはドラマで倍化しており、見る側を家路に感情移入させる装置にもなっていた。
自分は元々家庭や職場でどんな人間だったのか。なぜ結婚し、離婚し、新たな家族を持ったのか。知りたい。でも、知るのが怖い。そんな不安定な立場と複雑な心境に陥ったフツーの男を、木村拓哉がキムタクを封印して誠実に演じたのが、このドラマだ。
何より木村が、夫であり父でもあるという実年齢相応の役柄に挑戦し、きちんと造形していたことを評価したい。今後は、顔の細部を動かすようなテレビ的演技だけでなく、たたずまいも含め、全身で表現できる役者を目指してもらいたいと思う。
年明け早々に始まる医療ドラマ、TBS日曜劇場『A LIFE〜愛しき人〜』が、旧来の“キムタクドラマ”の延長にあるのか、それとも“木村拓哉ドラマ”の確立となるのか。当面の試金石だろう。
俳優・草彅剛とMC・稲垣吾郎の展開
木村と同様、俳優としての才能を生かしそうなのが草彅剛だ。2016年1月クールに放送された『スペシャリスト Specialist』(テレビ朝日系)に注目したい。
無実の罪で10年間服役していた刑事・宅間(草彅)という設定が意表をついていた。刑務所で学んだ犯罪者の手口や心理など、いわば“生きたデータ”が彼の武器だ。
草彅は、飄々としていながら洞察力に秀でた主人公を好演。また、ひと癖ある上司(吹越満)や、勝手に動き回る宅間に振り回される女性刑事(夏菜)など、脇役陣との連携も巧みだった。
年明けの1月クール、草彅は『嘘の戦争』(フジテレビ系)で主演を務める。冤罪だった父親のために詐欺師となって復讐を果たす男の役だ。誠実そうな風貌の草彅だからこそのキャスティングであり、そのギャップをどれだけ見せられるかが勝負だ。
3人目は稲垣吾郎である。三谷幸喜監督『笑の大学』(2004年)や三池崇史監督『十三人の刺客』(2010年)、また今年春のドラマ『不機嫌な果実』(テレビ朝日系)などが印象に残る。いずれも、いわゆる主演ではないものの、しっかりと存在感を示していた。
中でも、『十三人の刺客』が強烈だった。稲垣は役所広司たち刺客の敵であり、悪役である将軍の弟。この“狂気の人”を、想像以上の迫力で見事に演じていたのだ。今後も、稲垣の持ち味を生かせる役柄であれば、主役・脇役を問わず出演すべきだと思う。
また同時に、ブックバラエティ『ゴロウ・デラックス』(TBS系)で見せる、実に自然体なMCがとても魅力的だ。今月放送された、みうらじゅんと宮藤官九郎がゲストの前後編でも、これだけ個性の強い面々を相手に、自分を見失わず、しかも自分の性癖さえ適度にはさみみ込みながらトークを展開していた。これは立派な才能であり、今後はもっと活用すべきだ。
不透明な香取慎吾と、中居正広の「兄貴路線」
そして香取慎吾だが、実は5人の中で、今後が一番見えにくい。NHK大河ドラマ『新選組!』(2004年)や、『薔薇のない花屋』(2008年、フジテレビ系)での好演は記憶にあるが、2016年夏のTBS日曜劇場『家族ノカタチ』は、あまり感心できなかった。
繰り返される「結婚できないんじゃなくてしないんだ」という台詞が象徴するように、こだわりが強くて独身ライフを謳歌(おうか)しているという設定が、阿部寛主演の『結婚できない男』(フジテレビ系)とイメージがダブったのは仕方ないにしても、香取演じる独身男は、他人を拒否し、いつもイライラしていて不機嫌な人にしか見えなかった。
もちろん脚本や演出に従っただけかもしれないが、香取が俳優としてどのように進んでいきたいのかが、見る側に伝わってこなかったのだ。
あとは、テレビ朝日系『SmaSTATION!!』(スマステーション!!)のようなバラエティーということになるが、今回のSMAP解散への過程を経て、どこか香取自身が以前と比べて楽しんでいるように見えない。むしろ痛々しささえ感じてしまい、視聴者側も手放しで楽しめなくなっている。年が明けたら気分を一新し、今後の方向性を打ち出していって欲しい。
最後は中居正広だ。ドラマ『ATARU』(2012年、TBS系)は、主人公の特異なキャラクターが功を奏して適役だった。しかし、その後の『新ナニワ金融道』(2015年、フジテレビ系)などでの演技は、あまり進化しているように見えず、困った。
恐らく今後も、俳優としてより、『中居正広の金曜日のスマイルたちへ』(TBS系)など自身の冠バラエティーで活躍していくのではないか。今年、「ベッキー復帰問題」で見せた、芸能界の“ちょっとヤンチャな愛すべき兄貴”といったポジションも悪くないだろう。ただし、キャリアとしては実質的な大物になっているだけに、逆に大物風の言動にならないよう、気をつけたい。
SMAPノムコウ
2016年1月、『SMAP×SMAP』(フジテレビ系)で行われた異様な“生謝罪”に象徴される、後味の悪い独立騒動。そして、どこかスッキリしないまま、終幕を迎えた解散劇。
この1年で、5人のイメージは明らかにダメージを受けた。かつてのように、素直に彼らを見て楽しめない“しこり”が残ってしまった。どんなに取り繕っても、それは事実だ。
今後、5人はそれぞれに、この現実を踏まえて芸能活動を行っていくことになる。いや、実際の活動を通じて、イメージを回復し、しこりを解消していこうと努力するだろう。
“夜空ノムコウ”には明日が待っていたが、“SMAPノムコウ”にも、きっと何かが待っているはずだ。たとえそれが、「あのころの未来」とは違っていたとしても。
(iRONNA 2016.12.31)